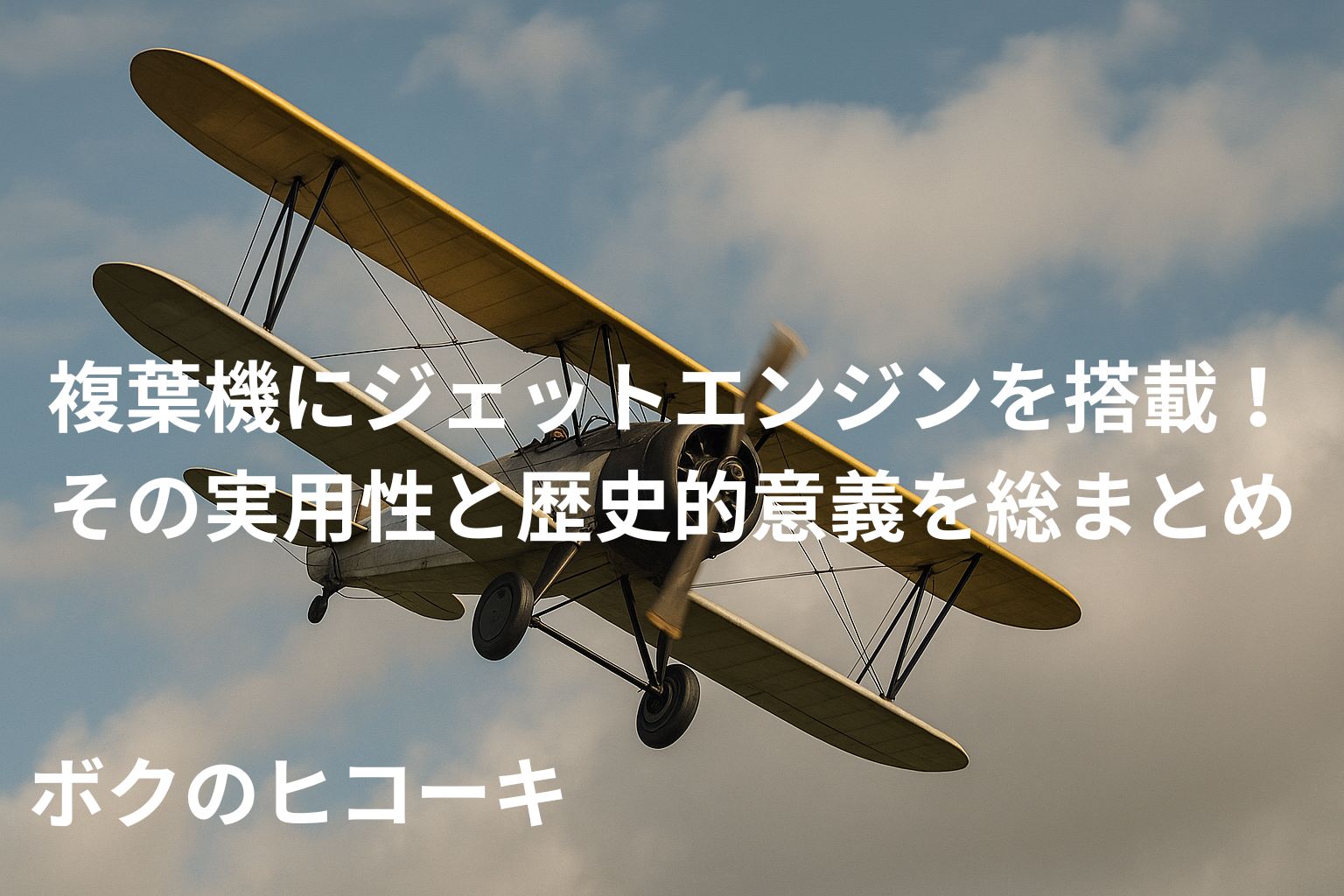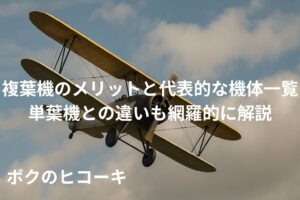「複葉機 ジェット」と検索する方の多くは、航空機の進化における意外な組み合わせや、歴史的な技術背景に興味を持っているのではないでしょうか。複葉機といえば第一次世界大戦などで活躍したクラシックな航空機の象徴ですが、実はジェットエンジンと組み合わせた試みも存在していました。
本記事では、複葉機の最高速度や「複葉機はなぜ廃れたのか」といった基本的な技術的背景から、現在も現役で使用されている機体、さらにはブーゼマン複葉機のような最先端の研究事例まで幅広く解説。
また、「世界最強の複葉戦闘機」や「世界で最も遅いジェット機」と称される機体の実例を紹介しながら、複葉機とジェット推進の関係性を探っていきます。さらに、レーダーとの関係や歴代の名機についても触れ、複葉機という航空技術の遺産が現代にどのような影響を与えているのかを紐解いていきます。
過去と未来をつなぐテーマとして、複葉機の魅力と限界をぜひ一緒に見ていきましょう。
- 複葉機とジェットエンジンの相性や技術的な課題
- 複葉機が廃れた歴史的背景と構造的な理由
- 世界唯一の複葉ジェット機M-15の特徴と失敗例
- 現在も使用される複葉機やその戦術的価値
複葉機にジェット機が誕生した理由と背景

- 複葉機の最高速度は?
- 複葉機はなぜ廃れたのか?
- ジェットエンジンとの相性の悪さ
- 複葉機の設計思想と時代背景
- 世界で最も遅いジェット機は?
- M-15ベルフェゴルとはどんな機体か
複葉機の最高速度は?
複葉機の最高速度は、機体の設計やエンジン性能によって異なりますが、一般的には時速400kmから520km程度が限界とされています。これは第二次世界大戦期までに開発された複葉機の性能を基にした目安です。
まず基本的な理解として、複葉機は上下2枚の主翼を持つ構造上、大きな揚力を得られる反面、空気抵抗が大きくなるという特徴があります。特にストラット(支柱)や張線といった支持構造が空気の流れを乱し、速度を上げるうえでの制約となっていました。
代表的な高速複葉機としては、イタリアのフィアットCR.42があります。この機体は複葉戦闘機の中でも特に高い性能を持ち、改良型の「CR.42B」では最大で時速520kmに達しました。これは複葉機としては驚異的な速度であり、“複葉戦闘機の最終進化形”とも呼ばれています。
一方で、一般的な複葉戦闘機(たとえば日本の九五式戦闘機など)は、時速400km前後の性能が主流でした。設計思想そのものが「低速・高揚力・高い操縦性」に重点を置いていたため、単葉機のような高速化には限界があったのです。
このように、複葉機の最高速度は、設計上の制約から大きくは伸びず、400〜520km/hの範囲にとどまりました。速度の限界があるにもかかわらず、初期の航空戦においては機動性や扱いやすさから重要な役割を果たしていたことも、複葉機の存在意義を理解するうえで欠かせません。
複葉機はなぜ廃れたのか?

複葉機が主流の地位から退いた背景には、航空技術の進歩と運用ニーズの変化が深く関係しています。1930年代以前は航空機の中心的存在だった複葉機ですが、その設計思想が技術革新に追いつかず、徐々に姿を消していきました。
構造面では、複葉機特有の課題がありました。
- 上下2枚の翼とそれを支える張線・支柱が必要なため、空気抵抗が非常に大きい
- 空気抵抗の増加により、速度性能が劣り、時代とともに不利な構造となった
- 初期の航空機ではエンジン出力が小さく、揚力を確保するために複葉構造が必要だったが、後に不要になった
さらに、材料技術の進化も大きな転換点となりました。
- 初期の複葉機は主に木材や布で作られ、剛性を確保するには翼の枚数を増やすしかなかった
- 金属素材の普及により、強度と軽量性を兼ね備えた単葉機の設計が可能に
- 単葉構造の方が整備性や耐久性にも優れていた
時代のニーズも、複葉機の終焉を早める要因となりました。
- 軍事・民間ともに「高速・高高度・長距離飛行」が重視されるようになった
- 複葉機の「低速・短距離・高揚力」重視の特性は、現代的な航空要件と合致しなくなった
- その結果、1930年代後半以降は複葉機の新規開発が激減し、戦闘機としての役割も失われた
このように、複葉機は「低出力・低速」が前提だった時代の産物であり、航空機に求められる性能が変化する中で自然と淘汰されていったのです。現在では、複葉機は農業用や曲技飛行用、または歴史的保存機として限られた用途でのみ生き残っています。
ジェットエンジンとの相性の悪さ
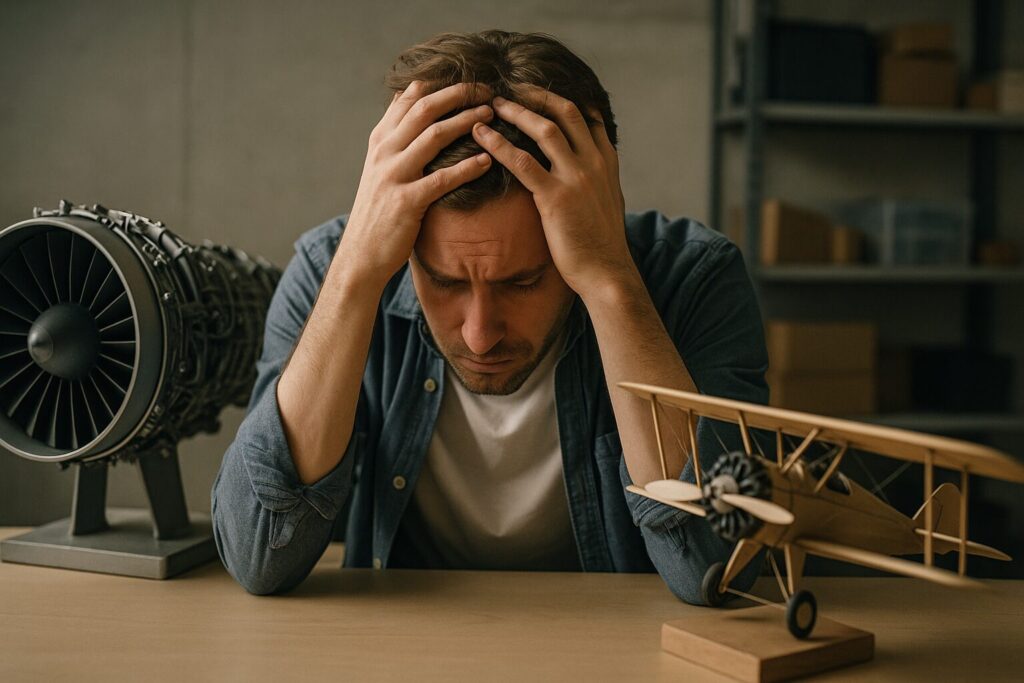
複葉機とジェットエンジンの組み合わせが極めて珍しいのは、それぞれの構造や運用目的が根本的にかみ合わないためです。両者が持つ性能特性が物理的に矛盾しており、設計上の相性が非常に悪いことが大きな理由となっています。
複葉機とジェットエンジンが合わない主な要因は以下のとおりです。
- 複葉機は低速飛行に必要な揚力を得るため、上下2枚の主翼を備えている
- 主翼間にストラット(支柱)や張線を配置するため、空気抵抗が非常に大きくなる
- ジェットエンジンは高速・高高度飛行に適した推進装置であり、空気抵抗の少ない機体設計が前提
- 空気抵抗が多い複葉構造では、ジェットエンジンの性能を十分に活かせない
- ジェット機でありながら低速でしか飛行できないという設計上の矛盾が生じる
この不適合を象徴する機体が、ポーランドで開発されたM-15ベルフェゴルです。
- 世界唯一の実用複葉ジェット機として開発された農業機である
- 最大速度はわずか約200km/hと、ジェット機としては異例の低速性能
- 高い抗力のため、ジェットエンジンの推力を速度に転換できなかった
- スロットル操作に対する応答が遅く、農業用途には不向き
- 安定性・操縦性に問題があり、運用効率も悪かったため短期間で退役
このように、複葉機とジェットエンジンは目的と特性がかけ離れており、両者を組み合わせるメリットはほとんど存在しません。現代の航空設計においてもこの構造を採用する機体は見られず、唯一の例外であったM-15が技術的実験として終わったことからも、複葉機とジェットエンジンの相性の悪さは明らかだと言えるでしょう。
複葉機の設計思想と時代背景

複葉機は、航空技術がまだ未成熟だった黎明期において、「飛ぶために必要不可欠な構造」として生まれました。20世紀初頭は、現在のような高出力エンジンや強度のある素材が使えなかったため、複葉構造が飛行機設計の最適解とされていたのです。
複葉機の誕生と採用には、以下のような技術的・運用的背景があります。
- 当時のエンジン出力は非常に低く、揚力を補うために上下2枚の主翼を持つ構造が求められた
- 翼を上下に重ねることで、広い翼面積を確保しつつ機体の全幅を抑えられた
- 空気中での旋回性能が高く、狭い空域でも自由に操縦できる機動性を実現
- 木材や布といった軽量で強度の乏しい素材が主流だったため、ストラットや張線で補強しやすい構造が必要だった
- 単葉機では確保できない剛性を、複葉構造で補えたため、安定した飛行が可能だった
特に以下のような名機が、複葉機の設計思想を象徴しています。
- ライト兄弟による「フライヤー号」:初飛行を達成した実験機として歴史的価値が高い
- 英国の「ソッピース・キャメル」:第一次世界大戦の主力戦闘機として活躍し、高い運動性を発揮した
ただし、時代が進むと複葉構造の欠点が顕在化していきます。
- 翼が2枚あるため空気抵抗が大きくなり、速度や航続距離に不利が生じた
- 金属製材料の登場により、単葉構造でも高い強度が得られるようになった
- エンジン出力が向上し、単葉機でも十分な揚力が確保できるようになった
- 「高速・長距離飛行」を重視する時代に、複葉構造の意義が薄れていった
1930年代以降は、こうした理由から単葉機への置き換えが急速に進み、複葉機は戦闘機や主力機としての役目を終えることとなりました。
このように、複葉機は航空機設計の初期段階で極めて重要な役割を果たした存在であり、その設計は当時の技術力・素材・運用ニーズを色濃く反映したものであったといえます。
世界で最も遅いジェット機は?

「世界で最も遅いジェット機」とされているのは、ポーランドのPZL社が1970年代に開発した農業用複葉ジェット機「M-15 ベルフェゴル」です。この機体の最高速度はおよそ200km/hであり、ターボファン方式のジェット機としては異例の低速で飛行しました。
一般的に、ジェット機といえば高速・高高度飛行を得意とし、戦闘機や旅客機といった高性能機を連想するかもしれません。しかし、M-15はこの常識を覆す特殊な存在です。なぜなら、そもそもこの機体は低速での安定飛行を目的とした農業機として設計されたからです。
ただし、低速設計とはいえジェットエンジンを採用しており、その結果としてジェット機としての分類に該当しながら、最低レベルの速度性能を持つ機体となりました。この点で、M-15は航空史において非常にユニークな記録を持つ存在です。
また、同機の開発背景には、ソビエト圏で進められていた燃料の統一構想も影響しています。つまり、レシプロ機からジェット燃料対応機に切り替える流れの中で、農業用航空機も例外ではなく、M-15のような機体が生まれたのです。
ただし、結果的には速度が遅すぎて経済性に乏しく、また操縦性の問題も重なり、わずか数年で退役しています。このことから、世界で最も遅いという称号は「異例であったが成功しなかった試み」という意味合いも含まれています。
このように、M-15 ベルフェゴルは単なる記録上の遅さだけでなく、設計思想や歴史背景も含めて、他に類を見ない特異なジェット機だったといえるでしょう。
M-15ベルフェゴルとはどんな機体か

M-15ベルフェゴルは、ポーランドのPZL社が1970年代に開発した、世界で唯一の量産された複葉ジェット機です。正式には農薬散布用の農業機として設計されましたが、その特異な構造や性能から、航空史における極めて例外的な存在として知られています。
まず外観からして、M-15は他のどの航空機とも似ていません。
上下に2枚の主翼を持つ複葉構造に加えて、中央上部にターボファンジェットエンジン(イーフチェンコAI-25)を1基搭載し、双尾翼型のテイルブームを備えるという非常に珍しいスタイルでした。この姿から「ベルフェゴル(悪魔の名)」というあだ名が付けられたほどです。
この機体が開発された背景には、ソ連(当時)の農業政策と燃料政策があります。具体的には、大規模な国営農場(コルホーズやソフホーズ)での農薬散布作業を効率化するために、既存のレシプロ機An-2に代わるジェット燃料を使用できる後継機として設計されたのがM-15でした。
ところが、理想と現実には大きな乖離がありました。ジェットエンジンは低速域では効率が悪く、さらに複葉構造による抗力の増大もあり、飛行性能は期待ほどではありませんでした。横方向の安定性も不十分で、特にタンク満載時の操縦性には課題が多く、運用面での安全性にも懸念があったのです。
さらに、オイルショックによる燃料価格の高騰が追い打ちとなり、M-15の運用コストは想定以上に膨らみました。結局、計画されたほどの調達は実現せず、175機の生産にとどまり、1983年には完全退役となりました。
このように、M-15ベルフェゴルは「複葉機にジェットを載せる」という設計思想そのものが極めて珍しく、歴史的・技術的に見ても唯一無二の存在です。失敗に終わったとはいえ、航空機設計の中で大胆な試みが行われた例として、今なお多くの航空ファンに語り継がれています。
参考資料:乗り物ニュース
複葉機にジェットエンジンの実例と技術的特異性

- 世界最強の複葉戦闘機は?
- ブーゼマン複葉機の最新研究動向
- 現役で使われている複葉機とは
- 複葉機とレーダー探知の関係
- 名機と呼ばれる複葉機の系譜
世界最強の複葉戦闘機は?

複葉戦闘機の歴史の中で「世界最強」と称される機体は、イタリアのフィアットCR.42です。この機体は第二次世界大戦期に実戦投入され、複葉機としては異例の高性能と戦果を記録しました。
CR.42の特徴としてまず挙げられるのは、その優れた運動性能です。複葉構造の強みである高い機動性を活かし、急旋回や格闘戦に強く、多くのエースパイロットを生み出しました。特に初期の戦場では、敵機がこの複葉機を味方の練習機と誤認したことで優位に立ったケースもあったと報告されています。
加えて、改良型である「CR.42B」には高性能なダイムラー・ベンツ製のエンジンが搭載され、最大速度は520km/hにまで達しました。これは複葉機としては最高クラスの性能であり、「複葉戦闘機の最終進化形」とも呼ばれます。
耐久性の面でも意外な評価が。布張りの主翼や胴体は、一見すると脆弱に見えますが、敵弾が貫通するだけで爆発や火災を引き起こしにくいため、実戦では意外な粘り強さを発揮したとする記録も残っています。
また、このCR.42は総生産数が約1,800機に達し、複葉戦闘機としては非常に多く製造されたことも注目に値します。さらに、終戦後もしばらくの間、練習機や夜間戦闘機として使用され続けました。
このように見ていくと、フィアットCR.42は単なる旧式の複葉機ではなく、実用性・戦果・生産数のすべてにおいて傑出した存在であり、「世界最強の複葉戦闘機」と呼ばれるにふさわしい機体だといえます。
ブーゼマン複葉機の最新研究動向

ブーゼマン複葉機とは、1930年代にドイツの航空力学者アドルフ・ブーゼマンが提唱した特殊な複葉翼設計の理論モデルです。この設計は、従来の複葉機とは異なり、超音速飛行における空気抵抗(衝撃波抗力)を削減することを目的としています。
最大の特徴は、上下の2枚の主翼から発生する衝撃波を互いに干渉させて相殺するという仕組みにあります。これにより、通常の単翼設計では発生する強い抗力を抑え、理論上はより効率的な超音速巡航が可能になるとされていました。
当時の技術ではこの理論を実機に反映させることは困難でしたが、近年、再び研究対象として注目を集めています。特に、東北大学の研究グループが行っている数値シミュレーションにおいて、ブーゼマン型複葉翼の持つ衝撃波相殺効果の有効性が改めて検証されているのです。
最新の研究では、単なる上下二枚の翼ではなく、翼端を閉じる「閉鎖型複葉翼」のような形状を用いて、迎え角の変動や翼端干渉の問題を軽減する設計が模索されています。このような閉鎖構造によって、従来型複葉の欠点を解消しつつ、理論上の利点を最大限に引き出すアプローチが進められているのです。
現在のところ、これらの研究は風洞実験やコンピュータ上での空力解析の段階にとどまっており、実用機としての開発には至っていません。しかし、今後の超音速航空機やスペースプレーンの分野では、このような設計思想が新たな形で応用される可能性も指摘されています。
つまり、ブーゼマン複葉機の研究は、過去の理論に現代の技術を掛け合わせることで、未来の高速航空機設計に活かされようとしている最前線の研究であるといえるでしょう。
現役で使われている複葉機とは

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表的な現役複葉機 | アントノフAn-2(ロシア製、1947年開発) |
| 主な用途(軍用) | 輸送、農業支援、空挺投下、極地作戦など |
| 現役数 | ロシア連邦軍で約200機が稼働中 |
| 主な強み | 低速安定性、頑丈な構造、短距離離着陸性能 |
| 特殊な特徴 | 木材・布構造によるステルス性があるとされる |
| 注目される理由 | 対ドローン作戦など新用途での活用可能性 |
| 民間での活用 | 農薬散布、航空ショー、アクロバット飛行 |
| 民間での代表機 | ピッツ・スペシャル、スタンプSV.4など |
| 整備・運用面の課題 | 整備性・運用効率が低く、用途が限定的 |
| 戦闘機や大型機での現状 | 複葉構造は既に技術的に淘汰されている |
| 複葉機の魅力 | 目的に合えば高い実用性を維持している |
現代においても、複葉機は完全に消え去ったわけではありません。数は少ないものの、特定の目的に特化した複葉機が今なお現役で使用されています。その代表例が、ロシア(旧ソ連)製のアントノフAn-2です。
An-2は1947年に開発された大型の複葉機で、主に輸送、農業、空挺部隊の投下、さらに極地での作戦などに用いられてきました。驚くべきことに、今でもロシア連邦軍では約200機が現役で使用されているとされ、不整地離着陸や短距離輸送といった任務でその価値を発揮しています。
この機体の最大の強みは、低速でも安定して飛行できる性能と、未舗装の滑走路でも離着陸可能な頑丈な設計にあります。さらに、木材や布で構成された構造がレーダー反射を抑えるため、実質的に「ステルス性」を持つとも言われています。この特性が、対ドローン作戦など新たな用途でも注目されている理由の一つです。

民間用途においても、複葉機は農薬散布や航空ショー、アクロバット飛行などで使用されています。ピッツ・スペシャルやスタンプSV.4のような小型複葉機は、優れた操縦性を持ち、エアロバティクスの分野で今も人気です。
ただし、現代の主流航空機と比べると、複葉機は整備性や運用効率の面で不利な点が多く、運用は非常に限定的です。特に戦闘機や大型輸送機の分野では、すでに複葉構造は技術的に淘汰されています。
それでも、用途が合致すれば今も高い実用性を発揮するのが複葉機の魅力です。特にAn-2のような実用機は、「必要な環境で最も信頼できる機体」として、今後もしばらくは現役で使われ続けると見られています。
複葉機とレーダー探知の関係

複葉機は現代の航空戦において主流ではないものの、レーダー探知に対する特異な特性を持つ機体として、一部で注目されています。特に「複葉機はレーダーに映りにくい」という見解は、第二次世界大戦後の電波探知技術の発展に伴い、軍事分野でたびたび語られてきました。
複葉機がレーダーに対して持つ特性は、以下のような要因によるものです。
- 木材や布を用いた構造材によって、金属部品の面積が少ない
- 金属面の反射が小さいため、レーダー波が強く戻らない傾向がある
- 支柱や張線などの細かな構造が、レーダー波を拡散・散乱させやすい
- 凹凸の多い機体形状により、レーダー波の一方向的な反射を抑えられる
- 角度によりレーダー波を逸らすステルス機の設計思想と類似した構造特性がある
実際にこの特性を利用した事例も報告されています。
- 旧ソ連製のAn-2複葉機が、レーダーによる探知をかく乱する“囮”として使用された
- 対ドローン作戦において、意図的にレーダー反射が少ない機体として運用された例がある
- 防空システムの自動追尾を混乱させ、センサーの誤作動や無駄な迎撃を誘導したケースも存在する
しかしながら、こうした運用は例外的であり、万能ではありません。
- 現代の高性能レーダーや多波長センサーは、低反射の対象でも探知可能
- 複葉機だからといって「完全にレーダーに映らない」わけではない
- 過信すれば逆に誤った戦術判断を招くリスクもある
このように、複葉機は本来の設計目的とは異なる文脈で、現代の軍事環境において新たな価値を見出される存在となっています。古い構造であっても、レーダー探知技術との相互作用により、思わぬ再評価が進んでいる点は非常に興味深い事例です。
名機と呼ばれる複葉機の系譜

| 機体名 | 国籍 | 特徴・功績 |
|---|---|---|
| ソッピース・キャメル | イギリス | 高い運動性と火力を持ち、第一次世界大戦で活躍。レッドバロン撃墜で有名 |
| カーチス JN-4 “ジェニー” | アメリカ | 軍民両用で活躍し、多くのパイロット育成に貢献。民間航空の発展に寄与 |
| フォッカー Dr.I | ドイツ | 三葉機ながら複葉系統に属し、高い旋回性能で空中戦を制覇。レッドバロンの搭乗機として有名 |
| 共通点 | 技術面・歴史面で航空史に影響を与え、文化的象徴ともなっている | |
| 現在の扱い | レプリカが航空ショーで飛行するなど、保存・再評価が進行中 | |
複葉機の歴史には、数多くの“名機”と呼ばれる機体が存在します。これらは、単なる技術的成功にとどまらず、歴史や戦術、さらには文化的影響にまで及ぶ存在感を持っていた点は特筆ものです。

まず代表的なのが、第一次世界大戦で活躍したソッピース・キャメル(Sopwith Camel)です。この機体は、イギリス空軍が導入した複葉戦闘機で、抜群の運動性と火力を兼ね備えていました。
ドイツのエースパイロット、マンフレート・フォン・リヒトホーフェン(通称レッドバロン)を撃墜した機体としても有名であり、その存在は歴史の転換点ともなりました。

続いて、アメリカのカーチス JN-4 “ジェニー”も忘れてはならない名機です。この機体は第一次世界大戦後、軍用から民間用に転用され、多くのパイロット育成に貢献しました。アメリカの航空産業黎明期を支えた機体として、今日でも高く評価されています。

特に、ドイツのフォッカー Dr.Iは名機の筆頭と言えます。三葉機として分類されますが、複葉設計の延長上にあるものです。特に「レッド・バロン」(赤い男爵)の異名で呼ばれたリヒトホーフェンが操縦していたことで知られています。小型で軽量ながら、空中戦で高い旋回性能を誇り、当時の敵機を圧倒しました。
これらの名機に共通するのは、単に戦果を挙げたというだけでなく、技術的・歴史的に大きな影響を与えたという点です。また、いずれの機体も修復・保存が進められており、現代でも航空ショーなどでレプリカ機が飛行する姿を目にすることができます。
このように、複葉機の系譜には数々の名機が連なっており、それぞれが異なる物語と功績を持っています。単なる旧式航空機ではなく、航空史の重要な節目を築いた機体たちであることを、あらためて認識すべきでしょう。
複葉機のジェットエンジンの特異性と歴史的意義を総括
この記事のポイントをまとめます。
- 複葉機の最高速度はおおむね時速400〜520km程度
- 空気抵抗の大きさが複葉機の速度性能を制限していた
- 単葉機の登場により複葉機は主流から外れた
- 材料やエンジン技術の進歩が複葉構造を時代遅れにした
- ジェットエンジンは高速飛行を前提とする設計思想を持つ
- 複葉構造はジェット推進と根本的に相性が悪い
- 世界唯一のジェット複葉機はM-15ベルフェゴルである
- M-15はジェットでありながら最高速度200km/hと極端に遅かった
- M-15の運用は短期間で終了し、失敗事例とされている
- 初期の複葉機は低出力エンジンでも揚力を得るための工夫だった
- フィアットCR.42は複葉戦闘機の最終進化形として知られている
- ブーゼマン複葉機は超音速時代における空力研究として再注目されている
- 現在でもAn-2など一部の複葉機は限定的に運用されている
- 木製・布製の複葉機はレーダー反射が少なく、囮運用例もある
- 名機と呼ばれる複葉機は歴史・戦果・技術面で高く評価されている
最後までお読みいただきありがとうございました。
おすすめ記事:
飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策
【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説
戦闘機 エンジンの仕組みを徹底解説|ジェット推進の原理と特徴とは
ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説