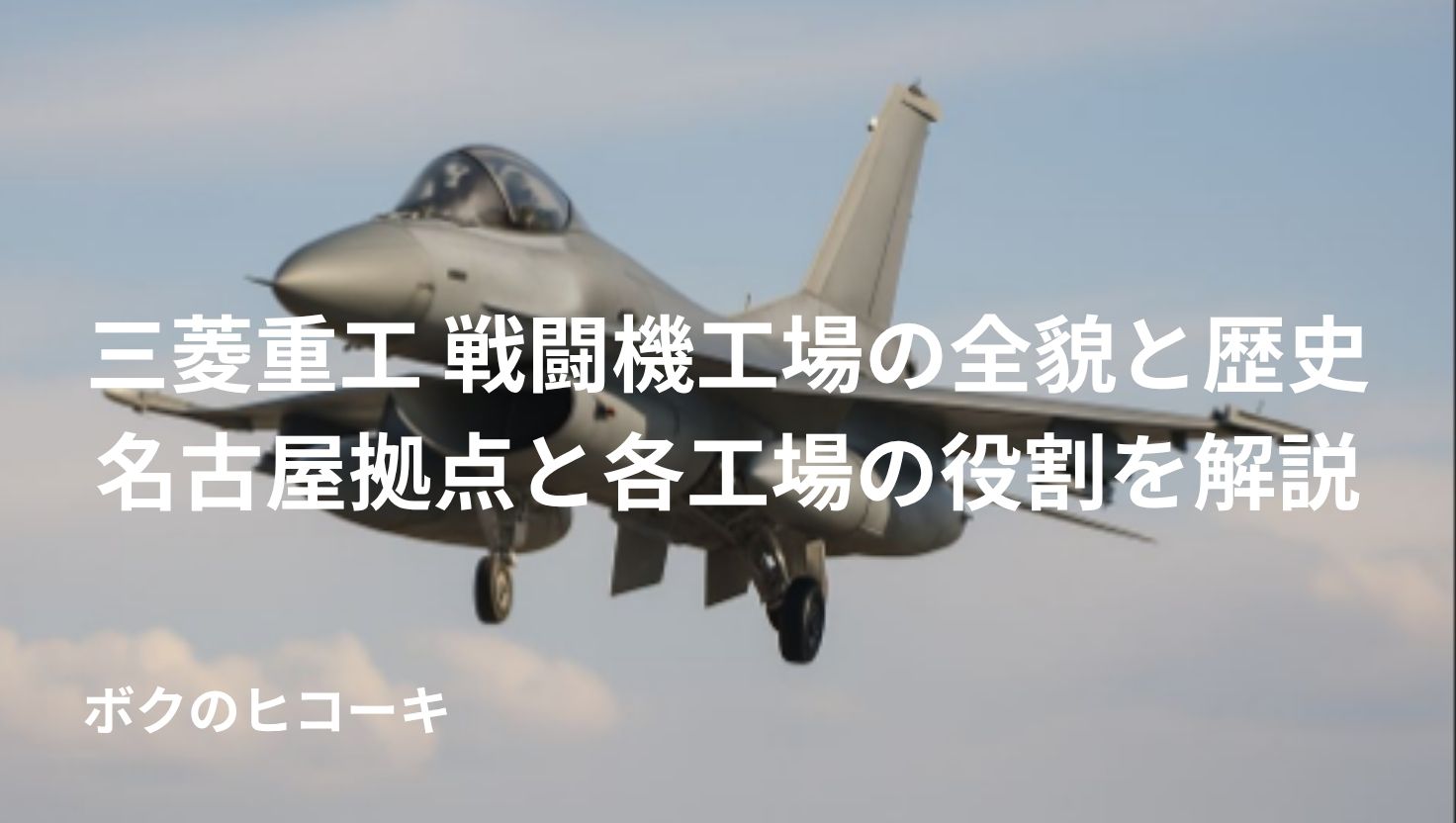三菱重工業は、日本を代表する重工業メーカーとして、防衛・航空宇宙分野においても長年の実績を誇ります。中でも「三菱重工 戦闘機 工場」は、名古屋地域を中心に数多くの拠点を構え、日本の防衛装備を支える重要な存在です。
本記事では、小牧工場をはじめとした工場一覧や、それぞれの拠点が果たしている役割を詳しくご紹介します。
また、「日本の戦闘機を作っている会社は?」という疑問に対しても、三菱重工の歴史的な歩みや、現在の航空宇宙事業部の活動を通じて明らかにしていきます。
戦闘機の歴史や、ミサイル 工場における開発事情、三菱重工のロケットはどこで打ち上げられるのかといった宇宙分野の話題にも触れながら、三菱重工の総合力を解説していきます。
さらに、名古屋 工場 工場見学の可否や注意点、名古屋航空宇宙システム製作所 年収の実態、三菱重工のタービンの拠点はどこかといった就職希望者にとっても気になる情報を網羅。三菱重工の就職難易度や求められるスキルについても取り上げ、進路を検討する方にも役立つ内容となっています。
本記事を通じて、三菱重工 戦闘機 工場の全体像とその社会的な意義を理解し、名古屋地域に集約された日本の最先端技術の現場を深く知るきっかけになれば幸いです。
- 三菱重工の戦闘機工場の種類と役割
- 各工場の所在地と担当する製造工程
- 小牧工場を中心とした最終組立の重要性
- 航空宇宙・ミサイル・ロケット事業との関係性
【三菱重工】戦闘機工場の全体像と役割

- 工場一覧とそれぞれの拠点の特徴
- 小牧工場が担う最終組立の重要性
- 名古屋工場の工場見学は可能?見学方法と注意点
- ミサイル工場の機能と所在地
- 三菱重工の航空宇宙事業部 事業内容は?
- 三菱重工のロケットはどこで打ち上げられますか?
工場一覧とそれぞれの拠点の特徴
三菱重工業の航空宇宙分野における主要な工場は、名古屋地域に集中しており、それぞれが専門的な役割を担っています。これらの拠点は、設計から最終組立、さらには宇宙関連機器の製造まで、幅広い工程を分担しながら高度な一貫生産体制を構築しています。
代表的な工場とその特徴は以下の通りです:
- 大江工場(名古屋市港区)
- 航空機の基礎設計および部品製造を担当
- 戦前には零戦の開発も行い、日本の航空技術の原点ともいえる歴史を持つ
- 「大江時計台航空史料室」を併設し、復元展示による技術と歴史の伝承も行っている
- 小牧南工場(愛知県西春日井郡豊山町)
- F-2、F-15J、F-35Aなどの戦闘機や民間機SpaceJet(旧MRJ)の最終組立を実施
- 航空機の整備・検査・飛行試験も行う、中核的な組立拠点
- 航空自衛隊の機体整備の拠点として、防衛分野でも極めて重要な位置づけ
- 飛島工場(海部郡飛島村)
- 航空機の部分構造や宇宙機器の組立を専門に担当
- ロケット(H-IIA・H-IIB)や国際宇宙ステーション「きぼう」の部品製造にも関与
- 宇宙開発に特化した高度な技術力を備える拠点
- 小牧北工場(名古屋誘導推進システム製作所)
- ミサイル(パトリオット、長射程型など)や航空宇宙用エンジンの製造を実施
- 誘導制御機器の開発も担い、日本のミサイル防衛における重要な生産拠点
これらの工場は、単なる製造拠点ではなく、それぞれの分野で専門性を発揮しながら相互に連携しています。名古屋周辺にこうした機能が集約されていることは、日本の航空宇宙産業全体の競争力を高める大きな要因となっています。
小牧工場が担う最終組立の重要性

小牧工場、特に小牧南工場は、三菱重工業の航空機製造において極めて重要な役割を果たしています。特に防衛用航空機の「最終組立」「試験」「整備」などを担う拠点として、日本の安全保障に直接関わる基幹工場です。
この工場の最も大きな特徴は、F-2、F-15J、F-35Aといった自衛隊主力戦闘機の最終組立ラインが存在していることです。
これにより、設計・部品製造を担当する他工場からのパーツを集約し、完成機としての品質検査や飛行試験を経て納品されるまでを一括で管理する体制が整っています。つまり、小牧南工場は完成品としての航空機の信頼性を担保する“最後の砦”ともいえる存在です。
例えば、F-2戦闘機はアメリカのF-16をベースに開発されましたが、日本の地理的特性や運用要件に応じたカスタマイズが施されており、極めて精密な最終調整が求められます。これらの作業が高い精度で実現されるのも、小牧南工場の技術力と品質管理体制が確立しているからこそです。
一方で、このような機密性の高い作業を伴うことから、外部からのアクセスや取材、見学は厳しく制限されており、安全保障やサイバーセキュリティの観点からも徹底した管理体制が敷かれています。

また、民間航空機として開発されたMRJ(Mitsubishi SpaceJet)もこの工場で最終組立が行われていました。このように、小牧工場は軍用・民間両分野での航空機開発の最前線でもあり、三菱重工の航空機技術の集積地として高く評価されています。
以上のことから、小牧工場は航空機産業における製造工程の中でも、信頼性と性能を保証する極めて重要なポジションを担っているのです。
参考資料:MRJ/SpaceJet appears officially done |
名古屋工場の工場見学は可能?見学方法と注意点

三菱重工業の名古屋地域にある工場の中で、工場見学が可能な拠点は限られています。特に「大江工場」と「小牧南工場」は、見学施設が併設されていたことで知られていますが、自由に立ち入れるわけではなく、事前の予約や公開条件があります。
見学に関する主な情報は以下のとおりです:
- 大江工場(名古屋市港区)
- 敷地内に「大江時計台航空史料室」が設置されている
- 零戦や秋水といった歴史的戦闘機の復元展示が見学可能
- 航空史に関心のある個人にも学びの多い展示内容
- 事前に電話予約が必要で、見学可能日は月曜・木曜の9時~15時に限定
- 自由見学形式のためガイドツアーはなし
- 館内には丁寧な解説資料が整備されている
- 小牧南工場(愛知県豊山町)
- かつてMRJミュージアムが併設されていた
- 2023年のミュージアム閉館以降、現在は見学休止中
- 将来的な再開予定については公式情報の確認が必要
見学を希望する際には、以下の注意点にも留意する必要があります:
- 三菱重工の工場は観光地ではなく、見学は企業の厚意による特別公開
- 時間厳守や撮影ルール、立入制限などのマナー遵守が求められる
- 防衛装備が含まれる区域では、撮影や立ち入りが厳しく制限されている
- 特に飛島工場や小牧北工場は、ミサイル・宇宙機器を扱うため一般公開の対象外
- 研究機関や教育関係者など、一部の特別な申請者に限り見学が許可されることがある
このように、三菱重工の名古屋工場における見学は限られた施設でしか実施されていませんが、航空技術や戦闘機の歴史を体感できる貴重な機会です。見学を検討する際は、必ず事前に公式の最新情報を確認し、計画的な予約を行うことが大切です。
ミサイル工場の機能と所在地

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 拠点名 | 名古屋誘導推進システム製作所 小牧北工場 |
| 所在地 | 愛知県小牧市 |
| 設立年 | 1972年 |
| 主な機能 | ミサイル、航空・宇宙用エンジン、制御システムの開発・製造 |
| 代表的な製品 | PAC-2、PAC-3、12式地対艦誘導弾、長距離ミサイル |
| 先進開発分野 | 極超音速滑空兵器(HGV)、ハイブリッド誘導・推進技術 |
| セキュリティ体制 | 高度な品質保証・サイバーセキュリティを導入 |
| 見学の可否 | 不可(防衛関連施設のため非公開) |
| 施設の特徴 | 研究・試験・製造の一体型機能を有する |
三菱重工業におけるミサイル製造の中心的な拠点は、愛知県小牧市にある「名古屋誘導推進システム製作所 小牧北工場」です。この工場は1972年に開設され、日本の防衛装備に欠かせない誘導兵器や航空・宇宙用エンジン、制御システムなどの開発・製造を担っています。
この工場の機能の中核は、防衛省向けのミサイル開発とその製造です。具体的には、パトリオットミサイル(PAC-2、PAC-3)をはじめ、国産ミサイルである12式地対艦誘導弾の能力向上型、さらには射程1,000km以上の長距離ミサイルの開発などにも携わっています。

これらの製品は、日本のミサイル防衛システムや離島防衛、敵基地攻撃能力の強化に直結するものです。
また、近年では極超音速滑空兵器(HGV)など新たな脅威に対応する先進技術の研究・試験も進められており、小牧北工場はそれらの最前線に位置しています。防衛装備の高度化に伴い、誘導技術、推進システム、サイバーセキュリティなど複数の先端領域が統合されたハイブリッドな技術開発が求められているのです。
このように、同工場は単なる製造施設ではなく、研究・試験・生産を一体化した総合的な機能を持つミサイル開発拠点としての役割を果たしています。ただし、防衛関連施設であることから見学や公開情報は限られており、詳細な設備内容や作業工程は公開されていません。
ミサイルの安全な製造・管理体制を維持するために、高度な品質保証やサイバーセキュリティ対策も実施されており、国防に関わる施設としては非常に高いセキュリティ水準が求められています。地政学的リスクが高まる中、このような製造拠点の存在は日本の防衛力を維持するうえで極めて重要だといえるでしょう。
参考資料:防衛省 [JASDF] 航空自衛隊
三菱重工の航空宇宙事業部 事業内容は?

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業部の構成 | 防衛、民間航空機、宇宙開発の3本柱で構成 |
| 防衛航空機分野 | F-2、F-15J、F-35Aの製造整備、次世代戦闘機F-3の開発に参画 |
| その他の防衛機 | ヘリコプター、練習機、哨戒機などの一部生産や分担製造 |
| 民間航空機分野 | MRJ(Mitsubishi SpaceJet)開発、ボーイング・エアバスとの共同プロジェクトに関与 |
| 得意分野 | 複合材による軽量・高性能部品の製造、燃費・環境性能重視の部材開発 |
| 宇宙関連 | H-IIA、H3ロケットの開発、国際宇宙ステーションの「きぼう」やHTVの製造 |
| JAXAとの連携 | 信頼性の高い宇宙輸送システムを構築し、高評価を得ている |
| 中枢拠点 | 名古屋航空宇宙システム製作所(大江・小牧・飛島工場)に集約 |
| 運営体制 | 設計・製造・試験・納品まで一貫体制を構築 |
| グループ企業の役割 | MHIエアロスペースシステムズなどがソフトウェアや解析を支援 |
| 今後の展望 | 無人機や自律飛行技術にも対応可能な体制を整備 |
| 航空宇宙分野の重要性 | 国家戦略、環境問題、国際協力と深く関係し、重要性が高い |
| 三菱重工の目標 | 国内技術の発展と国際貢献の両立、持続可能な技術革新の推進 |
三菱重工業の航空宇宙事業部は、防衛、民間航空機、宇宙開発の3つの柱で構成されており、日本国内外の航空宇宙分野を支える重要な役割を担っています。この事業部は、航空機の設計から製造、整備、さらには宇宙機器の打ち上げ・輸送に至るまで、幅広い領域をカバーしているのが特徴です。
まず、防衛航空機分野では、F-2やF-15J、F-35Aといった自衛隊向け戦闘機の製造や整備を一貫して実施しています。
加えて、次世代戦闘機(通称F-3)の開発にも主契約者として参画しており、日本の防衛技術の中心を担っているといえるでしょう。このほか、各種ヘリコプターや練習機、哨戒機の一部の生産や分担製造も行われています。
次に民間航空機分野においては、かつての三菱リージョナルジェット(MRJ、のちにMitsubishi SpaceJet)に代表される小型ジェット旅客機の開発・製造経験があり、ボーイングやエアバスとの共同プロジェクトにも多数関与しています。
特に、ボーイング787の主翼構造など、複合材を用いた軽量で高性能な部品製造が得意分野です。環境性能や燃費効率を追求した部材開発にも注力しています。
そして宇宙関連では、日本の主力ロケットであるH-IIAやH3ロケットの開発・製造に加え、国際宇宙ステーションの日本実験モジュール「きぼう」、HTV(こうのとり)といった輸送機の製造も手がけています。これらはJAXAとの連携により進められ、信頼性の高い宇宙輸送システムとして世界でも高く評価されているのです。
航空宇宙事業部の中枢拠点は、名古屋航空宇宙システム製作所(大江・小牧・飛島工場など)に集約されており、設計から部品製造、組立、試験、納品までが一体となった運営体制が構築されています。
また、関連企業としてMHIエアロスペースシステムズなどのグループ会社がソフトウェアやシミュレーション解析を支えており、今後の無人機・自律飛行技術への対応力も備えています。
航空宇宙分野は、国家戦略と密接に関わると同時に、環境問題や国際協力とも関係する高度な分野です。三菱重工はその中で、国内技術の発展と国際貢献の両立を目指して、持続可能な技術革新を進めているのです。
三菱重工のロケットはどこで打ち上げられますか?

三菱重工が製造するロケットが打ち上げられているのは、鹿児島県にある「種子島宇宙センター」です。この施設は、日本の宇宙開発を支える最も重要なロケット発射拠点であり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)との連携のもと、各種人工衛星や探査機の打ち上げが行われています。
種子島宇宙センターは、1975年の設立以降、H-I、H-II、H-IIA、H-IIB、そして最新のH3ロケットまで、多くの打ち上げを成功させてきました。三菱重工はH-IIAロケット以降、ロケットの製造だけでなく、打ち上げサービス全体の請負事業者としても活動しており、宇宙輸送インフラの整備に重要な役割を担っています。
例えば、2025年6月にはH-IIAロケットの50号機が打ち上げられ、温室効果ガス観測衛星「いぶきGW」を搭載し成功しています。このように、気象観測・地球環境の監視・通信衛星の投入など、さまざまな目的に応じて打ち上げられるロケットの多くが三菱重工の製品です。
ロケットの製造は、主に愛知県の飛島工場などで行われ、各パーツが精密に組み立てられた後、種子島まで輸送されます。ここで最終チェックや燃料充填を経て、打ち上げに臨むという流れです。製造から打ち上げまでの一貫体制が整っているため、品質管理と信頼性の高さに定評があります。
ただし、ロケットの打ち上げは気象条件や技術的な要因に大きく左右されるため、延期や中止といったリスクも常に存在します。これは宇宙産業における宿命とも言えるものですが、三菱重工は高い打ち上げ成功率(H-IIAは97%以上)を維持しており、アジア地域では特に信頼される打ち上げ事業者の一つとされています。
このように、三菱重工のロケットは「種子島宇宙センター」で打ち上げられ、その成功の裏には国内工場の技術と精密な工程管理があるのです。日本の宇宙開発において不可欠な存在といえるでしょう。
参考資料:JAXA(宇宙航空研究開発機構)
【三菱重工】戦闘機工場の歴史と今後
- 三菱重工の戦闘機 歴史から見る技術の進化
- 日本の戦闘機を作っている会社は?
- 三菱重工の名古屋航空宇宙システム製作所 年収の実態
- 三菱重工の就職難易度は?求められる学歴と倍率
- 三菱重工のタービンの拠点はどこですか?
三菱重工の戦闘機 歴史から見る技術の進化

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発の始まり | 1930年代に旧日本海軍の要請で戦闘機開発を開始 |
| 零戦の開発 | 1937年から開発、超々ジュラルミン採用の革新的な戦闘機として1940年に制式採用 |
| 戦後の製造禁止 | 第二次世界大戦後に連合国によって一時製造を禁止される |
| 1950年代の再開 | F-86Fセイバーのノックダウン生産で航空機事業を再開 |
| ライセンス生産の展開 | F-104J、F-4EJ、F-15Jなどの米国機の生産で技術力を蓄積 |
| F-2戦闘機の開発 | F-16をベースに日本独自仕様で開発。複合材主翼やデジタル制御を導入 |
| F-2の意義 | 地理や戦術思想に合致した“日本主導型”戦闘機として設計 |
| 次期戦闘機F-3 | 日英伊による第6世代戦闘機を共同開発中。愛称候補は「烈風」 |
| F-3の特徴 | ステルス性、AI運用、自律飛行、ドローン連携など先進技術を搭載予定 |
| 継続する技術力 | 長年の蓄積によって日本の航空防衛の中核を支えている |
三菱重工業の戦闘機開発は、日本の航空技術史そのものとも言える長い歴史を持っています。1930年代に始まったその歩みは、戦前・戦中の名機「零戦」に代表される高性能機から、戦後の国産化・共同開発を経て、現在の第5世代戦闘機に至るまで進化を続けてきました。
古くは1937年、旧日本海軍の要請により三菱重工は零式艦上戦闘機(通称:零戦)の開発に着手しました。この機体は、超々ジュラルミンという軽量かつ高強度の合金を初めて本格採用し、高い機動性と航続距離を兼ね備えた当時としては画期的な戦闘機でした。
1940年の制式採用後、太平洋戦争において主力として活躍し、日本の航空技術の高さを世界に示す存在となったのです。
戦後、日本は連合国によって航空機の製造を一時的に禁止されましたが、1950年代に入り再び製造が許可され、三菱重工はF-86Fセイバー戦闘機のノックダウン生産から事業を再開します。そこからF-104J、F-4EJ、F-15Jといった米国機のライセンス生産を通じて技術を蓄積し、日本独自の生産体制と技術開発能力を高めていきました。
その成果として生まれたのが、1990年代から開発が進められたF-2戦闘機です。この機体はアメリカのF-16をベースにしつつ、日本独自の仕様を加えたもので、複合材を用いた主翼構造や、デジタルフライトコントロールシステムなどの先端技術が数多く導入されました。

F-2は単なるコピーではなく、日本の地理や戦術思想に適合した国産機として設計されており、戦後初の本格的な“日本主導型”戦闘機と評価されています。
近年では、F-2の後継として開発が進められている次期戦闘機(通称F-3、愛称候補「烈風」)にも三菱重工が中心となって参画。
この機体は日英伊の国際共同開発による「第6世代戦闘機」とされ、ステルス性能やAIによる自律運用、ドローンとの連携など、従来の戦闘機を超えた“システム・オブ・システムズ”としての役割が期待されています。
このように、三菱重工の戦闘機開発の歴史は、零戦から始まり、戦後の国産復興、そして現在の国際的な共同開発へと進化してきました。技術力の積み重ねと、それを支える工場・人材・ノウハウが、日本の航空防衛の中核を形づくっているのです。
参考資料:三菱重工 – Mitsubishi Heavy Industries
日本の戦闘機を作っている会社は?

現在、日本で戦闘機の開発・製造を行っている主な企業は「三菱重工業」です。同社は日本の防衛産業において中核的な役割を果たしており、戦前の零戦開発から始まり、戦後のライセンス生産、そして国際共同開発に至るまで、一貫して日本の戦闘機製造を牽引してきました。
戦闘機の設計・組立の中心を担っているのは三菱重工ですが、それを支える関連企業も重要です。
例えば、エンジン部分はIHI(旧石川島播磨重工業)が担当し、電子機器やレーダー、ミッションコンピュータなどは三菱電機やNEC、東芝といった大手電機メーカーが提供しています。それぞれが自社の専門技術を持ち寄り、日本の防衛装備品を構成しているのです。
現在開発中の次期戦闘機プロジェクト(F-3)は、三菱重工が主契約者として機体開発を担当し、エンジンはIHI、電子システムは三菱電機などが協力しています。このプロジェクトは英国のBAEシステムズ、イタリアのレオナルドと共同で進められており、グローバルな分担体制によって技術とコストの最適化が図られています。
ただし、すべてを国内で完結できるわけではなく、特に電子戦や人工知能などの分野では海外パートナーとの連携が欠かせません。これにより、日本の防衛技術は国内の強みを生かしつつ、世界的な開発潮流にも適応する体制を構築しています。
以上から、「日本の戦闘機を作っている会社は?」という問いに対しては、主に三菱重工業と回答できますが、それを取り巻く多くの企業との協力体制があってこそ、高度で多機能な戦闘機の開発・製造が可能になっているのです。
三菱重工の名古屋航空宇宙システム製作所 年収の実態

三菱重工業の中でも、名古屋航空宇宙システム製作所は航空機・宇宙機器の開発・製造を一手に担う主力拠点です。そこで働く社員の年収水準は、同社全体の平均に準じており、高水準であることが知られています。
2025年時点の三菱重工全体の平均年収はおよそ1,078万円で、平均年齢は42.5歳です。この水準から考えると、名古屋航空宇宙システム製作所の社員もほぼ同等の年収を得ているとみてよいでしょう。特に設計や技術職においては、高度な専門知識が求められるため、800万~1,000万円台の年収が珍しくありません。
具体的には、20代後半で約450万~500万円、30代で600万~700万円、40代で1,000万円以上になるケースもあります。管理職や主任・主幹クラスになると、年収は1,200万円~1,500万円に達することも。設計職は中でも最も高収入の部類に入り、業務の責任の重さと技術力が反映された結果です。
一方で、生産現場に近い製造職については、年収の平均はやや低めで、おおよそ589万円前後とされています。職種間で最大200万円以上の差があることもあり、これは業務内容や求められるスキルの違いによるものです。
たとえば、設計職や研究職は開発リスクや安全性、信頼性への責任が重いため、その分だけ報酬にも差がついています。
また、年収のほかに注目すべき点として、三菱重工は福利厚生が非常に充実しています。住宅手当や家族手当、企業年金制度、長期休暇制度などが整っており、トータルでの待遇面において非常に恵まれた職場環境が整備されているからです。
ただし、就職の難易度は高く、難関大学の理系学部を中心に採用される傾向が強いため、志望者には高度な専門性や一定の学歴が求められます。転職による中途入社も可能ではありますが、同様に高いスキルと経験が期待されるに違いありません。
このように、名古屋航空宇宙システム製作所での年収は、職種とキャリアに応じて幅がありますが、全体的に見れば非常に高待遇な環境が提供されています。航空宇宙産業の最前線で働く価値と報酬のバランスは、技術者にとって大きな魅力と言えるでしょう。
三菱重工の就職難易度は?求められる学歴と倍率

三菱重工業への就職は、国内屈指の難関として知られています。とくに航空宇宙、エンジン、タービンなどの技術系分野は高い人気を誇り、求められる人材像も高度です。2025年の東洋経済ONLINEによる難易度ランキングでは、同社は上位に位置しており、入社難易度指数はおよそ60台とされています。
さらに、リクナビに登録されたプレエントリー数と採用予定人数の比から推測される倍率は、おおむね24〜27倍と見られており、厳しい競争環境が浮き彫りになります。
求められる学歴の傾向としては、旧帝大、東京工業大学、慶應義塾大学、早稲田大学など、難関大学出身者の比率が高く、エントリーの段階から特別な扱いを受けることもあるようです。
ただし、名古屋大学や九州大学、神戸大学、千葉大学といった地方の国公立大学や、関関同立・MARCHレベルの理系学部からも一定数の採用実績があり、理系の専門性があれば挑戦の余地は十分にあります。
中途採用に関しても高いハードルがありますが、実務経験や技術的な専門性を有する人材であれば歓迎される傾向にあります。とくに、航空宇宙、エネルギー、インフラ関連などの分野でスキルを磨いた転職希望者にとっては、有力なキャリアパスの一つとなるでしょう。
もっとも、選考では高度な業務遂行能力や論理的思考、課題解決能力などが重視されるため、自己分析や企業研究を徹底する必要があります。
このように、三菱重工への就職は高い専門性と学歴を前提とした選抜が行われるため、準備不足では太刀打ちできません。一方で、自身の強みを明確にし、求められるスキルとの一致をアピールできれば、厳しい競争の中でも道は開けてきます。高待遇と引き換えに期待値も高いため、戦略的なアプローチが不可欠です。
参考資料:東洋経済オンライン
三菱重工のタービンの拠点はどこですか?

三菱重工業は、発電用タービンの分野において世界トップクラスの技術力を誇ります。その中心となる拠点は、兵庫県の「高砂製作所」と茨城県の「日立工場」です。両拠点はそれぞれの役割を持ちながら連携し、グローバルな需要に応え続けています。
高砂製作所(兵庫県)
- 1960年代初頭に神戸造船所から独立して設立されたタービン製造の母工場
- ガスタービン・蒸気タービンを中心に設計・製造・実証までを一体化
- 1,650℃級に対応する高効率ガスタービンの開発実績を持つ
- 水素やアンモニア燃料に対応した脱炭素型タービンの開発にも注力
- 経済産業省やNEDOの支援を受けた次世代エネルギー技術の拠点でもある
日立工場(茨城県)

- 1930年代に創設された歴史ある拠点
- 蒸気タービン、発電機、ガスタービンの設計から製造までを担当
- 高砂製作所と連携して、多様な製品ラインナップに対応
- 国内外の発電事業者に向けて技術提供と製品供給を実施
- 一貫した品質管理体制により信頼性の高い製品を生産
両工場の役割と意義
- 高砂製作所は設計から試験までを一括して行える研究開発型の製造拠点
- 日立工場は大量供給を担う量産型の生産拠点として機能
- それぞれが専門性を活かし、相互補完によって三菱重工のタービン事業を支えている
- 両工場の存在により、日本発の高性能タービンが世界市場で高い競争力を維持している
このように、高砂製作所と日立工場は、三菱重工の発電技術の中核として、それぞれの特長を活かしながら技術革新と信頼性の向上を追求しています。
【三菱重工】戦闘機工場の役割と全体像を総括
この記事のポイントをまとめます。
- 名古屋地域に戦闘機関連の工場が集約されている
- 大江工場は設計と部品製造を担当する拠点
- 小牧南工場はF-2やF-35Aの最終組立を担う中心工場
- 飛島工場はロケット部品や宇宙機器の組立を行う
- 小牧北工場はミサイルや誘導装置の製造を担当
- 大江工場には航空史料室が併設され一部見学可能
- 小牧南工場では戦闘機の整備や飛行試験も実施
- MRJの最終組立も小牧南工場で行われていた
- 小牧北工場ではパトリオットミサイルなどを製造
- 航空宇宙事業部は防衛・民間・宇宙の3領域をカバー
- ロケットの打ち上げは鹿児島の種子島宇宙センター
- 戦闘機技術は零戦からF-2、次期F-3まで進化している
- 日本の戦闘機開発は三菱重工が中心となっている
- 航空宇宙部門の年収は職種により大きく異なる
- 就職には高学歴と理系専門性が強く求められる
最後までお読みいただきありがとうございました。
おすすめ記事:
飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策
飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド
【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説
ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説