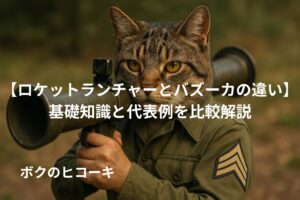三菱重工のロケット打ち上げ予定を探している方に向けて、H3を中心とした計画や基礎知識、現地の体制まで詳しく紹介。この記事では、H3ロケットの特徴や費用感、H2Aロケット打ち上げ成功の位置付けについて解説し、三菱重工ロケット打ち上げ失敗から得られた改善点も丁寧に整理してまいります。
さらに、ロケット工場の生産体制と三菱重工ロケット見学の可否、三菱重工ロケット関連の年収目安、ロケット事業撤退の真偽についても解説。
また、三菱重工のロケット打ち上げ予定2025年の全体像、H3ロケットの打ち上げ予定日に関する最新計画、打上げ当日の公式ライブ配信URLのご案内といった疑問にもお答えできるよう、実務に役立つ視点で総合的に説明してまいります。
- 最新の打ち上げ計画と機体ごとの位置付けが分かる
- 2025年の主要スケジュールを表で俯瞰できる
- 工場体制や見学可否など現地の実態が把握できる
- 配信の見方や当日のチェックポイントを掴める
三菱重工のロケット打ち上げ予定の全体像

- H3の特徴と位置付け
- H-IIAロケット打ち上げ成功の意味
- 三菱重工のロケット打ち上げ失敗の教訓
- ロケット工場と生産体制
- 三菱重工のロケット見学の可否
H3の特徴と位置付け
H3は、従来のH-IIA/Bシリーズを継承しながら、設計思想を根本から見直した次世代の国産基幹ロケットです。柔軟性、信頼性、コスト効率を重視してモジュラー化設計が採られており、多様なミッションや衛星重量に応じて構成を変更できる点が大きな強みです。
特に第1段には LE-9エンジン を採用し、2基または3基をクラスター化する方式を採っています。LE-9は、LE-7Aに比して約1.4倍の推力を実現しつつ、エキスパンダーブリードサイクルという比較的構成の簡素な方式を用いることで、部品点数や整備性、制御負荷を抑える設計が取られています(出典:JAXA「LE-9エンジン」)(rocket.jaxa.jp)
この構成により、SRB(固体ロケットブースタ)の有無、搭載エンジン数、フェアリングのサイズなどを組み換え可能なモジュール方式となり、用途に応じて最適化できる柔軟性を実現しています。たとえば補給機ミッションや静止遷移軌道投入に適した強化構成、あるいは小型衛星打ち上げ向けのシンプル構成など、見通しある運用が可能です。
また、2024年以降は実運用ミッションを複数成功させており、2025年には準天頂衛星や大型補給機ミッションも視野に入った段階。これら実績と計画を背景として、H3は日本の政府ミッションのみならず商業衛星打ち上げ市場への本格参入を目指しており、ロケット輸送の中核的存在としての地位確立を図っています。
参考スペック比較(代表的構成)
| 項目 | H-IIA(代表構成) | H3(代表:H3-24Wなど) |
|---|---|---|
| 全長 | 約53m | 最大約63m |
| 静止遷移軌道(GTO)投入能力 | 約4〜6トン | 6.5トン以上を目標 |
| 第1段エンジン | LE-7A × 1基 | LE-9 × 2基または3基 |
| SRB(追加固体ブースタ) | 必須構成 | 0本/2本/4本を選択可能 |
| 打ち上げコスト目標 | 基準設定 | 約半分を目指す設計目標 |
この比較から、H3は従来機を上回る運用の自由度と性能を併せ持つロケットとして、日本の宇宙打ち上げインフラを刷新する意図が明確です。
H-IIAロケット打ち上げ成功の意味

2025年6月29日、H-IIAロケット50号機が温室効果ガス・水循環観測技術衛星GOSAT-GWを搭載して種子島から打ち上げられ、成功を収めました。この最終号機の成功は、H-IIAシリーズにおよそ49回の成功実績を重ねたうえで有終の美を飾るものとなり、その技術力と信頼性を改めて証明しています。
この成果が持つ主な意味は以下の通りです。
- H-IIAシリーズの高い成功率を示す最終的な証左である。
- 後継ロケットH3へのスムーズな技術継承を後押しする役割を果たした。
- 推進技術、構造技術、打ち上げ運用ノウハウがH3開発に取り込まれていることの裏付けである。
また、搭載されたGOSAT-GWは温室効果ガスと水循環を同時観測する切り札的な衛星であり、地球環境モニタリングの能力を大きく強化します。この衛星を正確に軌道投入できたことが「高精度投入」への信頼を打ち立て、今後の衛星ミッション拡張にもつながっているのです。
H3が将来の打ち上げ主力となる中、H-IIA最終号の成功は技術の継続と信頼性の拡張の両面を支える重要な節目だったと言えます。
三菱重工のロケット打ち上げ失敗の教訓

H3試験機1号機(2023年3月)で、第2段のエンジンが着火せずミッションが中止された事例は、日本のロケット開発における痛切な教訓になりました。この不具合の背景には、電気系統(点火装置・推進系コントローラ)および配線設計上の不備などが複合的に作用した可能性が指摘されています。
この失敗を受けて、以下のような対策が講じられました:
- 点火装置(エキサイタ部分)の絶縁強化および回路見直し
- 推進系コントローラのソフトウェア・ハードウェア両面での耐性向上
- 配線経路や電磁ノイズ対策の再設計
- 非破壊検査・X線CT検査の標準化強化
- 試験系レビューと予備冗長系設計の徹底
これらの対策は、2号機以降の運用機体に横展開され、運用実績と併せて信頼性の改善が進みました。こうしたプロセスを通じて得られた「失敗からの知見」が、現在の打ち上げ運用の安定性を支える基盤となっています。
失敗から学んだ最も重要なポイントは、設計と検証過程のシンプル化、高品質保証プロセス、そして反復レビューの徹底にあるのです。これらを全機体に展開したことにより、現在のH3運用は改善傾向を示しつつあります。
ロケット工場と生産体制

H3ロケットの生産拠点として中核を担うのが、愛知県弥富市に位置する名古屋航空宇宙システム製作所 飛島工場です。この工場は、三菱重工業の航空宇宙部門の中でも最先端の設備を備え、H3のコア機体の製造・組立・検査・出荷までを一貫して行う体制を構築しています。
日本国内における数少ない大型ロケット製造施設として、極めて高い精度と信頼性が求められる工程を担当。
この工場では、自動鋲打ち機などの先進的な自動化設備が導入されており、外板やタンク部分の接合においてミクロン単位の精度を実現しています。こうした自動化は作業員の負担軽減に加え、品質の均一化、製造リードタイム短縮にも大きく寄与。
また、全ての主要部品や組立工程にはトレーサビリティ管理が徹底され、どの部材がどのタイミングで加工・検査されたかを追跡できる仕組みが整備されています。
環境面では、機体を扱うエリアは温度・湿度が一定に管理されたクリーンルーム相当の環境下に設置されており、航空機や宇宙機特有の極微細な異物混入や腐食を防ぐ工夫が施されています。
検査工程には非破壊検査(X線、超音波、渦電流など)が標準で取り入れられ、内部欠陥の有無を徹底的にチェックすることで信頼性向上を図っているのが特徴です。
生産能力の面では、現行の体制で年間5〜6機のH3コア機体を製造可能とされていますが、今後の需要増加に応じてライン増設や人員拡充を行い、より高い生産能力に引き上げることも視野に入れています。
これにより、政府・商業双方の打ち上げ需要に柔軟に対応できる体制が整うと見込まれています(出典:三菱重工公式サイト「名古屋航空宇宙システム製作所」)。
観点体制・特徴
| 観点 | 体制・特徴 |
|---|---|
| 主担当 | 名古屋航空宇宙システム製作所 飛島工場 |
| 主業務 | H3コア機体の組立・検査・出荷 |
| 品質 | クリーン環境と非破壊検査の併用 |
| 能力感 | 年5〜6機規模、増強余地あり |
このような高度な生産基盤と品質管理体制により、H3ロケットの安定した製造と将来の量産化のための基礎が確立されています。
三菱重工のロケット見学の可否

飛島工場は、日本の宇宙輸送を支える基幹インフラであり、極めて高い安全性と機密性が要求されるため、一般公開は行われていません。組立工程や試験装置は高度な機密技術を含むため、第三者が容易に立ち入ることはできない構造となっています。
ただし、教育機関や限られた専門団体などに対しては、事前調整のうえで特別プログラムが実施される場合があります。
一般の方がロケット製造の雰囲気を知る手段としては、公開施設やイベントの活用が現実的です。例えば、JAXAの筑波宇宙センターではロケットエンジンや人工衛星の展示があり、ガイドツアーによって開発・運用の現場を間近に感じることができます。
また、種子島宇宙センターや内之浦宇宙空間観測所では、打ち上げ関連施設の一部が見学コースとして整備されており、一般向けに予約制ツアーが実施されています。
さらに、三菱重工やJAXAは公式発表や広報動画を積極的に公開しており、公式YouTubeチャンネルや公式ウェブサイトを通じて、最新の開発状況や打ち上げの様子を視聴することが可能です。こうしたデジタルコンテンツを活用することで、現地に足を運ばずとも最新の宇宙開発動向を把握できます。
見学を希望する場合は、最新情報を随時確認するとともに、受け入れ条件や募集時期などの詳細をしっかり把握することが大切です。特に打ち上げシーズンや新型機の組立時期などは工場内の稼働が集中するため、受け入れが一層制限されることがあります。
安全・機密保護を優先する体制を理解したうえで、公開可能なイベントや施設を選んで体験することが推奨されます。
三菱重工のロケット打ち上げ予定の最新情報

- 三菱重工のロケット関連職種 年収の目安
- ロケット撤退の噂と公式見解
- H3ロケットの打ち上げ予定日は?
- 三菱重工のロケットの打ち上げ予定 2025年
- 打上げ当日の公式ライブ配信URLを教えて
- 【まとめ】三菱重工のロケット打ち上げ予定について
三菱重工のロケット関連職種 年収の目安
日本の宇宙産業を支える三菱重工のロケット関連職種は、設計開発から製造、品質管理、打ち上げ運用まで多岐にわたる構成です。それぞれの業務は高度な専門知識と責任を伴うため、年収も職種・経験・役職によって大きく幅があります。
一般的な技術職ではおおむね650万〜900万円程度が目安とされ、特にエンジン開発やシステム統合など高度な専門性が求められるポジションではさらに高水準になる傾向です。管理職やプロジェクトマネージャーなどの役割に就く場合は、1,000万円を超えるケースも存在しています。
期間契約社員や派遣社員として従事する場合は、正社員と異なる給与体系が適用され、時給制や日給制など契約内容によって実収入が変わる点も特徴です。加えて、三菱重工は総合重工メーカーとして、通勤手当、住宅補助、家族手当、賞与(年2回)、確定拠出年金、社員持株会などの福利厚生制度を充実させています。
これらが、長期的なキャリア形成や生活の安定を後押ししています。
職種別に見ると、生産管理やプロジェクト推進などの部門は比較的高い給与水準で、製造・組立に携わる職種は経験や技能に応じて段階的に昇給する仕組みが一般的です。特に宇宙関連分野は、技術力の蓄積とスキル認定が年収に直結しやすいため、資格取得や専門研修の受講がキャリアアップに有効です(出典:賃金構造基本統計調査 – 厚生労働省)。
ロケット撤退の噂と公式見解

2025年9月時点において、三菱重工がロケット事業から撤退するとの公式発表は一切確認されていません。同社はH-IIA最終号機の運用完遂後も、後継のH3に経営資源を集中させ、より低コストで高頻度な打ち上げを実現することで国際競争力を高める方針を示しています。これは撤退ではなく、むしろ事業拡充に近い方向性です。
宇宙輸送市場はSpaceXや欧州のアリアン6など国際競合が激化していますが、三菱重工は国内最大の宇宙輸送事業者として、官民双方の打ち上げ需要に応える責務を担っています。そのため、製造工程の自動化やコスト構造の改善、品質保証プロセスの強化など、運用最適化と技術革新を並行して進めています。
また、H-IIAで培われた高度な信頼性と打ち上げ実績は、H3開発への技術移管により維持・強化されています。これにより、国内外の顧客からの信頼を引き続き確保し、衛星打ち上げ市場の多様なニーズに応える姿勢を明確に打ち出しています。
過去の大型プロジェクトで得た知見が宇宙輸送分野でも活かされており、撤退ではなく持続的な成長を目指していることが分かるのです。
H3ロケットの打ち上げ予定日は?

H3ロケットの直近の基幹ミッションとして注目されているのが、7号機による新型宇宙ステーション補給機HTV-X1の打ち上げです。現在の計画では、2025年10月21日午前10時58分頃(日本時間)に種子島宇宙センターから打ち上げが予定されています。
予備期間は10月22日から11月30日まで設定されており、天候や国際宇宙ステーション(ISS)の運用スケジュールに合わせて日程調整が行われる可能性があります。
この7号機はH3-24Wという重輸送構成を採用し、第1段にLE-9エンジンを2基搭載し、固体ロケットブースター(SRB-3)を4本追加、さらにワイドフェアリングを装備しています。これにより、大型補給機HTV-X1を軌道に投入できる性能を確保。
静止トランスファ軌道(GTO)級の能力とISS補給ミッションの両立を狙い、設計段階から柔軟な構成が導入されています。
このミッションは、H3が政府ミッションおよび国際協力ミッションにおける信頼性を実証する重要なステップとされています。複数回の打ち上げ成功を重ねることで、商業衛星打ち上げ市場への本格参入、さらには低コストで安定した宇宙輸送サービスの確立が期待されているのです。
H3の計画進行とあわせて、最新情報をJAXAや三菱重工の公式サイトで確認することが推奨されます。
三菱重工のロケットの打ち上げ予定 2025年

2025年の三菱重工ロケット事業は、複数の重要な節目を迎える年です。年初には準天頂衛星みちびき6号機をH3-22S(フライト5号機)が打ち上げ、機体性能の安定と運用体制の確立に寄与しました。
夏にはH-IIAの最終号機が温室効果ガス・水循環観測衛星GOSAT-GW(いぶきGW)を投入し、長年続いたシリーズが円満に幕を閉じました。
そして秋には、新型宇宙ステーション補給機HTV-X1を搭載するH3-24W(フライト7号機)による重ミッションが予定されており、政府・国際協力ミッション双方におけるH3の実力を証明する重要な試金石とみなされています。
こうした複数のミッションを通じて、H3は従来機の技術を発展的に継承しつつ、より低コストかつ高頻度の運用を目指しています。
また、これらのミッションは、衛星測位(みちびき)、地球環境観測(GOSAT-GW)、国際宇宙ステーション補給(HTV-X1)など、日本の宇宙インフラを支える多様な分野に直結しているため、国内外から大きな注目を集めているのです(出典:JAXA「H3ロケット」https://www.jaxa.jp/projects/rockets/h3/)。
以下の表に2025年の主要打ち上げ計画を整理します。
| 打上げ日(日本時間) | 機体 | 搭載物 | 状況 | 射場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月2日 17:30 | H3-22S(F5) | 準天頂衛星みちびき6号機 | 成功 | 種子島 |
| 2025年6月29日 1:33 | H-IIA 50号機 | GOSAT-GW(いぶきGW) | 成功 | 種子島 |
| 2025年10月21日 10:58頃 | H3-24W(F7) | HTV-X1(新型補給機) | 予定 | 種子島 |
※時刻は計画や当日の運用により調整される場合があります
これらの打ち上げは、H3が国際的な打ち上げサービス市場で地位を確立するための重要なステップであり、ミッションごとの成功がそのまま信頼性の裏付けとなります。
打上げ当日の公式ライブ配信URLを教えて

打ち上げ当日は、JAXA公式のYouTubeチャンネルでライブ視聴が行われるのが通例です。番組は通常、打ち上げ予定時刻の約1時間前から開始され、機体の整備状況、当日の天候、カウントダウンの進行、そして打ち上げ直前の最終チェックなど、専門家による詳細な解説とともにリアルタイムで配信されます。
YouTube内で「JAXA ライブ」などのキーワードで検索すると、該当する配信ページにアクセスでき、視聴予約を行うことも可能です。
また、三菱重工の打ち上げサービス関連の公式発表や、種子島宇宙センターの公式案内ページでも、当日の運用情報が逐次更新される仕組みです。これらを併用することで、視聴者はより正確な進行状況を把握できます。
視聴前には開始時刻と配信タイトルを必ず確認し、直前のスケジュール変更や打ち上げウインドウの調整に備えることが重要です。
さらに、打ち上げシーズンには関連するオンラインイベントや解説セミナーが併催される場合もあり、一般視聴者が宇宙開発への理解を深める機会となっています。こうした情報を活用することで、現地に行かずとも、迫力ある打ち上げの瞬間とその背景にある技術・運用をリアルタイムで体感することが可能です。
【まとめ】三菱重工のロケット打ち上げ予定について
この記事のポイントをまとめます。
- H3はモジュール設計とLE-9採用で柔軟性と経済性を両立
- H2A最終号機は2025年6月29日にGOSAT-GWを投入
- H3の7号機は2025年10月21日午前10時58分頃に計画
- H3-24W構成でHTV-X1を打ち上げる大型補給機ミッション
- 2025年2月にはH3がみちびき6号機の投入に成功
- H3の改善点は点火装置や電気系統の強化と検査拡充
- 三菱重工の撤退情報は確認されておらず継続路線
- 主生産拠点は名古屋の飛島工場でコア機体を組立
- 年間5〜6機規模の製造能力で増強余地が見込まれる
- 見学は原則非公開で教育向け特別プログラムが中心
- 三菱重工のロケット関連職種の年収は職種で差があり幅を持つ
- H2Aロケット打ち上げ成功はH3時代への確かな橋渡し
- ライブ視聴はJAXA公式のYouTube配信が基本
- 予定時刻は天候や運用都合で変更の可能性に留意
- 三菱重工のロケット打ち上げ予定はH3中心に推移
最後までお読みいただきありがとうございました。