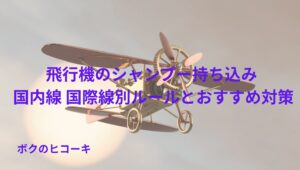飛行機を自由に操るパイロットという職業に憧れを抱き、「航空機の操縦士になるには」と検索する人は少なくありません。しかし、実際にその夢を叶えるためには、いくつものハードルを乗り越える必要があります。例えば、パイロットになるには学力や費用といった現実的な課題があり、特に理系科目や英語力が重要視されます。
また、進路選びにおいては「パイロットになるためには大学で何を学ぶべきか」といった視点も欠かせません。
さらに、パイロットになるには何年かかる?といった疑問を持つ人も多く、ルートによって必要な期間や訓練内容は大きく異なります。加えて、パイロットになれる確率は高くはなく、自社養成など狭き門を突破するためには入念な準備が求められます。
パイロットになる条件や、航空身体検査などの健康基準をクリアしなければならない点も見落とせません。
資格面では、事業用操縦士の取得を目指すことがプロへの第一歩となりますが、航空機操縦士としての難易度は高く、継続的な学習と訓練が不可欠です。それでも、努力が実を結べば、航空機操縦士としての年収は非常に高く、仕事内容も責任あるやりがいの大きいものとなります。
本記事では、航空機の操縦士になるための進路、必要な資格、かかる費用と時間、そしてその後の働き方や収入までをわかりやすく解説。将来パイロットを目指すあなたにとって、最初の確かな一歩となる情報をお届けします。
- 航空機の操縦士になるための具体的な進路や選択肢
- 必要な学力や訓練費用の目安と違い
- 資格取得までの流れと年数、条件
- 就職後の仕事内容や年収の実態
航空機の操縦士になるにはどんな進路がある?

- パイロットになるには 学力や費用はどのくらい必要か?
- パイロットになるためには?選ぶべき大学
- 事業用操縦士になるにはどうすればいい?
- 航空機操縦士の年収はどのくらい?
- パイロットになれる確率は?合格率の実情
パイロットになるには 学力や費用はどのくらい必要か?
パイロットを目指すうえで、学力と費用は避けて通れない大きなポイントです。どちらも一定以上の準備が必要となるため、早めの対策が重要になります。
まず学力についてですが、パイロットになるには高度な専門知識と論理的思考力が求められます。特に必要とされるのが、数学、物理、英語の3教科です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要な学力 | 高度な専門知識と論理的思考力が必要 |
| 重視される教科 | 数学、物理、英語 |
| 試験内容(航空大学校) | 英語・総合(数学・理科・一般常識)数学:微積分・三角関数など物理:気象・力学・電磁気など |
| 英語の要求水準 | 航空英語に対応できる実用レベル(文法力だけでは不十分) |
航空大学校を受験する場合、英語と総合(数学・理科・一般常識)に関する筆記試験が実施されます。数学では微積分や三角関数、物理では気象や力学、電磁気など、高校〜大学基礎レベルの知識が問われる内容です。また、英語力は航空英語に対応できる水準が求められるため、単なる文法知識では不十分です。
続いて費用面ですが、進路によって大きな差があります。
| 進路 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 私立大学の養成課程 | 約2,200万円〜3,200万円 | 訓練費・留学費含む。費用が高額。 |
| 航空大学校 | 約650万〜1,000万円 | 学費は抑えめだが、2年以上の大学在籍が事前に必要。 |
| 航空会社の自社養成制度 | ほぼ無料(給与をもらいながら訓練) | 金銭的負担は少ないが、倍率は100倍以上の年もある超難関。 |
私立大学のパイロット養成課程では、訓練費や留学費を含めて総額2,200万円〜3,200万円程度が一般的です。一方、航空大学校であれば学費は比較的抑えられ、全体で650万〜1,000万円程度が目安になります。ただし、入学前に2年間以上の大学在籍が必要なため、その分の費用も考慮する必要があります。
さらに、航空会社の自社養成制度を活用すれば、費用はほとんどかからず、給与をもらいながら訓練を受けることが可能です。しかし、倍率は100倍を超える年もある狭き門です。
このように、パイロットになるには理系科目の学力と高い英語力、そして進路によっては数千万円に及ぶ費用が必要です。奨学金や教育ローンの利用も含め、進学前にしっかりと計画を立てることが求められます。
パイロットになるためには?選ぶべき大学

パイロットを本格的に目指す際、どの大学に進学するかはその後のキャリアに大きな影響を与えます。現在の日本では、パイロット養成に特化した大学も増えており、それぞれの特徴を理解して進路を選ぶことが大切です。
| 進路 | 主な大学・機関名 | 特徴 | 学費目安 | 注意点・条件 |
|---|---|---|---|---|
| 私立大学のパイロット養成課程 | 東海大学、桜美林大学、法政大学、崇城大学など | ・操縦訓練+航空工学・気象・航空英語などを体系的に学習・海外フライトスクールと提携する大学も多数 | 約2,000万円以上(4年間) | 学費が非常に高額。奨学金や経済的支援制度の有無を要確認 |
| 航空会社の自社養成制度 | ― | ・一般大学在学中に試験を受験・費用がほとんどかからない(訓練中に給与が支給される) | 実質ほぼ無料 | 非常に高倍率(100倍以上も)学部学科問わず高い学力が必要 |
| 航空大学校 | 航空大学校 | ・訓練費用は比較的安価・理論と実技を本格的に学べる国家機関・大学進学後の進路として選ばれることも多い | 約650万〜1,000万円程度 | 入学条件:大学に2年以上在学し62単位以上取得別途大学費用が必要 |
最も一般的な選択肢は、パイロット養成コースを持つ私立大学への進学でしょう。代表的な大学として、東海大学、桜美林大学、法政大学、崇城大学などが挙げられます。これらの大学では、航空機の操縦訓練のみならず、航空工学、気象、航空英語などパイロットに必要な幅広い知識を体系的に学べるのが特徴。
さらに、多くの大学では海外のフライトスクールと提携し、国際的な訓練環境を提供しているのも魅力のひとつです。
ただし、学費は高額で、4年間で2,000万円を超えるケースも珍しくありません。そのため、経済的な支援制度や奨学金の有無も進学先選びの重要な要素となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 進学前の準備 | 学力(特に数学・物理・英語)をしっかり身につけておくことが重要 |
| 選択の基準 | ・学費の負担可能性・将来のキャリア設計・訓練内容と環境(海外提携含む)・支援制度の有無など |
| その他の留意点 | 自社養成と航空大学校を目指す場合も、一般大学での学業がしっかりしていることが前提 |
一方で、一般の4年制大学に進学後、航空会社の自社養成試験を受けるというルートも。自社養成は費用面で大きなメリットがあるものの、非常に高い競争倍率を突破する必要があります。そのため、学部学科を問わず、大学ではしっかりと学力を身につけておくことが欠かせません。
また、航空大学校へ進むためには、4年制大学に2年以上在学し62単位以上を取得することが条件です。このルートも選択肢の一つとして念頭に置いておくべきです。
このように、パイロットになるためには、目的に応じた大学選びが欠かせません。操縦訓練を最優先したいのか、学費を抑えたいのか、それとも航空会社に就職しやすい環境を選びたいのか、明確な目標を持って進路を検討する必要があります。
事業用操縦士になるにはどうすればいい?

事業用操縦士とは、航空機を使って報酬を得る仕事に従事するための資格で、エアラインパイロットやドクターヘリ、遊覧飛行、空撮などで活躍する際に必要です。これはプロの操縦士としての第一歩であり、取得までには明確なルートと条件があります。
基本的には、自家用操縦士(PPL)を取得後、飛行時間を積みながら事業用操縦士(CPL)の取得を目指すことになります。必要な飛行時間は最低200時間以上で、うち100時間以上は機長としての飛行経験が必須です。また、夜間飛行や計器飛行、長距離の野外飛行など、特定の訓練経験も規定に含まれています。
年齢制限は18歳以上、高卒程度の学力が求められ、航空身体検査(第2種または第1種)や航空無線通信士などの関連資格も併せて取得が義務付けられています。
資格取得のための訓練は、航空大学校、パイロット養成課程のある大学・専門学校、または民間のフライトスクールで受講可能です。これらの訓練機関では、必要な知識や操縦技術を段階的に学べるカリキュラムが準備されています。
中には、海外での飛行訓練を取り入れている施設もあり、国際的な技術水準を目指すこともできるのが魅力のひとつです。
一方で、取得までの費用は非常に高く、数百万円から1,000万円を超える場合もあるため、奨学金制度の活用や進路の慎重な検討が欠かせません。また、訓練の難易度も高く、学科試験だけでなく実技試験にも厳しい基準が設けられているため、継続的な学習と実践が必要です。
事業用操縦士の資格を取得すれば、航空会社の副操縦士として採用される可能性も広がります。最終的に定期運送用操縦士(ATPL)を目指すためにも、まずはこの資格取得を確実にクリアしておくことが重要です。
参考資料:「パイロットになるには」国土交通省
航空機操縦士の年収はどのくらい?

航空機操縦士の年収は、国内の全職種の中でも非常に高い水準にあります。ただし、所属する航空会社の規模や経験年数、操縦する機種によって大きな差が生じるのが特徴です。
まず、厚生労働省の調査によると、航空機操縦士の平均年収は約1,600万円前後となっています。これは日本の平均年収(約450万円前後)の3倍以上にあたり、職業全体の中でもトップクラスの水準です。特に大手航空会社に勤務するパイロットであれば、さらに高い年収が期待できるでしょう。
例えば、日本航空(JAL)や全日本空輸(ANA)では、副操縦士であっても年収1,300万〜1,500万円程度が相場となっており、機長クラスになると2,500万円〜3,000万円に達するケースもあります。このように、ポジションが上がるにつれて報酬も大きく上昇する傾向です。
一方、地方航空会社や小型機を扱う事業用操縦士の場合は、年収が800万〜1,000万円台に留まることも。さらに、ヘリコプターやドクターヘリのパイロット、公務員として勤務する操縦士の場合は、給与体系が異なり、年収が700万円台からスタートすることもあります。
注意点として、パイロットの年収は「高収入=楽な仕事」ではないということです。長時間のフライト、時差による体調管理、定期的な技能審査や身体検査への合格義務など、常に高い責任と緊張感の中で業務を行う必要があります。また、航空業界の景気や国際情勢によって雇用・報酬が影響を受ける点にも留意すべきでしょう。
このように見てみると、航空機操縦士は非常に高収入な職業である一方で、それに見合った厳しさと継続的な努力が求められる職種でもあります。
パイロットになれる確率は?合格率の実情

パイロットという職業は多くの人にとって憧れの対象ですが、実際にその夢を実現できる人はごく一部です。進路ごとに見ても、その合格率は決して高くありません。
まず、最も費用負担が少ない「航空会社の自社養成パイロット」は、毎年7,000人以上が応募するといわれており、採用されるのは50人前後に限られます。つまり、合格倍率は100倍以上、合格率は1%未満という非常に狭き門です。このルートは学歴・英語力・適性・体力・人格すべてが高い水準で求められるため、十分な準備と訓練が必要です。
次に「航空大学校」への進学を目指す場合ですが、こちらも毎年の募集枠が約100名程度で、受験者数は1,000人前後にのぼります。倍率はおおよそ10倍前後であり、合格率は10%程度です。学力だけでなく、身体検査や操縦適性検査などの通過も必要になるため、対策の幅が広いのが特徴です。
私立大学のパイロット養成コースに関しては、入試倍率が比較的緩やかで、2〜3倍程度の学校もあります。このため入学自体はしやすいですが、卒業後に航空会社への就職が保証されているわけではありません。適性検査、身体検査、就職試験を通じて初めてパイロットとしての道が開かれるため、大学入学後も油断できないのが実情です。
また、民間フライトスクールから事業用操縦士資格を取得するルートもありますが、この場合も航空会社に採用されるには、相応の飛行時間・英語力・健康状態が求められます。自己負担も大きく、就職までの保証がない点には注意が必要です。
こうした点を踏まえると、「パイロットになりたい」と志す人のうち、最終的に職業パイロットとして活躍できる人は、全体の1〜2%ほどに限られます。これは医師や弁護士など、他の難関職と比べてもかなり低い数値です。
ただし、適切な準備と情報収集、訓練を継続すれば、夢の実現も不可能ではありません。進路を早い段階から計画し、現実的な目標を見据えることが成功への鍵となります。
航空機の操縦士になるには何を準備すべきか

- パイロットになるには何年かかる?
- パイロットになる条件と必要な資格とは?
- 航空機操縦士 難易度はどのくらい?
- 航空機操縦士 仕事内容と働き方の実態
- 航空無線資格や英語力は必要なのか?
- 航空身体検査や健康条件はどれほど厳しい?
パイロットになるには何年かかる?
パイロットとして航空会社で乗務するまでにかかる年数は、進むルートによって大きく異なります。一般的には早くても3年、長い場合は10年以上かかるケースもあります。
まず、最短ルートのひとつが「自社養成パイロット制度」です。この制度では、大学卒業後に航空会社へ入社し、会社の訓練課程を経て副操縦士に任命されます。
入社後、1〜2年の地上業務期間を含み、約2〜3年で副操縦士として乗務を開始することが可能です。このルートが最も早くパイロットになれる方法ですが、採用されるまでの競争が非常に激しく、現実には難関といえます。
一方で、航空大学校や私立大学のパイロット養成課程を経由する場合、高校卒業からパイロットになるまでには一般的に5〜7年ほどかかります。
例えば、航空大学校の場合は入学前に2年以上の大学在籍が必要で、その後2年間の訓練期間が。さらに、航空会社に就職してからも追加の社内訓練を受け、初めて副操縦士としてフライトに就くことができるのです。
また、自費での訓練や専門学校を利用して事業用操縦士の資格を取得するルートでは、資格取得後すぐにパイロットの職に就けるとは限らず、求人状況や経験が影響します。そのため、安定してパイロットとして働けるまでには10年以上の時間がかかることも珍しくありません。
さらに、機長になるには副操縦士としての経験が不可欠であり、早くても乗務開始から10年程度の実績が求められます。つまり、機長として一人前になるには、トータルで15年以上を見込んでおく必要があるのです。
このように、パイロットになるまでの道のりは長く、訓練・実務経験・社内評価など多くの要素が関わります。早期からの情報収集と継続的な努力が成功には不可欠です。
パイロットになる条件と必要な資格とは?

パイロットを目指すには、明確に定められた条件と複数の国家資格が必要です。適性や体力、知識など幅広い能力が求められるため、あらかじめ基準を理解しておくことが重要です。
まず必要な資格は、「航空従事者技能証明」と呼ばれる国のライセンスです。このライセンスは3段階に分かれており、最初に取得するのが「自家用操縦士(PPL)」、次に「事業用操縦士(CPL)」、そして最上位にあたるのが「定期運送用操縦士(ATPL)」です。パイロットになるには、基本的にこの順序で段階的に資格を取得していきます。
加えて、航空会社で働くには「計器飛行証明」や「航空無線通信士」の資格も必要です。これらは、安全運航に関わる重要な技術・知識であり、どれも専門的な試験に合格しなければなりません。
身体面では、「航空身体検査証明」を取得することが必須です。これは視力・聴力・心電図・血液検査など、健康状態を厳しくチェックする検査です。多くの航空会社では、身長158cm以上や矯正視力0.7〜1.0以上といった具体的な基準を設けている場合もあります。
学歴条件についても確認が必要です。例えば航空大学校では、25歳未満かつ大学に2年以上在籍し62単位以上を修得していることが受験資格となっています。また、航空会社の自社養成パイロット制度では、基本的に4年制大学卒業(または見込み)が応募条件となっているのが一般的です。
このように、パイロットになるには身体的な基準、学歴条件、そして複数の国家資格が必要となり、どれか一つが欠けても職業パイロットにはなれません。目指すのであれば早い段階でこれらの条件を理解し、着実にクリアしていく必要があります。
航空機操縦士 難易度はどのくらい?

航空機操縦士の資格取得は、趣味として飛行機を操縦したい人と、職業パイロットを目指す人とで大きく難易度が異なります。基本的には、自家用操縦士よりも事業用操縦士、そして定期運送用操縦士へと進むほどに、取得の難しさが増していくのです。
まず自家用操縦士(PPL)の資格は、比較的取得しやすい部類に入ります。学科試験の範囲も基礎的であり、実技訓練も含めて十分な時間と資金を確保できれば、多くの人が合格可能です。実際の合格率は90%以上とされており、自動車免許と同様に、努力すれば到達できるレベルです。
一方で、事業用操縦士(CPL)の難易度はぐっと上がります。飛行時間200時間以上や、複雑な学科内容(航空法規、航空力学、空中航法、気象など)に加え、実地試験でも高度な操作が求められるのです。合格率は約50%前後とされており、国家資格の中でも難関に位置づけられます。
さらに、定期運送用操縦士(ATPL)は、職業パイロットの中でも機長として定期便を運航するための最高峰の資格です。必要な飛行時間は1,500時間以上とされ、知識・技術ともに最上級の内容が求められます。取得者も限られており、試験内容は非公開の部分も多く、一般的に「極めて難しい資格」とされています。
加えて、資格取得後も定期的な技能審査、身体検査、航空会社での社内訓練を継続する必要があり、知識・技術の更新を怠ることは許されません。つまり、航空機操縦士という職業は、資格取得後も不断の努力が求められる仕事です。
このように、航空機操縦士の難易度は段階ごとに大きく異なり、プロフェッショナルを目指すほどに高くなります。目標とするレベルに応じた学習と準備が不可欠です。
航空機操縦士 仕事内容と働き方の実態

航空機操縦士の仕事は、「飛行機を操縦すること」だけではありません。フライトの準備から運航後の報告まで、多くの業務が含まれているのが実情。勤務形態も特殊で、一般的な会社員とは異なる生活リズムが求められます。
まず出発前には、天候や空域状況、フライトプランの確認を実施。この段階で、気象予測や目的地周辺の空港情報を把握し、安全な飛行経路を設計。続いて、整備士やディスパッチャー(運航管理者)と打ち合わせを行い、航空機の状態や積載物の確認、燃料の搭載量などを詳細にチェック。これらはすべて「フライト前業務」にあたります。
搭乗後は、機長と副操縦士の2名で飛行機を運航。機内では、操縦だけでなく、計器の監視、航空管制との交信、気象の変化への対応、緊急時の判断など、瞬時の判断が求められる場面が続きます。加えて、乗客の安全と快適性を保つために、客室乗務員との連携も欠かせない要素のひとつです。
フライト終了後には、「ポストフライト業務」が待っています。航空機の状態を整備担当者に報告し、飛行日誌の記入、必要に応じた報告書の作成などを実施。すべてが終了するまでがパイロットの仕事といえるでしょう。
働き方については、勤務時間や休日のスタイルが一般的な職業とは大きく異なります。国内線の場合は1日に2〜3便を担当することもありますが、国際線では1フライトごとに数日を要し、現地に数泊するケースも。
また、夜間や早朝のフライトも多いため、体調管理が極めて重要です。勤務はシフト制で、月に10日程度の休日があることが一般的となっています。
このように、航空機操縦士は単なる「飛行のプロ」ではなく、安全運航を担う責任ある専門職です。多くの人と協力しながら、緊張感の中で日々業務を遂行する仕事であると言えるでしょう。
航空無線資格や英語力は必要なのか?
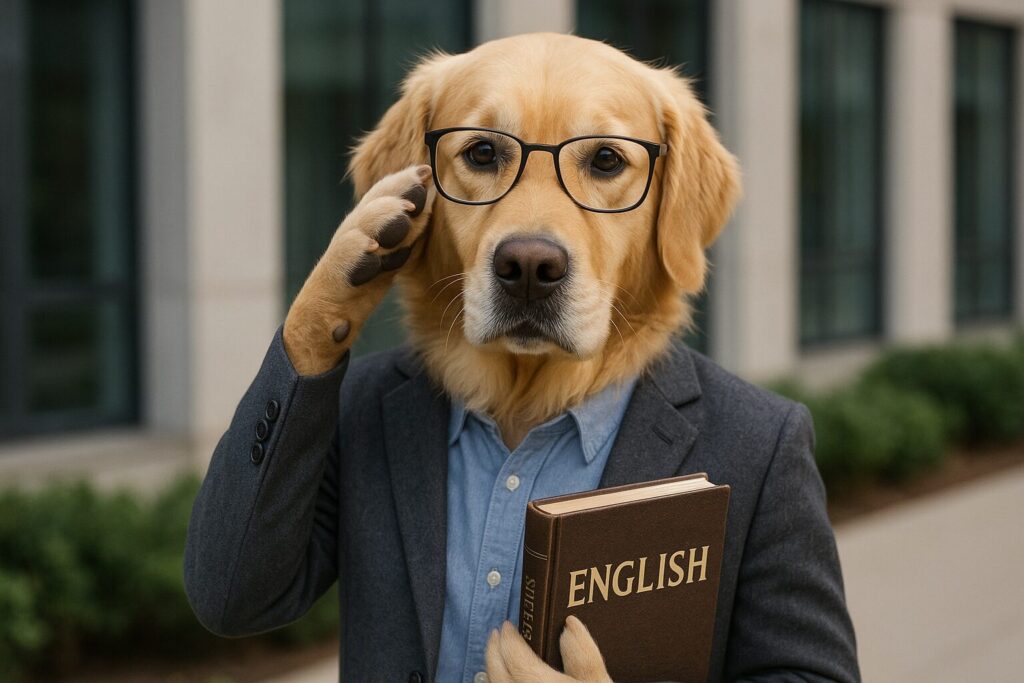
パイロットを目指すうえで、航空無線資格と英語力はどちらも欠かせないスキルです。操縦技術だけでなく、情報のやりとりが正確にできる能力が、安全な運航には不可欠とされています。
まず、航空無線に関してですが、航空機を操縦するには「航空無線通信士」または「航空特殊無線技士」といった無線従事者の資格が必要です。
これは航空機と地上の航空管制官との間で通信を行うために義務付けられているもので、資格を持たずに操縦することは法律上認められていません。たとえば、フライト中に進路の変更指示や離着陸許可などを受けるには、無線を使った正確な交信が必須です。
次に英語力についてです。国内線では日本語での通信が基本ですが、国際線での交信はすべて英語です。さらに、近年では国内線でも外国の航空機や国際線との交錯がある空域で英語によるやりとりが発生する場面が増えています。そのため、英語での基本的な航空用語や交信フレーズを理解・運用できる力が求められるのです。
具体的には、ICAO(国際民間航空機関)の基準に基づく「航空英語能力証明」が必要とされる場合も。これは音声による英語での意思疎通能力を測るテストで、航空会社によっては採用試験や昇進条件に含まれることもあります。
なお、英語力といっても日常会話の流暢さだけでなく、「簡潔で正確に伝える能力」が重要視されます。特に緊急時や天候の急変といった場面では、ミスのない交信が乗客の安全を左右するためです。
このように、パイロットとして働くためには、航空無線の法的資格と実務で使える英語力の両方を備えることが必要です。早い段階から英語に触れ、無線交信の形式に慣れておくことが、今後の大きな助けとなるでしょう。
航空身体検査や健康条件はどれほど厳しい?

航空身体検査は、パイロットとしての資格を維持するうえで非常に重要な要素のひとつです。この検査は年齢や職務内容に応じて定期的に実施され、一定の基準を満たさないと、たとえ優れた操縦技術を持っていても、飛行業務に就くことができません。
まず、航空従事者には「第1種航空身体検査証明」が必要です。これはパイロット、特に定期運送用操縦士や事業用操縦士として働く者に課せられるもので、検査項目は、視力、聴力、血圧、心電図、呼吸機能、肝機能、尿検査、血液検査、そして精神的健康状態までが含まれます。
視力に関しては、裸眼の基準ではなく、矯正視力で0.7~1.0以上を維持していれば問題ない場合が多いですが、航空会社や進路によってはより高い基準を設定していることも。また、色覚異常に関しては業務内容に影響を与えるため、詳細な検査で判断されます。
年齢によっても検査の頻度は変わります。例えば40歳未満では1年に1回、40歳以上になると半年に1回の検査が義務付けられています。このような制度は、加齢による身体能力の変化を早期に把握し、リスクを最小限に抑えるためのものです。(参考資料:「航空身体検査の内容」航空医学研究センター )
精神的な健康も見逃せない要素です。ストレス耐性や集中力、判断力は、航空機の安全運航に直結する能力であり、うつ病やパニック障害などの診断歴がある場合には、乗務の許可が下りないことも。
こうした厳格な健康管理の背景には、万が一の際の判断ミスを防ぎ、多くの命を守るという使命があります。健康であることは、パイロットとしての基本条件なのです。
そのため、パイロットを目指す段階から、日頃の健康管理や生活習慣の見直しが必要です。無理な食生活、過度な飲酒、睡眠不足などは避け、安定した身体状態を保つことが、資格維持の鍵となります。
航空機の操縦士になるにはどんな準備や進路が必要か
この記事のポイントをまとめます。
- 数学・物理・英語の学力が必須で高校〜大学基礎レベルが求められる
- 航空大学校や私立大学、民間フライトスクールなど進路の選択肢がある
- 私立大学は2,000万円以上かかることもあり、費用面の計画が重要
- 航空会社の自社養成制度を活用すれば費用負担は少ないが倍率が非常に高い
- 自家用→事業用→定期運送用と段階的に操縦資格を取得していく
- 航空大学校には大学在籍2年以上と62単位以上の取得が条件
- 航空無線通信士などの無線資格は法的に必須である
- 英語力は国際線での交信や採用試験で重視される
- 航空身体検査は視力・聴力・精神面など厳格な基準が設けられている
- 副操縦士になるまでには最低3年、長ければ10年以上かかることもある
- 年収は航空会社や経験により差があり、1,600万円以上のケースもある
- 職業パイロットになれる確率は1〜2%と非常に低い
- 自家用操縦士の合格率は高いが、事業用以上は難関国家資格となる
- フライト以外にも準備・点検・報告など幅広い業務が含まれる
- 就職後も訓練・審査・健康維持など継続的な努力が求められる
最後までお読みいただきありがとうございました。
おすすめ記事:
セスナ機の免許取得費用はどこが安い?取得方法と節約ポイントを解説
【37年後に着陸した飛行機】実話の真相とタイムスリップ説の真偽
飛行機にヘアスプレー/ANAの持ち込み可否と預け荷物のルール解説
【空を飛ぶ夢】スピリチュアル的に見る解放感や不安のメッセージとは?
飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策
プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例