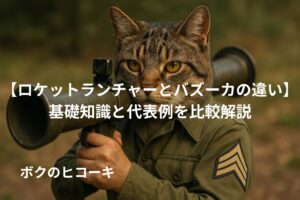ロケットリーグのランク分布を知りたい方に向けて、ランク分布の最新傾向やランク帯の割合、各ランクの一覧、部門の考え方、レートの仕組み、そして人数の目安まで一気に整理します。
多くの人がランクUPを難しいと感じる理由や、チャンピオン帯で必要とされる力にも触れ、「ロケットリーグのプレイヤー人口は?」といった全体像の疑問や、「ロケットリーグのレベルはどうやって確認する?」という実務的な疑問にも答えます。
検索の手間を省き、要点だけをわかりやすく把握できる構成にまとめました。
- シーズン16基準のランク分布とランク帯の割合を理解できる
- 主要モード別の人数傾向と自分の位置づけを把握できる
- ランクが難しい理由とチャンピオン帯で必要な要素を学べる
- レベルや成績の確認手順と実用ツールを把握できる
【ロケット リーグ】ランク分布の全体像

- ランク一覧を簡潔に確認
- ランク帯の割合/目安と傾向
- ランク分布と最新のデータ指標
- 部門ごとの仕組みと意味
- レートとランクの関係
ランク一覧を簡潔に確認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ランク段階 | プレイヤーの技術水準を段階的に示す指標。全体で8段階のランク構造を採用 |
| 各段階(一覧) | ブロンズ シルバー ゴールド プラチナ ダイアモンド チャンピオン グランドチャンピオン スパーソニックレジェンド(SSL) |
| 最高ランク | スパーソニックレジェンド(SSL)。世界全体で上位約0.03%前後のみが到達する希少帯 |
| ディビジョン構成 | 各ランクはI〜IIIのディビジョンに細分化(例:ゴールドI〜III)。細かな昇降で実力を精密に反映 |
| 昇格・降格の考え方 | 勝敗に応じて内部レート(MMR)が変動。一定基準を超えると昇格、下回ると降格し、急激な変動を抑制 |
| シーズンごとのMMR調整 | 新シーズン開始時にランクを一時リセット。再配置戦(プレースメント)で適正ランクを再決定し、平均MMRも変動 |
| 分布の中心 | ゴールド〜ダイアモンド帯にプレイヤーが最も多く集まり、中堅層として分布の中心を形成 |
| 中堅帯で求められる要素 | 基本操作の安定性と試合中の判断力に加え、チーム連携やローテーションの意識が昇格の鍵 |
| 活用ポイント | ディビジョン推移で短期の上達を可視化。シーズン開始直後はMMR変動が大きいため数試合の傾向で評価 |
| 補足 | 同じプラチナIIIでもシーズンにより難易度が変動。分布とMMR調整を前提に相対位置で実力を把握 |
ロケットリーグのランクシステムは、プレイヤーの技術水準を段階的に示す明確な指標として機能しています。全体はブロンズから始まり、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイアモンド、チャンピオン、グランドチャンピオン、そしてスパーソニックレジェンド(SSL)までの8段階構成。
なかでもスパーソニックレジェンドは最上位ランクで、世界全体のプレイヤーのうちおよそ上位0.03%前後しか到達できない極めて限られた実力層です。
さらに各ランクは、IからIIIまでのディビジョン(例:ゴールドI〜ゴールドIII)に細分化され、昇格や降格の仕組みを通じてプレイヤーの実力をより精密に反映。これにより、短期間での急激なランク変動を抑制し、各プレイヤーが自分の実力に見合った対戦環境を得られるよう設計されています。
全体として、競技性と公平性の両立を意識したシステム設計といえるでしょう。
特筆すべきは、シーズンごとにMMR(Matchmaking Rating)の調整が入る点です。これは新シーズンの開始時にランクが一時的にリセットされ、再配置戦(プレースメントマッチ)によって改めて適正ランクが決定されるためです。したがって、同じ「プラチナIII」でも、シーズンによってその難易度や平均MMRが変動します。
全体的な傾向として、ゴールドからダイアモンド帯のプレイヤーが最も多く、いわゆる“中堅層”としてランク分布の中心を形成しています。このゾーンでは、基本操作の安定性と試合中の判断力が求められ、昇格のためには個々のプレー精度だけでなくチーム全体の連携意識も不可欠です。
(出典:Psyonix公式フォーラム)
ランク帯の割合/目安と傾向

シーズン16時点におけるロケットリーグのランク帯分布を分析すると、プレイヤー人口の偏りが明確に見えてきます。全体としてゴールドからプラチナ、さらにダイアモンドにかけてプレイヤー数が集中しており、いわゆる「中間帯」が母数の中心という構図です。以下に、おおよその割合と特徴を整理しました。
- ゴールド〜ダイアモンド帯:全体の約60〜70%を占める層である。
- ブロンズ・シルバー帯:初心者層として全体の1〜5%程度である。
- チャンピオン帯以上:上位約10%前後の限られた実力層である。
- グランドチャンピオン・スパーソニックレジェンド:上位数%のみが到達できる最高峰である。
中間帯の中でも特に「ゴールドIII〜プラチナII」は最も競争が激しいゾーンとされ、この層での停滞は多くのプレイヤーに共通する課題です。ここでは、単なるボール操作の巧拙だけでなく、次のような総合的なスキルが問われます。
- ブースト管理の最適化
- 味方とのローテーション理解
- 空中プレーとポジショニングの安定化
これらの要素が噛み合わないと、プレースタイルの安定化が難しく、昇格を阻む要因となります。判断の一貫性を保つことが特に難しく、この帯域での「壁」を感じるプレイヤーが多いのも特徴です。
さらに上位の「ダイアモンド帯」では、個々の技術面がすでに成熟段階に達しています。この層ではチーム内の役割理解とポジショニングの精度が昇格の鍵を握ります。わずかな判断ミスが失点に直結するため、安定して勝ち越すには以下の要素が不可欠です。
- プレイの再現性を高める精度の維持
- 試合展開に応じた柔軟な状況判断力
これらを継続的に磨くことで、安定した勝率と昇格の可能性が大きく高まります。
また、プレイヤー人口の多い時間帯や地域によってもマッチングの質に差が生じるため、同じランク帯でもプレイ環境に応じた微妙な難易度差が存在します。これらの要因が組み合わさることで、ロケットリーグのランクシステムは非常に奥深く、かつ動的なバランスを保っているのです。
ランク分布と最新のデータ指標
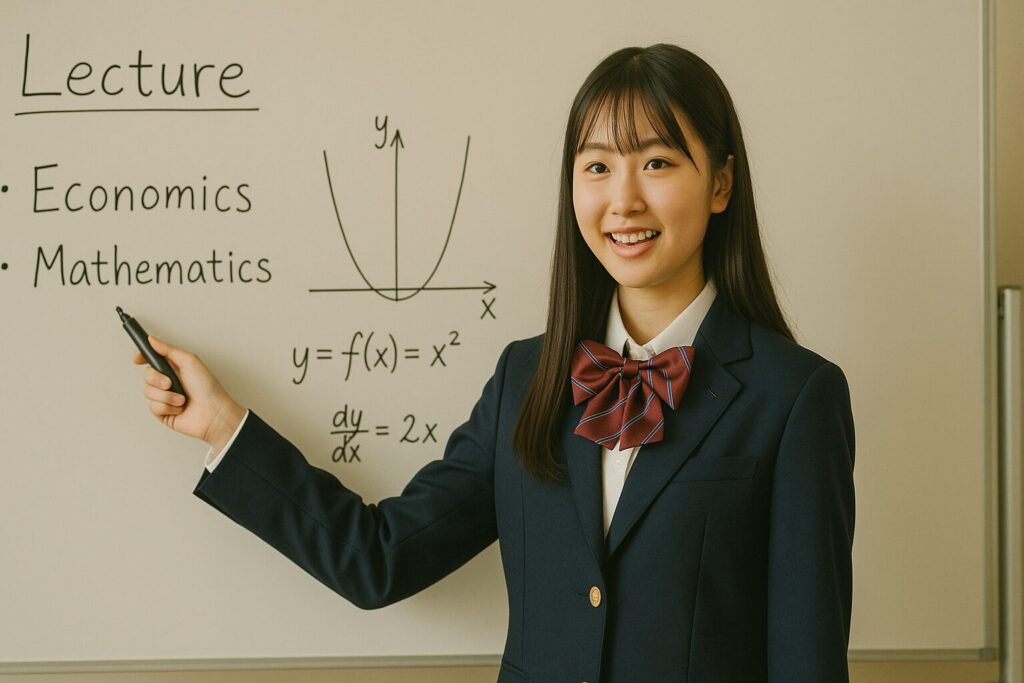
ロケットリーグの最新ランク分布(シーズン16基準)は、モードごとや地域ごとにやや異なりますが、3v3スタンダードを基準とした代表的な統計を以下に示します。このデータは大規模なプレイヤー群からのサンプリングを基にした概算値であり、シーズン内のランク変動によって若干の誤差が発生します。
| 指標パターン | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤ | チャンピオン | GC | SSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターンAの目安 | 約1% | 約3% | 約25% | 約33% | 約27% | 約8% | 1%未満 | 約0.03% |
| パターンBの目安 | 約1.5% | 約17% | 約39% | 約26% | 約13% | 約4% | 約0.3% | 約0.03% |
両パターンを比較すると、統計の抽出方法や対象プレイヤー層により数値は変動しますが、共通して「ゴールド〜ダイアモンド帯が全体の過半数を占める」という傾向が明確です。
最上位ランクであるスパーソニックレジェンドは、全プレイヤーのうち0.03%前後という極めて希少な層に限定されており、統計上も誤差の範囲に近いほど小さい値を示します。
この分布傾向は、ランクアップの難易度を示す重要な指標でもあります。つまり、ダイヤ帯以降では1つ上のランクに昇格するために求められる勝率や連勝数が急激に上がり、上位帯へ進むほど成長速度が鈍化します。逆にゴールドやプラチナでは、練習時間の蓄積によるスキル向上が比較的早くランク変動に反映されやすい段階です。
また、モードによっても分布の形状が異なり、1v1デュエルではスキル差が顕著に反映されるためプラチナ帯が最も厚く、3v3ではチームプレーの要素が強くなるためプラチナからダイヤにかけてバランスよく分布。これらの統計はプレイヤーの行動傾向やゲームデザインの方向性を理解する上でも重要な情報源となっています。
(出典:Rocket League Rank Distribution Season 16 – CS2)
部門ごとの仕組みと意味

ロケットリーグのランクシステムでは、各ランクの内部に「部門(ディビジョン)」が設けられています。この部門制度は、プレイヤーの実力をより正確に反映するための仕組みであり、ランクIからランクIII、場合によってはIVまでの段階構成です。
各部門の中で勝敗を重ねることで内部レート(MMR)が上下し、一定値を超えると次の部門、または次のランクへ昇格する流れとなります。反対に基準値を下回ると降格が発生するシステムです。
このように細かく段階が設定されていることで、プレイヤーのスキル変化を緩やかに反映させることができ、急激な昇格・降格による不公平感やストレスを軽減しています。
特に新シーズン開始時のプレースメントマッチ後は、MMRの安定化が起こるまで変動が大きくなるため、部門の存在は実力を精密に補正する重要な役割といえるでしょう。
部門制度がもたらすメリット
- 実力の段階的な可視化
プレイヤーが自分の成長をより細かく実感できるため、モチベーション維持につながります。たとえば「プラチナIからプラチナII」への昇格は小さな達成感を積み重ねる形でプレイ継続を促します。 - マッチング精度の向上
部門の存在により、ほぼ同等の実力を持つプレイヤー同士がマッチングされやすくなり、試合の公平性と競技性が高まります。これにより、一方的な試合展開が起こりにくく、ゲーム全体の満足度が向上します。 - 昇降格の緩衝機能
一度の連敗で大きくランクを落とすことを防ぎ、短期的な運や不調による影響を軽減します。このシステムによって、真の実力が安定して評価されやすくなっています。
MMRの内部処理は非公開ながら、Psyonix社が公開している情報によると、勝利時の獲得ポイントや敗北時の減少幅は、対戦相手とのレート差に基づき自動的に調整されています。
強い相手に勝てば多くのMMRを獲得でき、格下に負けると大きく失う仕組みです。この「動的レート変動アルゴリズム」により、部門ごとのマッチバランスが長期的に安定するよう設計されています。
(出典:Rocket League Party Skill and Matchmaking – Epic Games)
レートとランクの関係

ロケットリーグのランクは、見た目上の称号(ゴールド、ダイヤモンドなど)として表示されますが、その根底にあるのがMMR(Matchmaking Rating)と呼ばれる内部レートです。MMRはプレイヤーの実力を数値化したもので、勝敗結果によって増減します。この数値こそが実際のランク昇降を決定する中核的な要素です。
MMRは対戦形式(1v1、2v2、3v3など)ごとに個別に管理されており、例えば「2v2でダイヤモンドII」のプレイヤーでも、「3v3ではプラチナIII」に位置する場合が。それぞれのモードで異なるスキルセットが求められるため、MMRはモード間で独立して算出されています。
以下は、1v1モードにおける代表的なレート範囲の一例です。実際の数値はシーズンや競技人口の変化に応じて微調整されるため、あくまで目安として参照してください。
| ランク帯 | レート範囲の例(1v1基準) |
|---|---|
| ブロンズ | 約87〜274 |
| シルバー | 約263〜454 |
| ゴールド | 約455〜634 |
| プラチナ | 約635〜814 |
| ダイヤモンド | 約815〜994 |
| チャンピオン | 約995〜1168 |
| グランドチャンピオン | 約1175〜1353 |
| スパーソニックレジェンド | 約1345以上 |
これらの数値は固定ではなく、プレイヤー人口の増減や新シーズンの調整によって上下します。たとえば、新規参入者が増えたシーズンでは中間帯(プラチナ〜ダイヤ)のレートが若干上方修正される傾向があります。これは、全体のスキル分布を一定のバランスに保つための調整です。
MMRシステムの仕組みを理解する
- 勝敗による変動
勝利するとMMRが上昇し、敗北すると下降。変動幅は相手チームの平均レートとの差によって変化し、格上に勝つほど上昇幅が大きくなります。 - 非公開の内部計算
Psyonix社は正確な算出式を公表していませんが、Eloレーティングを基に独自の補正を加えたモデルが採用されているとされています。このため、短期的な勝敗よりも長期的なパフォーマンスの平均値が実力として反映されます。 - シーズン間でのリセット
新シーズン開始時には、全プレイヤーのMMRが部分的にリセットされ、再度プレースメントマッチで適正位置が決まります。この際、一部の上位層は過去シーズンの成績が加味されるため、完全なリセットではありません。
以上の仕組みにより、ロケットリーグのランク制度は単なる勝敗記録ではなく、長期的なスキル推移を反映する公平なレーティングシステムとして機能しています。
(出典:About Psyonix | Psyonix
【ロケットリーグ】ランク分布の最新解説

- 人数とモード別の傾向
- ロケットリーグのプレイヤー人口は?
- ランクアップが難しい理由を整理
- チャンピオン帯で求められる力
- ロケットリーグのレベルはどうやって確認する?
- 【まとめ】ロケットリーグにおけるランク分布の要点
人数とモード別の傾向
ロケットリーグの競技人口をモード別に見ると、3v3が最もプレイヤー母数が大きく、全体の分布傾向を最も正確に反映しています。この3v3モードは「スタンダード」と呼ばれ、チームプレーの戦略性が最も強く求められる形式です。そのため、上級者ほどこのモードを主戦場とする傾向があります。
2v2は個々のプレイヤーの影響力が高く、より個人技と判断力が試される構造となっており、プラチナからダイアモンドにかけての層が厚いことが多い傾向です。1v1は最も純粋な個人技の勝負であり、攻撃と守備をすべて1人で担う必要があるため、極端なプレイスタイルの違いが結果に直接反映されやすいモードとなります。
特にプラチナ帯のプレイヤーが最大勢力を占め、試合内容のばらつきが大きいことが特徴といえるでしょう。
モード別の代表的な目安(シーズン16)
| モード | 中心帯の例 | 上位帯の目安 |
|---|---|---|
| 1v1 | プラチナI〜IIIが最多 | チャンピオンI以上は約2〜3% |
| 2v2 | プラチナ〜ダイヤで約55% | グラチャン以上は3%未満 |
| 3v3 | ゴールド〜プラチナが最厚 | チャンピオン以上は一桁台前半 |
この表からも分かるように、すべてのモードにおいて中間層(プラチナ〜ダイヤ)が分布の中心を形成しています。
これは、ロケットリーグというゲームが単なる反射神経やエイムの正確さだけでなく、「ポジショニング」「ローテーション」「味方との連携」といった多角的なスキルを必要とするため、ある程度の経験と知識を持ったプレイヤーがこの帯域に集中する構造となっているためです。
モードの母数が大きいほど、同一ランク帯に属するプレイヤーの実力幅も広がる傾向があります。3v3のようにプレイヤー数が多いモードでは、同じ「プラチナII」でも実力差が顕著に現れやすく、昇格直後のプレイヤーと降格寸前のプレイヤーが同じ試合で対峙することも。
そのため、1試合ごとの難易度が安定しにくく、ランク帯の中で勝率の波が大きくなる傾向があります。
(出典:Rocket League Rank Distribution Season 16 – CS2
ロケットリーグのプレイヤー人口は?

ロケットリーグは2020年の基本無料化以降、世界中でプレイヤー人口が飛躍的に増加しました。Epic Gamesの公式発表によると、全世界で累計プレイヤー数は1億人を突破しており、現在も安定したアクティブユーザー数を維持しています。
月間アクティブユーザー数(MAU)は数千万規模に達し、同時接続者数でも常に上位を維持しているタイトルの一つです。
ただし、このうちランクマッチに参加しているのは全体の一部に過ぎません。カジュアルモードやイベントモードを中心にプレイする層を除くと、競技的ランクマッチ人口は全体の30〜40%前後とされています。
ランク分布の中心がゴールド〜プラチナ帯に形成されていることからも分かるように、大多数のプレイヤーは中間層で安定して活動しています。
地域別の傾向を見ると、北米とヨーロッパが上位帯プレイヤーの厚みを持つ地域です。特に北米サーバーはプロリーグ(RLCS)への参加選手が多く、競技レベルが全体的に高い傾向が。
一方で、アジア地域(日本・韓国・東南アジア)ではプレイヤー人口が急速に拡大しているものの、まだ上位層よりもプラチナ〜ダイヤの中間層が中心となっています。これにより、試合のマッチング時間は短く、一定の難易度バランスを保ちながらプレイできる環境が整っているのです。
また、プレイヤー人口の増加に伴い、クロスプラットフォームでの対戦機能(PC・PS・Switch・Xbox間の統合マッチング)も進化し、地域やデバイスに関係なく安定した対戦が可能です。これはeスポーツタイトルとしての裾野を広げ、世界中のプレイヤーが同じ競技環境で切磋琢磨できる基盤を築いていると言えます。
(出典:Epic Games公式)
ランクアップが難しい理由を整理

ロケットリーグでランクアップが難しいと感じる理由は、単純な勝敗ではなく「複数のスキル領域を同時に高水準で維持する必要がある」という設計思想にあります。ゲームの物理演算エンジンは非常に精密で、ボールの速度、角度、反射、摩擦がリアルタイムに計算される仕組みです。
そのため、車体の角度や速度、ブーストの使い方ひとつで結果が大きく変化するのが特徴といえるでしょう。
技術面での難しさ
ロケットリーグでは、単に「ボールを当てる」だけでは勝てません。空中でのボールコントロール(エアリアル)、壁を利用したシュート、天井やゴールポストを利用したクリアなど、複雑なプレイング技術が必要です。これらは、FPSや格闘ゲームとは異なり、三次元的な動作制御を前提としています。
そのため、視点操作やブースト管理を誤ると、一瞬でポジションを失うリスクがあります。
戦術面での難しさ
もう一つの大きな要因は、ローテーションと呼ばれるチーム戦術の理解不足です。ローテーションとは、攻撃と守備をチームで循環的に入れ替える動きのことを指します。
この概念を理解していないプレイヤーが多いランク帯では、チーム全体の配置が崩れ、失点を招くケースが頻発。個人技が通用するゴールド帯までは問題ありませんが、プラチナ以降は連携意識が欠けるとすぐに結果に響きます。
メンタル面と環境要因
また、ロケットリーグはメンタル的な影響も非常に大きいゲームです。1ミスが失点に直結しやすく、短い試合時間(5分)の中で流れが一変する展開となります。
そのため、集中力と冷静さを保つことが勝率に直結する構図です。さらに、ソロキュー(1人でランクマッチに参加する形式)では味方の実力差や通信の少なさが難易度を上げる要因にもなっています。
したがって、ランクを安定して上げるには「技術・戦術・メンタル」の三要素を段階的に整える必要があります。練習を重ねる際は、まずはブースト管理や空中制御の習熟から始め、次にポジショニングと味方の動きの予測へと意識を広げていくと効果的です。
これらを体系的に磨くことが、長期的にランクアップを実現する最も確実な道筋と言えるでしょう。
(出典:Psyonix公式ガイド『RL Fundamentals』)
チャンピオン帯で求められる力

チャンピオン帯に到達すると、プレイヤーはもはや「上手い」だけでは通用しない領域に入ります。このランク帯では、基礎技術の完成度は当然の前提であり、その上で判断力・予測力・一貫性の3要素が試合結果を大きく左右する構図です。
つまり、どれだけ正確にプレーできるかではなく、「いつ」「どの技術を」「どの状況で」使うかという選択の質が勝敗を分ける段階といえるでしょう。
高精度な空中制御とフェイント技術
チャンピオン帯のプレイヤーは、エアリアル(空中プレー)を常に安定して実行できる水準にあります。ただし、単純にボールへ最速で触れることよりも、相手の意図を外す「フェイント」や「軌道の緩急」が重視される傾向です。
これは、相手のディフェンスラインを崩すための心理的な駆け引きであり、プレイヤーの戦術眼が試される要素でもあるといえるでしょう。
ブースト経済とポジショニングの管理
上位帯では、ブースト経済(Boost Management)の精度が勝率に直結します。ブーストの残量を常に把握し、攻撃・守備・ローテーションの各局面で無駄なく利用することが不可欠です。プロシーンでも、1回の無駄な全消費がカウンター失点につながるケースが多く見られます。
また、味方と衝突しないローテーションを維持することが、試合全体のテンポを安定させる鍵となります。ローテーションが乱れると、守備の隙を生むだけでなく、攻撃時の決定力にも悪影響を与えるからです。
リスク管理と瞬時の意思決定
チャンピオン帯では、リスクを「完全に排除する」ことは不可能です。そのため、重要なのはどのリスクを取るかを瞬時に判断する力です。攻撃に転じる場面でのポジショニング、ボールへのチャレンジタイミング、味方の位置を考慮した守備切り替えなど、わずか1秒の判断遅れが失点に直結します。
この領域のプレイヤーは「攻撃的な守備」や「保守的な攻撃」など、状況に応じてプレースタイルを切り替える柔軟性も持ち合わせています。
チャンピオン帯の本質は「一貫性」
この帯域で安定して勝てるプレイヤーの最大の特徴は、「試合全体を通じてミスを最小限に抑える能力」です。単発のスーパープレーよりも、全試合を通して高い平均パフォーマンスを維持する一貫性が最も評価されます。
すなわち、勝率を押し上げる鍵は、華麗な技術ではなく、状況判断の正確さと再現性の高さにあるのです。
(出典:Psyonix公式競技ガイド『Pedaling to Performance: Exploring the Effects of Pre – LWW』)
ロケットリーグのレベルはどうやって確認する?

ロケットリーグのプレイヤーレベルやランク情報は、複数の仕組みで確認することが可能です。ゲーム内で確認できる要素と、外部サイトを活用してより詳細に分析する方法を理解しておくことで、自己分析やスキル向上に役立ちます。
ゲーム内で確認できる要素
まず、基本情報はゲーム内プロフィール画面で確認可能です。プレイヤーレベルは累積XP(経験値)によって決まり、レベル60以降は「レジェンド」「ロックスター」などの称号として段階的に表示されます。これはプレイ時間や経験の蓄積を示す指標であり、実際のランク(MMR)とは異なります。
さらに、ランクマッチにおけるシーズンランクとモード別MMRは、プレイリスト選択画面でリアルタイムに表示されます。MMR(Matchmaking Rating)は勝敗によって増減する内部数値で、各モード(1v1、2v2、3v3など)ごとに独立して計算されています。これにより、プレイヤーのモードごとの実力差を客観的に把握できるのです。
外部トラッキングツールでの分析
より詳細なデータを確認したい場合は、外部の戦績トラッカー(Stat Tracker)を活用する方法が効果的です。代表的なものに「Rocket League Tracker(https://rocketleague.tracker.network/)」があります。ここではユーザー名またはEpic IDを入力するだけで、以下のような情報を閲覧できます。
- 現在および過去シーズンのランク推移
- 直近の勝率・試合数・平均スコア
- 各モード別のMMRと最高到達ランク
- チームメイトとの勝率やマッチ履歴
このように外部トラッカーを用いることで、自分の成長傾向を可視化し、どの時期に上達したか、あるいはどのランク帯で停滞したかを定量的に分析できます。
長期的な改善を追う視点
重要なのは、プレイヤーレベル(XP)とMMRが必ずしも比例しないという点です。プレイ時間が長くても、効果的な学習と振り返りが伴わなければ、ランク上昇にはつながりません。
特定モードのMMR推移や直近50試合の勝率変化を見ることで、自分の課題をより正確に把握できます。例えば、勝率が50%前後で停滞している場合は「判断ミス」「ポジショニング」「ブースト管理」のいずれかに問題があるケースが多いです。
ロケットパスとの違い
最後に注意すべき点として、ロケットパスの進行度はプレイヤーレベルとは別軸で管理されています。ロケットパスはシーズンごとの限定報酬を得るためのシステムで、XPの獲得速度には影響しますが、MMRやランクには直接関係しません。プレイヤーレベルは経験の証、MMRは実力の証と理解することが大切です。
(出典:Psyonix公式FAQ『Check Out the RLCS FAQ – Rocket League ® – Official Site』)
【まとめ】ロケットリーグにおけるランク分布の要点
この記事のポイントをまとめます。
- 3v3の分布は中間帯が最も厚くSSLは極少数
- ゴールドからダイアモンドに主力人口が集中する
- 1v1はプラチナ中心で個の影響が大きく表れる
- 2v2はプラチナからダイアで人数比が厚くなる
- 3v3は全体傾向に近く分布の指標として使いやすい
- モード母数が大きいほど実力幅も広がりやすい
- MMRは相対値で変動し境界は季節で上下する
- 部門制度で昇降が滑らかになり実力を反映する
- 中間帯では昇格直後と停滞層が混在しやすい
- ランクが難しい背景は操作と判断の二面にある
- チャンピオン帯は精密制御と意思決定が要点
- レベル確認はプロフィールと戦績トラッカー活用
- 地域差はあるが上位はどこでも希少にとどまる
- 自分の位置づけはモード別分布で相対評価する
- 中期でMMR推移を追うと改善点が明確になりやすい
参考:シーズン別の推移イメージ(3v3中心)
| シーズン | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤ | チャンピオン | GCとSSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 約2% | 約10% | 約36% | 約31% | 約16% | 約4.5% | 約0.5% |
| 15 | 約2% | 約13% | 約38% | 約28% | 約14% | 約4.5% | 約0.5% |
| 16 | 約1.5% | 約17% | 約39% | 約26% | 約13% | 約4% | 約0.3% |
代表例:1v1デュエルの分布(例)
| ランク帯 | 目安の割合 |
|---|---|
| プラチナI〜III | 約49% |
| ダイヤI〜III | 約24% |
| チャンピオンI〜III | 約2% |
| グラチャンI〜III | 約0.6% |
| スパーソニックレジェンド | 約0.03% |
上の表と数値はシーズン16周辺の目安として整理しています。モード、地域、計測期間により差が出るため、最新のゲーム内表示と戦績トラッカーの値を合わせて相対的に読み解くと理解が深まります。
最後までお読みいただきありがとうございました。