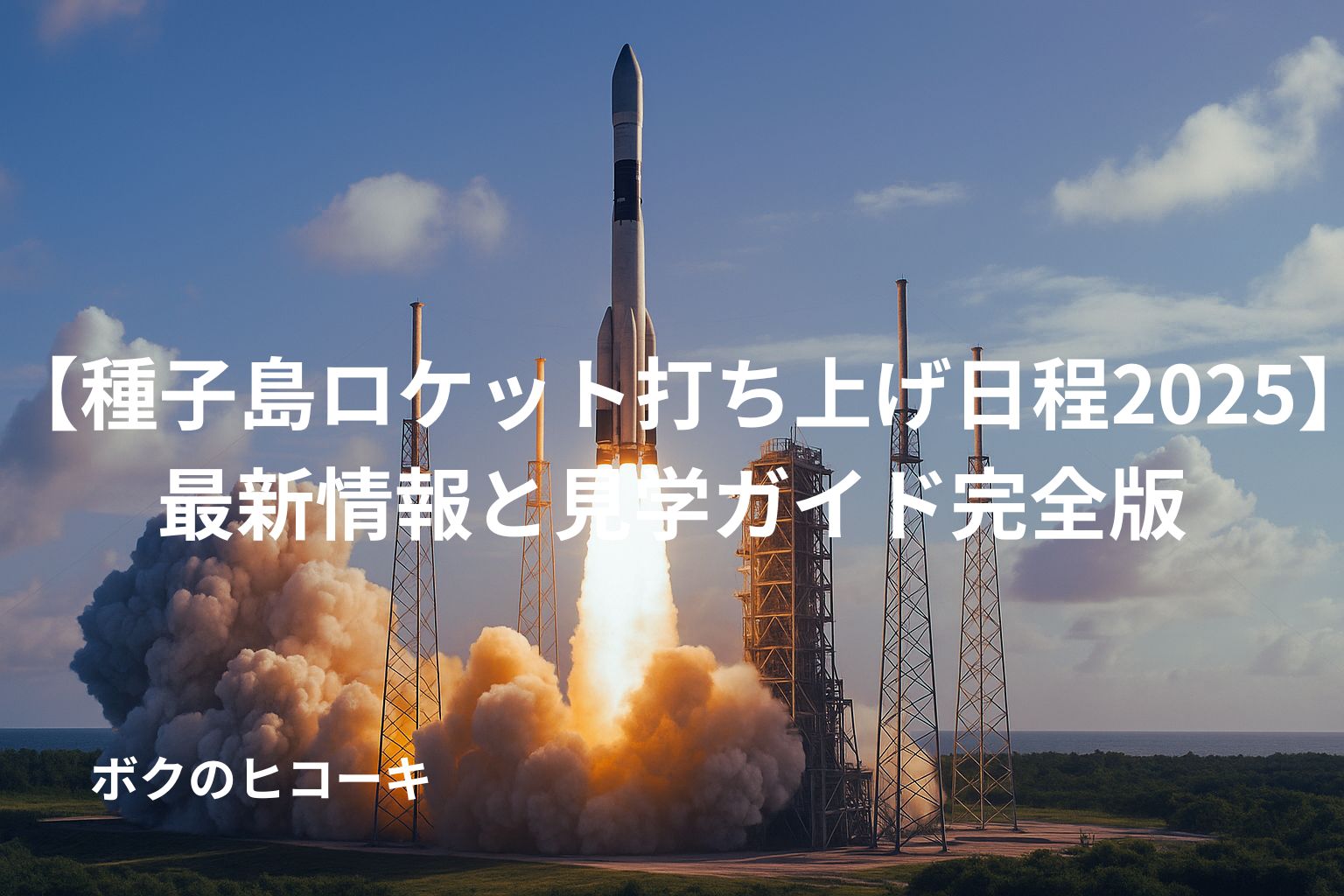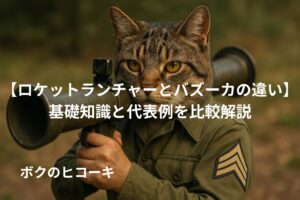「種子島 ロケット 打ち上げ 日程 2025」を調べている方が最短で要点を把握できるよう、2025年の打ち上げ日程 、確定情報や直前の動き、打ち上げ中継の視聴方法、現地の打ち上げ見学 ツアーの選び方まで網羅して解説します。
家族でも安心な打ち上げ 穴場の選定や、「種子島のロケット打ち上げ観覧場所は?」という疑問に答え、「ロケットの打ち上げはいつわかるのですか?」の判断基準、打ち上げ 延期への備え方も整理します。
背景知識として「H2Aはなぜ終了したのですか?」や「日本のH3はなぜ失敗したのですか?」にも触れ、将来の打ち上げ日程を2026年の見通しまで一気に理解できる構成です。
- 2025年の主要打ち上げと直前確定までの流れ
- 公式中継の見方と現地観覧の準備ポイント
- 延期リスクへの備え方と旅程調整のコツ
- 2026年の見通しと基礎知識の押さえどころ
種子島のロケット打ち上げ日程/2025年の全体像

- 打ち上げ日程2025年の一覧
- ロケットの打ち上げはいつわかるのですか?
- 打ち上げ延期の傾向と対策
- 打ち上げ中継の視聴方法ガイド
- H2Aはなぜ終了したのですか?
- 日本のH3はなぜ失敗したのですか?
打ち上げ日程2025年の一覧
2025年に種子島宇宙センターから予定・実施された主要ミッションを一覧化します。時刻は日本標準時(JST)で、ロケットの運用判断や天候の影響により直前で変更される可能性があります。
遠征計画は、少なくとも出発前日と当日朝に最新情報を再確認するのが安全策です。なお、打ち上げ時刻は打ち上げウィンドウ(許容時間帯)の中で確定され、機体や地上設備、航法・管制、追跡局の整合が取れた時点で最終決定されます。
| 打ち上げ日 | ロケット | 打ち上げ時刻(目安) | ペイロード | 予備期間・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | H3 5号機 | 17:30〜19:30 | 準天頂衛星みちびき6号機(QZS-6) | 予備期間は2月3日〜3月31日。前日判断で1日後ろ倒しの上で実施 |
| 6月29日 | H-IIA 50号機 | 1:33:03(打ち上げ窓1:33:03〜1:52:00) | 温室効果ガス・水循環観測技術衛星 GOSAT-GW | H-IIA最終号機。予備期間6月30日〜7月31日 |
| 10月21日 | H3 7号機 | 10:58頃 | 新型宇宙ステーション補給機 HTV-X1 | 予備期間10月22日〜11月30日。ISS運用と国際調整に依存 |
補足解説:機体と打上げウィンドウの読み方
H3ロケットは、第1段にLE-9エンジン、補助推進装置として固体ロケットブースターSRB-3を採用した構成です。ミッション内容に応じてブースターの本数やフェアリング(衛星を覆う外殻)の長さを調整する柔軟設計が特徴となっています。
HTV-X1補給機を打ち上げるH3-24W形態は、高エネルギー軌道への投入を想定した構成で、従来機よりも推力と効率を両立した設計です。これにより、国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送や大型衛星の投入といった多様なミッションに対応可能となっています。
一方、H-IIAロケットは2025年6月の50号機をもってシリーズを完了し、以後はH3への一本化が進みます。これにより、日本の宇宙輸送はよりコスト効率の高い次世代システムへと移行していく流れです。
打ち上げのタイミングを決定する「打ち上げ窓」は、軌道力学上の条件(太陽同期軌道やISSランデブーのための軌道交差角など)を基に算出されます。
さらに、地上の安全確保や飛行経路上の航行警報区域設定などの要件と連動して運用される仕組みとなっています。これらの調整により、安全性と効率性を両立した打ち上げ計画が実現されるのです。
(出典:JAXA プレスリリース・打ち上げ関連ページ https://global.jaxa.jp/)
以上のとおり、2025年はH-IIA最終飛行とH3の実運用移行が並走し、商業・科学・補給の各ミッションが種子島で連続しました。以降のセクションでは、確定時刻がいつ・どのように示されるのか、そして現地観覧や視聴計画の立て方を具体的に解説します。
ロケットの打ち上げはいつわかるのですか?

多くのミッションでは、打ち上げ日の目安が約1か月前に告知され、その後、打ち上げ窓(時刻帯)が示されます。最終的な具体時刻は直前の技術審査や気象判断を経て確定され、当日朝のブリーフィングで最終確認が行われるのが一般的です。
例えば、QZS-6は当初2月1日実施の見込みから気象条件を踏まえて2日にリスケされ、当日は17:30からの打ち上げ窓が提示されました。H-IIA 50号機も、6月24日予定から点検・調整を経て29日の1:33:03に実施されています。
確定までの代表的なタイムライン
- 約1か月前:暫定の打ち上げ日と打ち上げ窓(または目安時刻)を公表
- T–7日〜T–2日:機体状態と気象モデルを突き合わせ、カウントダウンロードマップを更新
- 前日午後〜当日朝:上層風と雷指数、凍結・降雨・雲量の閾値を満たすかを再判定し、GO/NOGOを判断
- L–数時間:機体へ推進剤(液体酸素/液体水素など)を充填し、計装系とレンジセーフティを総合チェック
- L–10分前後:自動シーケンスに移行、最終の保安・航法チェックを完了して点火へ
計画づくりのコツ
観覧や配信視聴の準備は、最初の公式告知を起点に進め、予備期間に合わせて行程を可変化しておくと実見の成功率が高まります。
航空券・宿泊は変更手数料と在庫のバランスを見て、出発2〜3日前に最終確定を行うとリスクを抑えやすくなります。SNSの速報性は魅力的ですが、判断の根拠は最終的に公式の発表に依拠する姿勢が堅実です。
打ち上げ延期の傾向と対策

延期の主因は、大別すると気象と安全確認の二つです。気象では上層風の臨界超過、対流雲に伴う落雷リスク、降雨や低温による機体条件不適合などが挙げられます。
安全確認では、機体や地上設備の計装系に異常兆候が見られた場合、原因切り分けのために延期して点検・交換・再試験を実施。2025年の事例では、QZS-6が悪天候見込みで前日発表により翌日に延期され、H-IIA 50号機も点検・調整を経て実施されました。
運用側は安全最優先の原則で判断し、確保済みの予備期間内で再設定する流れとなっています。
旅行者・観覧者のリスク低減策
- 宿泊と交通:キャンセル・変更規定が緩いプランを選び、予備日を含めた2連泊前提で設計すると柔軟性が高まります
- 現地動線:指定見学場(恵美之江、長谷、宇宙ヶ丘、前之峯)の複数候補を持ち、アクセス規制時の代替経路を事前に確認します
- 当日の情報取得:当日朝の公式サイト更新や自治体告知、会場の掲示で最終判断を確認してから移動を開始します
- 体調・装備:海風と日射の変動が大きいため、季節を問わず防寒・防風と水分補給の備えが観覧継続の鍵になります
判断基準の理解が安心につながる
延期は失敗ではなく、信頼性を担保するための運用判断です。とくに有人施設とランデブーする補給機ミッションや精密な観測衛星では、天候と技術指標の閾値を満たさない限り実施されません。これらの背景を理解した計画づくりが、結果として満足度の高い観覧体験につながります。
打ち上げ中継の視聴方法ガイド

自宅や移動先からでも臨場感を損なわずに視聴するためには、配信元と配信までの流れを押さえておくことが近道です。
公式中継はJAXAのカウントダウンページとYouTubeチャンネルで公開され、配信開始は打ち上げ約1時間前が目安です。番組では、機体やミッションの解説、カウントダウン手順、天候・レンジ(射場と空域・海域の安全確保)の状況が順次アップデートされます。
ISS補給機などランデブー要件が厳しいミッションでは、軌道力学の都合で秒単位まで時刻が決まるため、番組内テロップやアナウンスの更新をこまめに確認すると見逃しを減らせます。
視聴の準備としては、配信開始30分前までに端末とネットワークを整え、解像度を自動ではなく720p以上に固定すると打ち上げ時の噴射炎や分離イベントが判別しやすくなります。
YouTubeは数十秒の配信遅延が生じることがあるため、Xなどのテキスト速報と併用する場合は、ネタバレを避けたい人はSNSの通知を一時的にオフにする運用が有効です。大規模アクセス時は画質が一時的に低下することがあるため、予備としてモバイル回線と固定回線の両方を用意しておくと安心です。
公共施設でのパブリックビューイング(PV)は、家族連れやグループでの観覧に適しています。施設によっては大型スクリーン・同時通訳・専門家の解説が付く場合があり、初学者でも理解しやすい環境が整います。
PVの実施可否や入場方法は各自治体・施設が直前に告知するため、番組ページの案内リンクや自治体サイトを早めに確認しましょう。
なお、配信中はT−10分(自動シーケンス移行)やエンジン点火(T0)、ブースター分離、フェアリング分離、第1段燃焼停止・分離、第2段燃焼開始といった区切りがハイライトです。
これらのイベントは高度・速度・機体方位といったデータと併せて画面に表示されることが多く、基礎用語を把握しておくと理解が大きく進みます。たとえばフェアリング分離は上層大気での空力加熱や音響負荷が下がったタイミングで行われ、ペイロードの露出を可能にする工程です。
発射後の可視光映像が雲で遮られる場合でも、ナレーションとテレメトリ表示で進行が追えるように作られています。
(出典:JAXA カウントダウンページ https://fanfun.jaxa.jp/countdown/)
H2Aはなぜ終了したのですか?

H-IIAは2001年の初飛行から2025年の50号機まで運用され、日本の政府ミッション(地球観測・測位・探査)や商業衛星打ち上げを長期にわたり担ってきました。
高い成功率と柔軟な構成(固体ブースターの本数やフェアリング長の選択)により、多様な軌道需要に応えてきた一方、世界市場ではメタン系エンジンや再使用技術、垂直統合による製造合理化が進み、打ち上げ単価と調達性の面で新世代機の必要性が増していました。
そこで後継として設計されたのがH3です。H3は第1段に高推力のLE-9エンジンを採用し、製造の自動化・部品点数削減・サプライチェーンの再編により、ミッション適合性を保ちつつコストの低減と供給能力の増強を目指しています。
シリーズ移行にあたっては、H-IIAが積み上げた地上設備・運用ノウハウを活用しながら、段階的にH3へ比重を移す方針が示され、最終的にH-IIAは50号機で区切りを迎えました。
この世代交代は、国内ミッションの確実な打ち上げ枠を確保しつつ、国際協調プロジェクト(ISS補給や深宇宙探査)へ機動的に対応するための選択と位置づけられます。結果として、ミッションの多頻度化と、政府・産業界の衛星打ち上げ需要に対する供給の安定化が期待されるのです。
日本のH3はなぜ失敗したのですか?

2023年3月のH3初号機では、第2段エンジンが着火に至らず、所定の安全手順に従って破壊信号が送出され、飛行を終了しました。要因は単一の部品故障に限定せず、点火直前の電気系で想定される複数の不具合シナリオ(過電流、点火器系統の絶縁不良、信号伝送の異常など)を総合的に評価する形で分析が進められました。
ロケットの第2段は軌道投入の最終責任を負うため、着火シーケンスは冗長設計で監視され、異常な閾値を検知した場合は保安上の観点から中止判断が下されます。
初号機後には、電装ハーネスの配索と絶縁設計の見直し、非破壊検査(X線・CT等)の強化、着火器と周辺回路の耐ノイズ性・冗長性向上、製造・検査記録のトレーサビリティ拡充といった複合的な対策が実施されました。
さらに、地上燃焼試験の回数と条件を増やし、実機相当の温度・振動・電磁環境下での再現性を確認するプロセスが追加されています。これらは単なる現象対処に留まらず、製造工程・品質保証・運用手順にまたがる是正措置として組み込まれ、その後のフライトで順次検証が進みました。
打ち上げ失敗という事象は注目されがちですが、宇宙輸送システムでは、初期運用段階での不具合抽出と是正を通して設計成熟度を高めるのが定石です。
今回の経験で得られたデータは、同系統の後続機のみならず、地上設備・射場オペレーションのリスク管理にもフィードバックされ、より頑健な打ち上げ体制の構築につながっています。
種子島ロケット打ち上げ日程 2025年の見学方法

- 種子島ロケット打ち上げの観覧場所は?
- 打ち上げ見学ツアー申込の流れ
- 家族向けの打ち上げ/穴場案内
- 将来の打ち上げ日程 2026年の見通し
- 【まとめ】種子島のロケット打ち上げ日程2025年の要点
種子島ロケット打ち上げの観覧場所は?
種子島でのロケット打ち上げを安全かつ臨場感をもって体験するには、南種子町が管理する指定見学場の利用が基本です。これらの見学場は打ち上げ時の安全半径と風向を考慮して配置されており、観覧可能エリアからは肉眼でも機体の上昇と音響の伝播が体感できます。
特に恵美之江展望公園は射点に最も近い約3km地点にあり、ロケットの噴射炎や振動をはっきりと視認できる希少な場所です。
ただし、安全管理のため事前抽選制が採用され、当選者のみが入場できます。発射当日は射点を中心とした半径3km圏が立入禁止区域として設定され、海上にも航行制限区域が設けられるため、無許可での接近は厳禁です。
これらの制限は、打ち上げ時の落下物・音響衝撃・高温ガス流などからの安全確保を目的としており、地元自治体とJAXAが連携して警備・交通整理を行います。
南種子町役場やJAXAの公式ウェブサイトでは、毎回の打ち上げに合わせて見学可能エリア、交通規制、駐車場位置、シャトルバス運行情報を発表しています(出典:南種子町公式サイト http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/)。
代表的な観覧場所と特徴
下表は、代表的な見学場の位置関係と特徴をまとめたものです。現地は地形や風向によって視界条件が異なり、時間帯によって太陽光の角度も変化するため、観覧の目的に応じて最適な場所を選ぶとよいでしょう。
| 観覧場所 | 距離感 | 特色 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 恵美之江展望公園 | 約3km台 | 射点に最も近く、音圧・光量とも最大級。発射時の振動が地面から伝わるほど迫力がある | 抽選制で当選者のみ入場可能。階段が多く、足元注意 |
| 長谷公園 | 約6km前後 | 開けた視界で機体全体を追いやすい。カメラ撮影に適した角度 | 早朝打ち上げ時は駐車場が混雑。早着推奨 |
| 宇宙ヶ丘公園 | 約7km前後 | 高台から俯瞰でき、煙の広がりまで観察できる | 一部方角で射点が山に隠れる場合がある |
| 前之峯グラウンド | 約7km前後 | 広い平地で滞在が楽。子連れやグループ観覧向き | 射点が遠く、迫力はやや控えめ |
現地での注意事項
見学場では大型三脚やドローンの使用が制限される場合があり、夜間や早朝の打ち上げ時には照明器具を持参する必要があります。また、天候の変化が激しいため、レインウェアや防風ジャケットを携行することが推奨されます。
観覧中はスタッフの指示に従い、指定区域を越えての移動は避けましょう。地元住民との共存を意識し、ゴミの持ち帰りと交通マナーの順守も重要です。
打ち上げ見学ツアー申込の流れ

打ち上げを確実に観覧するためには、計画的な準備が欠かせません。特に宿泊施設が限られる種子島では、打ち上げ発表のタイミングに合わせて早期に行動することが鍵となります。観覧計画は次のような手順で進めるのが一般的です。
- 公式発表の確認:JAXAまたは三菱重工の公式サイトで打ち上げ日と予備期間を確認します。発表時期は通常1か月前で、天候や機体調整により変更される場合もあります。
- 宿泊・交通の仮押さえ:発表直後に宿泊施設が満室になるため、変更可能なプランで早めに確保しておきます。航空券やフェリーの予約も同時進行が望ましいです。
- 恵美之江展望公園の抽選確認:南種子町の公式サイトで抽選受付情報をチェックします。応募期間は打ち上げ約1か月前に設定されることが多く、当選発表は1〜2週間後です。
- 予備日の設定:打ち上げ延期に備えて、前後1〜2日の滞在余裕を確保しておきます。
旅行会社が提供する観覧ツアーでは、宿泊・現地送迎・観覧チケットをセットで手配してくれる場合が多く、初心者には特に便利です。ツアーを選ぶ際は、延期時の取り扱い規定(無料変更の可否、現地延泊対応など)を必ず確認しましょう。
打ち上げが予備日に移動した場合でも、柔軟に対応できるプランを選ぶことでリスクを軽減できます。
また、現地観覧が難しい場合には、JAXAの特設ページで案内されるパブリックビューイング(PV)の利用も有効です。南種子町役場前や中種子町体育館などの公共施設では、大型スクリーンと専門解説付きのPVが実施されることがあり、家族連れでも快適に視聴できます。
予約・移動のポイント
- 打ち上げは早朝または夜間に行われることが多く、交通手段の確保が難しいため、宿泊地は見学場へのアクセスを最優先に選定する
- 島内はバスの本数が限られるため、レンタカーまたはツアーバス利用が基本
- 台風接近や強風による延期の可能性を想定し、旅行保険への加入も検討する
打ち上げ見学は、観光と科学の融合体験として高い人気を誇りますが、同時に多くの来場者が集中するイベントでもあります。事前の情報収集と柔軟なスケジュール設計が、満足度の高い観覧体験につながるのです。
(出典:JAXA 打ち上げ特設ページ https://global.jaxa.jp/)
家族向けの打ち上げ/穴場案内

家族でロケット打ち上げを楽しむ際は、アクセスのしやすさ、施設の充実度、子どもの安全確保の3点を軸に観覧場所を選ぶことが重要です。
特に長谷公園と宇宙ヶ丘公園は、駐車場やトイレの動線が明快で、滞在しやすい環境が整っています。視界の広さと安全性のバランスが取れており、子ども連れでも安心して観覧できる点が特徴です。
長谷公園は海沿いに面しており、打ち上げ時の轟音や光を間近に感じつつも比較的ゆったりとスペースを確保できる人気スポットです。広場や遊具が整備されているため、発射待機中も子どもたちが飽きにくく、ファミリー層に適しています。
宇宙ヶ丘公園は標高約100mの小高い丘の上にあり、発射場全体を俯瞰できる視界の広さが魅力です。駐車場から観覧スペースまで緩やかな傾斜で、ベビーカー利用者にも比較的移動しやすい設計となっています。
一方で、恵美之江展望公園は射点から約3kmと最至近であるため迫力は格別ですが、階段が多く、抽選制のため混雑リスクが高い点に注意が必要です。抽選に外れた場合に備えて、長谷公園や宇宙ヶ丘公園を代替候補として計画に組み込むのが現実的と言えます。
観覧場所以外にも、地元住民に知られる「穴場スポット」として、前之峯グラウンドや竹崎海岸付近の高台が挙げられます。これらは距離的にはやや離れますが、混雑を避けながら打ち上げ全体を見渡すことができるため、ゆっくりとした観覧を希望する家族に向いているからです。
また、地元観光協会が運営する案内所では、過去の風向データを基にした観覧位置のアドバイスや、打ち上げ時の交通規制マップも配布されています。
安全面では、子どもが長時間屋外にいることを想定し、耳栓やサングラスの持参が推奨されます。ロケットの打ち上げ時には音圧が100デシベル前後に達する場合もあるため、小さな子どもや乳幼児は聴覚保護が必要です。
さらに、待機時間が長くなることも多いため、折りたたみ椅子やレジャーシートを持参し、休憩しながら観覧できる体制を整えておくと安心です。
(出典:観光ガイド – 鹿児島 – 南種子町 )
滞在快適度を上げるワンポイント
種子島は海に囲まれた立地のため、海風や強い日差しの影響を受けやすい地域です。季節を問わず気候対策を行うことが、快適にロケット打ち上げを観覧するための大切なポイントになります。
特に以下のような準備を整えておくと安心です。
- 冬季(12月〜2月)は海風が強く、体感温度が低下しやすい。防風ジャケット・帽子・膝掛けを携行することが望ましい。
- 夏季(7月〜9月)は紫外線量が全国平均より約15%高い傾向がある。日焼け止めやUVカットパラソルを活用することが効果的である。
乳幼児連れの家庭は、観覧場所までの動線を事前に把握しておくと安心です。宇宙ヶ丘公園は駐車場から観覧スペースまで約150mの緩やかな坂道が続き、ベビーカーでの移動も比較的容易です。一方、長谷公園は舗装路が多く歩きやすい反面、トイレの数が限られているため、事前に利用を済ませておくことをおすすめします。
観覧当日は長時間の待機になることも多く、2時間以上に及ぶケースもあります。現地の自動販売機は少なく、交通規制で周辺のコンビニも混雑するため、軽食や飲料水をあらかじめ用意しておきましょう。
- 飲料は冷凍ボトルや携帯クーラーバッグに入れて持参するのが望ましい。
- 水分補給をこまめに行うことで、熱中症のリスクを下げられる。
また、夜間に打ち上げが行われる場合は次の点にも注意が必要です。
- 夏場の夜は蚊が多く、虫除けスプレーを携行することが望ましい。
- 照明の少ない場所では懐中電灯を使用し、足元の安全を確保することが大切である。
これらの対策を講じることで、どの季節でも快適かつ安全に観覧体験を楽しむことができます。
将来の打ち上げ日程 2026年の見通し

2026年の種子島宇宙センターでは、日本の宇宙輸送能力を象徴するH3ロケットの本格運用が続き、複数の重要ミッションが予定されています。
最も注目されるのが、火星衛星探査計画MMX(Martian Moons eXploration)です。MMXは、火星の衛星フォボスとダイモスの起源を調べ、フォボスの地表サンプルを採取して2031年に地球へ帰還するという壮大なミッションです。
JAXAによると、MMXは日本の会計年度2026年(JFY 2026)にH3ロケットで打ち上げ予定とされています(出典:JAXA公式MMX特設サイト https://mmx.jaxa.jp)。
このプロジェクトは、国際的な協力体制のもとで進められており、NASA・CNSA(中国国家航天局)・ESA(欧州宇宙機関)とのデータ共有や技術連携が想定されています。探査機には高解像度カメラ(TENGOO)、分光計、フォボス着陸機(PEX)などが搭載され、地表物質の組成・構造を多角的に解析します。
さらに、H3ロケットによる新型宇宙ステーション補給機 HTV-X2およびHTV-X3の打ち上げも2026年度に予定されています。HTV-Xシリーズは、従来のこうのとり(HTV)に比べて輸送効率が約1.2倍向上し、再利用を視野に入れた設計が採用されています。
これにより、ISSや将来の月周回基地「Gateway」への物資補給が安定的に行える体制が整う見込みです。
ただし、これらの打ち上げスケジュールは国際調整や機体試験の進捗に左右されるため、確定情報は打ち上げの約3か月前に公式発表されます。特にMMXのような深宇宙探査ミッションでは、地球と火星の相対位置が打ち上げ機会を左右するため、予定期間内でも細かな調整が発生します。
2026年は、日本の宇宙開発が「新世代運用フェーズ」へと移行する節目の年となる見通しです。H3の信頼性確立と国際探査への本格参入は、日本の宇宙産業全体にとって重要な転換点となるでしょう。
種子島 ロケット 打ち上げ 日程 2025の要点まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 2025年はH-IIA最終便とH3実運用が並行した年である
- 主要三案件はQZS-6とGOSAT-GWとHTV-X1である
- 打ち上げの具体時刻は直前に最終確定される
- 予備期間の設定を前提に旅程へ余裕を持たせる
- 公式の中継はJAXAカウントダウンと配信で視聴可能
- 恵美之江は抽選制で最至近から迫力を体感できる
- 長谷と宇宙ヶ丘は家族連れ向きで動線が分かりやすい
- 当日は発射点半径三キロ圏が立入禁止となる
- 延期要因は天候と安全確認による再設定が中心である
- 観覧計画は複数候補と代替手段を必ず準備する
- H-IIA終了の背景はH3への世代交代方針にある
- H3初号機不具合は第2段着火不良が契機である
- 2026年はMMXとHTV-X後続が主要テーマとなる
- 最新予定はJAXAと南種子町の告知を基準に確認する
- 種子島 ロケット 打ち上げ 日程 2025の情報は随時更新される
最後までお読みいただきありがとうございました。