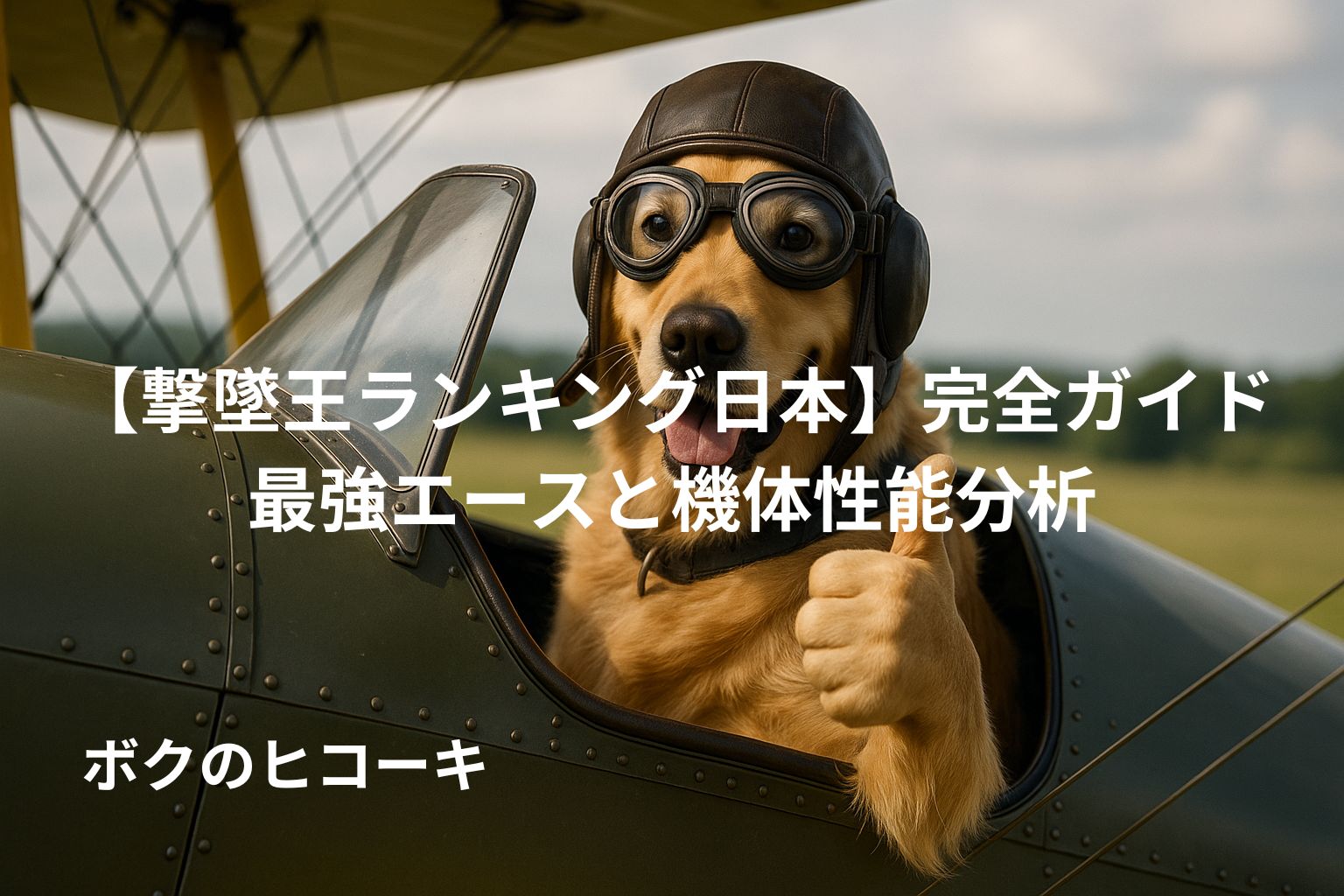日本の撃墜王に関心を持つ読者に向け、「撃墜王ランキング日本」の全体像を一目で把握できる内容にまとめています。
この記事では日本陸海軍の代表的なエースパイロットをはじめ、坂井三郎の評価や岩本徹三の撃墜数に関する見解、さらに菅野直や赤松貞明といった著名な撃墜王の戦歴を比較可能な形で整理。加えて、有名な日本のエースパイロットの戦績を総覧し、戦術や搭乗機体ごとの強みをランキング形式で可視化する視点も盛り込んでいます。
検索で多い「日本一の撃墜王は誰か」「零戦の最強パイロットは誰か」「日本の最年長パイロットは誰か」といった疑問にも、基礎データや検証した根拠を示しつつ答える構成にしました。
あわせて日本軍によるB-29撃墜数の推定や主要な迎撃エピソードも概説し、歴史的背景の理解を深められる内容です。
- 陸海軍の著名エースと撃墜数の基礎を整理
- 主要パイロットの戦歴と評価の根拠を理解
- 機体性能と戦術から強みの違いを把握
- B-29迎撃の実態と推定値の幅を把握
【撃墜王ランキング】日本の全体像

- 【撃墜王】坂井三郎
- 岩本徹三の撃墜数
- 撃墜王 菅野直と日本 撃墜王 赤松貞明
- 【日本の撃墜王】陸軍のエースパイロット
- 日本軍によるB-29撃墜数
- 有名な日本エースパイロットの戦歴まとめ
【撃墜王】坂井三郎
坂井三郎は公認28機、自称64機の撃墜記録で広く知られ、零式艦上戦闘機を主力に中国大陸から南太平洋、本土防空まで多方面で飛び続けました。評価が割れる点は、回想記と現存する戦闘記録の突き合わせで未確定箇所が残るためです。
ただし、操縦の正確性、被弾回避の判断、僚機喪失を抑える統率など、戦術上の堅実さは多くの証言で一致します。
零戦の強みである大半径・低速域の粘りを引き出し、空戦開始前の位置取り(高度と太陽位置)、交戦離脱のタイミング、燃料マージン管理といった戦闘管理に長けていました。結果として、長期の前線稼働と生還率の高さに結びつき、のちの教官としての育成にも活かされています。
ガダルカナルでの負傷と影響
1942年のガダルカナル上空で、坂井はSBDドーントレスを戦闘機と誤認して背後に近接、後部旋回銃座からの射撃を受けて頭部に重傷を負いました。
航法・機上無線の制約が大きい当時、視力低下は致命的なハンディでしたが、復帰後は前線での実戦投入と並行して、若手パイロットへの空戦手順の標準化、会敵前ブリーフィングの徹底など、部隊力の底上げに注力しています。
教範的には、被弾の直接原因は目標識別の誤りと射撃圏への不用意な侵入にありますが、坂井のケースは視界条件・太陽位置・機種識別の限界という当時の環境要因も示しています。この経験は、以後の識別訓練や接近角の選び方(特に後上方からの死角利用や射界外接近)に反映され、部隊全体の損耗抑制に資しました。
岩本徹三の撃墜数

岩本徹三の撃墜数は自己申告で202機に達し、日本のエースとして突出した存在です。公式換算ではより低い推定に収まる見解もあるものの、ソロモンおよびラバウル戦線での長期連続戦闘における高効率の戦果は、多数の史料で一貫して指摘されています。
零戦の長航続距離を活用し、前線基地のリソース制約下でも、迎撃・護衛・索敵の複合任務を高い整合で回していた点が注目されます。
戦術面では、上方優位からの一撃離脱を基本に、通信で味方の散開・集中を柔軟にコントロールしていました。
零戦の弱点である防弾・防漏の不足を、交戦前の位置取りと短時間交戦で補い、弾薬管理(20mmと7.7mmの使い分け)で撃墜効率を引き上げていたのです。燃料・潤滑・補給の逼迫が常態化する中での継続的高戦果は、純粋な操縦技量に加えて戦闘マネジメント能力の高さを示しています。
数値の見方と評価
自己申告は200機超と突出し、伝説性を帯びます。撃墜判定のメカニズムは国や時期で差があり、日本側記録では、現場の確証写真・残骸確認・他機証言の組み合わせが十分に揃わないまま暫定計上されるケースが少なくありませんでした。
反対に、米英側の喪失記録と一対一で突合できない戦闘も多く、最終合算が難しい構造的要因があります。
個別戦闘詳報の散逸により、厳密な合算は難しい側面があります。
特に前線基地の移動や空襲による文書喪失、帰還後に損失となった敵機の扱い、共同戦果の割り振りなどが誤差要因です。評価にあたっては、単発の最大値よりも一定期間あたりの撃墜率、 sortieあたりの有効命中率、被撃墜回避率(損耗率)といった運用指標を見る視点が有効です。
長期の前線稼働と高い生還率、戦術的柔軟性が評価の核になります。岩本の場合、複数戦域での継続的な sortie消化と、交戦時間の短縮・弾薬配分の最適化・離脱判断の的確さが、戦果と生存性を同時に押し上げました。
以上の点を踏まえると、数の絶対値だけでなく、戦域条件・機体性能・部隊運用を含めた総合指標で位置づけることが妥当と言えます。
参考資料:Wikipedia「米国戦略爆撃調査」
【撃墜王】菅野直(かんの なおし)と赤松貞明

両名はいずれも太平洋戦争末期の防空・迎撃戦において、際立った存在感を示したエースパイロットです。菅野直は紫電改を中心に、赤松貞明は雷電を駆使し、それぞれ異なる機体特性を最大限に活用しました。
彼らは戦術思想やリーダーシップの面でも対照的で、菅野は緻密な編隊戦術と新しい迎撃法の導入で部隊全体の力を引き出し、赤松は単機突入や高リスク戦術で個人戦果を重ねたと伝えられています。大型爆撃機に対抗するための高火力・高速機運用は、陸海軍を通じて最優先課題であり、この二人の存在はその象徴的な一例です。
菅野直の強み

菅野直は第343海軍航空隊に所属し、紫電改を駆ってB-24やB-29などの大型機に対し、前上方背面垂直攻撃とされる進入法を駆使したと伝わっています。
この戦術は、敵編隊の死角にあたる正面上方から高速度で接近し、機首下に集まる火力の弱点を突くものです。短時間で射撃し、慣性を活かして離脱することで反撃リスクを最小化しました。
紫電改は1,990馬力級の誉二一型エンジンと優れた上昇力、20mm機関砲4門という重武装を備え、従来の零戦に比べて高高度性能が向上していました。菅野はこの特性を生かし、大型爆撃機に対して短期間で高い戦果を挙げ、第343空のリーダー格として隊の士気を牽引したのです。
部隊全体の迎撃効率や新戦法の確立においても大きな役割を果たし、実質的に日本海軍防空戦力の最後の砦とされました。
赤松貞明の強み

赤松貞明は雷電を駆り、本土上空でB-29をはじめとする大型爆撃機やその護衛戦闘機に果敢に挑みました。
雷電は三菱製の局地戦闘機で、2,000馬力超の火星二三型エンジンと20mm機関砲を搭載し、高速かつ重武装で知られます。特に高高度における加速力と一撃離脱性能に優れ、重爆撃機迎撃に最適化された設計でした。
赤松はこうした性能を活かし、単機で敵編隊に突入する戦術や、雷電の短い旋回半径を使った急旋回射撃で敵の虚を突いたとされています。

撃墜数は公式整理で30〜40機前後とされますが、特徴的なのはその生還率の高さです。高リスクの戦術を取りながらも生還を繰り返した背景には、敵弾を回避する独特の機動や、燃料・弾薬管理、離脱判断の的確さがありました。この「攻め」と「生還」の両立が、赤松を象徴的存在に押し上げました。
二人はいずれも終戦期の高性能機を使いこなし、数的劣勢の中でも迎撃に成果を残しました。菅野が短期集中で戦果を挙げたのに対し、赤松は長期で安定した撃墜を重ねるなど、同じ防空戦でもアプローチが異なります。
これらの事例は、限られたリソースと時間の中でいかに戦力を最大化するかという課題に対する異なる答えとしても位置付けられます。
【日本の撃墜王】陸軍のエースパイロット

陸軍の撃墜王として知られるのは、篠原弘道(約58機)、黒江保彦(約51機)、穴吹智(51機)、坂川敏雄(49機以上)などです。活動の舞台はノモンハン、ビルマ戦線、中国大陸、本土防空など多岐にわたり、それぞれの戦域で求められる任務と高度帯に合わせて機種選定や戦術が変化しました。

九七式戦闘機の軽快な格闘性能、一式戦「隼」の長航続距離、二式戦「鍾馗」の高上昇力、三式戦「飛燕」の液冷エンジン由来の高速性、四式戦「疾風」・五式戦の終戦期高性能といった特性の違いが、パイロットの成果や生存性に直結しています。

戦時の個別戦闘詳報は散逸・欠落が多く、同一戦果を複数者で計上してしまう重複や、撃墜と撃破(帰還不能の大破と損傷帰還)の区別が曖昧になりやすい事情もあり、撃墜数には幅があります。数値は固定値ではなく推定レンジとして理解し、戦域・任務・搭乗機の文脈に乗せて読み解くことが大切です。
主な戦術面では、低中高度での格闘戦に強い機体では横旋回とエネルギー保持を両立させる旋回戦、高高度での迎撃任務では上昇余裕を活かした上方優位からの一撃離脱、重爆迎撃では機関砲の集中運用と正面・背面からの死角突入などが採られました。
これらは機体の推力重量比、翼面荷重、武装配置と弾種(12.7mm機銃、20mm機関砲、機種により40mm機関砲)に強く依存します。
主な陸軍エースパイロットの概要
| パイロット | 推定撃墜数 | 主な機種 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 篠原弘道 | 58 | 九七式戦 | ノモンハンで突出した戦果。上空優位確保からの連続交戦が特徴 |
| 黒江保彦 | 51 | 隼、鍾馗 | 加藤隼戦闘隊の中核。長距離侵攻と柔軟な編隊運用で成果 |
| 穴吹智 | 51(研究推定30前後) | 疾風、五式戦 | バセイン空戦などで高戦果。終盤は本土防空で高速迎撃に従事 |
| 坂川敏雄 | 49以上 | 隼 | 旋回性能に優れる隼で機位取りを優先し確実に加点 |
| 樫出勇 | 33 | 屠龍B | B-29迎撃で知られる。40mm級火力を活かした近距離射撃 |
以上のとおり、陸軍エースは軽快機から重武装機まで任務志向で使い分け、地理条件(山岳・海上・都市部)や敵機の護衛体制に応じてアプローチを変えていました。数値の幅を前提としつつ、人物像・戦域・機体特性を重ねて把握することで、戦果の背景が立体的に見えてきます。
日本軍によるB-29撃墜数

B-29迎撃は陸海軍をあげた最重要任務であり、本土空襲の激化に伴い防空戦力の再編が進みました。総撃墜数は資料により幅があり、百数十機規模との推定がしばしば示されています。
これは、戦闘機による撃墜と高射砲(対空砲火)による撃墜の区別が必ずしも明確でなかったことや、撃破と喪失の定義差、帰還後に不時着やスクラップとなった機体の扱いなどが数値差の原因となっているためです。
迎撃には屠龍、雷電、紫電改、月光、飛燕など多様な機体が投入されました。屠龍では40mm機関砲による一撃必殺を狙い、雷電や紫電改では高高度性能と加速力を活かし、月光では夜間迎撃を担当するなど、それぞれ異なる役割を持ち寄っていました。
また、体当たり攻撃(特攻ではなく防空専用の体当たり戦法)や増槽を投棄しての短時間全力戦闘など、従来の教範を超えた方法が試みられました。
主な迎撃エピソード(抜粋)
| 日付 | 概要 | 地域・補足 |
|---|---|---|
| 1945/1/9 | 体当たりや高射砲でB-29損失が発生 | 東京方面〜サイパン間 |
| 1945/1/27 | 複数機が各地で墜落と記録 | 千葉、茨城、静岡など |
| 1945/3/14 | 大阪市街で撃墜・墜落が確認 | 高射砲の効果が大きい |
| 1945/5/25 | 大規模空襲で多数の撃墜・撃破記録 | 喪失と帰還後大破の区別に注意 |
このように、数字の断定は難しいものの、高高度性能で勝るB-29に対し、日本軍が戦術の工夫と重武装で補おうとした経緯が読み取れます。高度な戦術導入や新機種配備が進む一方、燃料や熟練搭乗員の不足が続いたことが、最終的な防空力に大きな制約を与えました。
(出典:米国立公文書館 米国戦略爆撃調査記録 [USSBS])
有名な日本エースパイロットの戦歴まとめ

主要エースの来歴と強みを横並びで確認すると、個別の撃墜数やエピソードだけでは見えにくい共通点や差異が浮かび上がります。下の表は代表者の戦歴と主力機、撃墜数の目安を整理したものです(数値は資料により幅があります)。
| パイロット | 主な戦域 | 主な機種 | 撃墜数の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 岩本徹三 | 中国、ソロモン、ラバウル | 零戦 | 202(自己申告) | 長期稼働と高戦果 |
| 坂井三郎 | 中国、ソロモン、本土 | 零戦 | 28(公認)/64(自称) | 操縦と統率で象徴的 |
| 菅野直 | 南洋、本土防空 | 紫電改、零戦 | 72(単独48+協同24) | 大型機迎撃戦法 |
| 赤松貞明 | 本土防空ほか | 雷電、零戦 | 30〜40前後(整理) | 生還率と重武装運用 |
| 西澤広義 | 南太平洋 | 零戦 | 86前後 | 短期間で高戦果 |
| 樫出勇 | 本土防空 | 屠龍B | 33 | B-29迎撃で著名 |
| 黒江保彦 | ビルマなど | 隼、鍾馗 | 51 | 指揮と戦果の両立 |
このように、個々の数の比較に偏らず、戦域や機体、任務の違いを合わせて捉えることで妥当な評価軸が見えてきます。撃墜数は単なる記録ではなく、運用環境・戦術・機体性能・編隊運用など複合的な要因の結果であることを理解することが、当時の航空戦力を立体的に把握する鍵となるのです。
撃墜王 ランキング 日本の比較軸

- 戦術・機体別で見た撃墜王の強みランキング
- 日本一の撃墜王は誰ですか?
- 零戦の最強パイロットは誰ですか?
- 日本の最年長パイロットは誰ですか?
- 撃墜王 ランキング 日本の総括
戦術・機体別で見た撃墜王の強みランキング
戦術と機体特性の相性を軸に分析すると、パイロットが発揮した強みが立体的に理解できるようになります。特に第二次世界大戦期の日本軍航空戦においては、限られた性能の中でどう戦術を練り上げ、機体を選び、その特性を最大限に活かすかが勝敗を左右しました。
ここでは「機体適合度」「大型機迎撃力」「前線稼働の持続性」「指揮・育成」という四つの観点で整理し、各エースの特質を比較します。
| 評価観点 | 上位例 | 機体・要素 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 機体適合度 | 岩本徹三 | 零戦×一撃離脱 | 零戦の軽快性・長航続力を活かし、敵戦闘機の死角から接近する一撃離脱を徹底。交戦時間を短くし損耗を低減した |
| 大型機迎撃力 | 菅野直、赤松貞明、樫出勇 | 紫電改、雷電、屠龍B | 重武装と高速度を駆使しB-24やB-29などの大型機を無力化。正面・上方・背面など死角突入法を実践 |
| 前線持続性 | 岩本徹三、坂井三郎 | 零戦 | 長期間の前線稼働と高い生還率を維持。補給制約下で sortie効率を最大化し、損耗率を抑えた |
| 指揮・育成 | 坂井三郎 | 零戦 | 教官・隊運用への貢献。空戦標準化や識別訓練の徹底により、部隊全体の能力を底上げ |
このように、単純な撃墜数の多寡ではなく、どの機体で何を達成したか、どのような環境下で戦果を上げたかという「合目的性」に着目することで、ランキングの解像度が格段に上がります。
例えば紫電改は誉二一型エンジンを搭載し高高度性能に優れていたため大型機迎撃に適し、零戦は航続距離を活かした遊撃や制空に適していました。この「機体特性と任務」の一致がパイロットの強みを最大化したのです。
日本一の撃墜王は誰ですか?

日本一の撃墜王として最も広く挙がるのは岩本徹三です。自己申告202機という規模は群を抜いており、当時の日本軍パイロットとして最大級の戦果を示しています。
もっとも、この数字はあくまで自己申告に基づくものであり、公式換算ではより低い値で整理されることが多いです。これは、当時の記録の残存状況や敵側の損失記録との照合、共同戦果の扱い、帰還後に失われた機体の分類など、複雑な要素が関わっているためです。
岩本はソロモン・ラバウル戦線など長期間の前線投入を経験し、過酷な環境の中でも高い生還率を維持し続けました。彼の戦術は従来の格闘戦に加え、エネルギー戦闘理論を取り入れた一撃離脱戦法、僚機との緻密な連携、無線通信を活かした指揮など、多岐にわたります。
これらにより、単なる個人の撃墜数以上に部隊全体の生存性や戦闘効率の向上に寄与しました。
また、戦術の完成度だけでなく、燃料や整備が限られた環境下で sortieを効率的にこなし続けた点も評価されています。
坂井三郎、菅野直、西澤広義、赤松貞明といった他のエースたちもそれぞれ独自の強みを持ち、撃墜王という概念を「最多数」だけでなく「戦術革新や持続力」の観点から多角的に評価することが、当時の航空戦力を正しく理解する上で重要です。
(出典:米国国立公文書館「USAAF Losses Data」https://catalog.archives.gov/)
零戦の最強パイロットは誰ですか?

零戦に限れば、総合的に岩本徹三が最有力と考えられます。零戦は長航続距離と格闘性能に優れる一方、防弾装備や燃料防漏装置が不十分であり、戦闘中に被弾した際のリスクが極めて高い機体でした。
岩本はこの弱点を補うため、常に高度優位を確保し、太陽位置や敵編隊の死角を利用することで、短時間かつ高確率の攻撃を成功させていました。これにより、交戦時間を短縮し被弾率を大幅に抑え、長期にわたり前線で高い戦果を維持しました。
彼の戦法の特徴は、一撃離脱を基本としながらも状況に応じて柔軟に編隊を再編し、僚機との相互支援を徹底したことです。敵戦闘機に対しては旋回戦を避け、爆撃機に対しては機首下の死角に潜り込むなど、目標と機体特性に応じた戦術選択が際立っていました。
坂井三郎も操縦技量と統率力で高い評価を得ており、零戦エースの象徴的存在といえます。彼は被撃墜リスクを抑えつつ僚機とともに優位を築く手法や、教官として若手に伝えた標準化された空戦手順を確立し、零戦部隊の長期戦闘力を支える基盤を構築しました。
最強の捉え方が撃墜数偏重なのか、生存性や隊運用の完成度を含むのかで結論は揺れますが、零戦運用の完成度という観点では岩本が最有力、象徴性では坂井という整理が自然です。これにより、零戦という機体が本来持つ長所と短所をより深く理解する手がかりが得られます。
日本の最年長パイロットは誰ですか?

日本における最年長パイロットの象徴的存在として広く知られているのが髙橋淳(たかはし じゅん)氏です。
大正11(1922)年10月8日生まれ。東京都出身。
世界最高齢と「ギネス認定」された95歳(2017年当時)の現役パイロット。飛行時間は2万5000時間を超え、周囲からは「飛行機の神様」と崇められていました。
海軍の大型爆撃機(一式陸上攻撃機)操縦士として南方を転戦し、敗戦近くの沖縄戦で特攻隊に編入されたときには“最期”を覚悟したそうです。しかし出撃中、心に誓っていたのは「同乗者は誰も死なせない」という覚悟でした。

彼は第二次世界大戦期に軍の航空隊で飛行経験を積み、その後戦後の航空再建期に民間航空やグライダー分野で長年にわたり活動しました。軍用機から民間機、さらに教育用グライダーまで、時代や用途の異なる多彩な機体を操縦し続けた点が大きな特徴です。
特に注目されるのは、戦後も民間航空会社や地方の航空クラブで指導者として活動し、長期間にわたり飛行技能を維持したことです。これは高齢でありながらも、定期的な身体検査や資格更新を通じて安全基準を満たし続ける必要があるため、極めて稀な事例といえます。
プロパイロットとしてのライセンスを長年保持し、年齢を重ねてもなお現役で飛行を続けたことは、日本の航空界における継続的な貢献として高く評価されています。
また、髙橋氏の経歴は「最年長プロパイロット」という一面だけでなく、航空教育や地域航空文化の普及という側面にも及びます。若年層に対する訓練や安全啓発、グライダー競技や航空祭への協力など、パイロット養成と航空文化の伝承に力を注ぎました。
これにより、単に記録上の長寿飛行というだけでなく、日本の航空技術・文化の継承者という位置付けがなされています。

なお、民間航空における操縦資格は、国土交通省航空局が定める定期審査や医学的適性試験に合格することが前提です。高齢であればこれを維持すること自体が非常に困難であり、その意味でも髙橋氏の実績は突出しています。年齢を超えて現役であり続けたという事実は、体力・判断力・技能維持の総合力を示す証拠といえるでしょう。
2021年12月7日静かに息を引き取られました。
- 2021.12.10 Friday
- 富士川滑空場
- 21:23
- by fly-fujikawa
静岡県航空協会の主任教官を長年して下さったギネス最高齢パイロット教官の
高橋淳教官が12月7日静かに天国に・・・
前日までお元気だった様ですが静かにお亡くなりになったようです・・・
多くのパイロットを育て多くの方がお世話になり航空に多大な貢献をされました
淳さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます~~~
葬儀は菩提寺の東京都港区白金の興善寺で12月10日行われました~
安らかなお顔で天国から皆さんを見守っていると言っている様でした・・・
(出典:国土交通省航空局「航空従事者の医学適性や航空身体検査の証明について」)
撃墜王 ランキング 日本の総括
この記事のポイントをまとめます。
- 陸海軍の代表的エースを数と役割で体系化
- 岩本徹三は長期稼働と戦術完成度で突出
- 坂井三郎は操縦技量と統率で象徴的存在
- 菅野直は紫電改で大型機迎撃の戦法を確立
- 赤松貞明は雷電で重武装を活かし高い生還率
- 陸軍は隼から屠龍まで任務別の機種選択が鍵
- 数値は資料差が大きく推定幅の理解が必要
- 戦域と任務を加味して評価軸を設定すること
- 一撃離脱や高度優位など戦術の適用が勝敗を左右
- B-29迎撃は重武装機と対空砲火の総合戦であった
- エースの価値は撃墜数だけで測れない視点が要点
- 表で機体と戦術を比較すると差異が明確になる
- 零戦の最強は運用完成度で岩本が最有力と整理
- 日本一の撃墜王は岩本だが記録差に留意が必要
- 歴史理解には人と機体と環境の三層把握が有効
最後までお読みいただきありがとうございました。
おすすめ記事:
零戦21型の塗装色を再現する方法|クレオス指定色と剥がれ表現の技法
零戦の展示場所まとめ/実機や復元機を体感できる国内外博物館案内
飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策
プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例