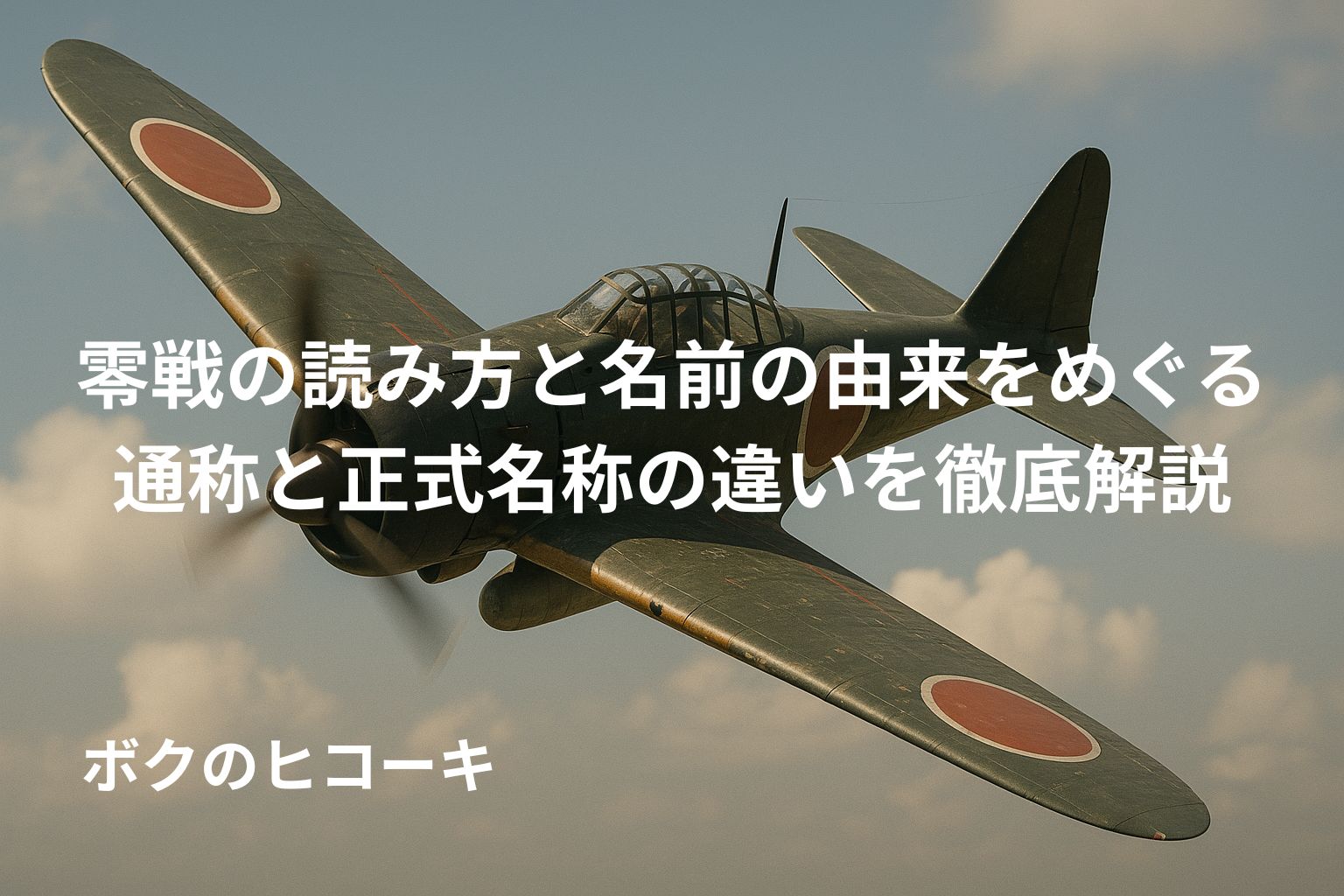太平洋戦争期の象徴である零戦について、零戦の読み方や名前の由来、正式名称、型式一覧までを一気に整理します。
まずゼロ戦とは簡単にどんな機体なのかを押さえ、零戦21型や零戦52型の違い、アメリカでは零戦を何と呼んでいたか?という素朴な疑問、さらに零戦はなぜゼロとつくのかまで丁寧に解説。
加えてゼロ戦に対する海外の反応や特攻に関する歴史的事実にも触れ、検索の目的に沿って要点を網羅します。
- 零戦の読み分けと正式名称の基礎が分かる
- 名称の由来と型式の見方を理解できる
- 21型と52型の違いと戦史的役割を把握できる
- 海外での呼称や評価、特攻との関係を学べる
零戦の読み方と名前の由来についての基本解説

- 零戦の読み方と一般的な呼び方
- 零戦の名前の由来と歴史背景
- 零戦の正式名称とその意味
- ゼロ戦とは?簡単に理解するために
- 零戦の型式一覧と主な特徴
零戦の読み方と一般的な呼び方
零戦の読み方は大きく二通りに整理できます。公的・制度的な読みである「れいせん」と、実務や口語で広まった「ぜろせん」です。
前者は零式艦上戦闘機という正式名称に由来し、漢字の零を漢音で読む運用に沿います。海軍の制式呼称や通達、機体図面などでは、機種名を漢字で表し、その読みを伝統的な読み方に合わせるのが基本でした。したがって、学術書や博物館の正式解説、行政資料に準じた表記では、「れいせん」が基準になります。
一方の「ぜろせん」は、戦中の実際の運用現場と社会的広がりのなかで定着した呼び方です。米軍がZero Fighterと呼称した影響に加え、数字の0や片仮名のゼロを用いた0戦・ゼロ戦という略記が現場メモや新聞・雑誌で用いられ、読みも自然にぜろへ傾きました。
戦時の新聞記事では零戦の語にゼロセンのルビが付される例があり、一般読者に向けて音で理解させる意図が読み取れます。搭乗員や整備員の証言に見られる口頭使用でも、素早い指示伝達や混同回避の観点から、発音しやすく誤認しにくい「ぜろせん」が日常語として機能していました。
現在は両立の姿勢が主流となっています。多くの国語辞典や百科事典では「れいせん」を見出し語に据え、その一方で「ぜろせん(ゼロ戦)」を通称として併記する形が一般的です。
展示の場においても、学術的な解説や史料引用では「れいせん」が用いられる一方、来館者に伝わりやすい導入やキャプションでは「ゼロ戦」という呼称が選ばれる場面が少なくありません。
さらに教育向け資料や子ども向けコンテンツでは、耳になじんだ「ぜろせん」を先に示し、その後に正式名称を添える構成が採られる傾向が見られます。
使い分けの目安をもう少し具体化すると、次のように整理できます。
制度や史料に即して厳密な用語運用が求められる文脈(学術論文、所蔵目録、公式解説)では「れいせん」を基本にし、一般向けの解説や語り口、当時の口語の再現、米軍資料との照合を伴う場面では「ぜろせん」も自然に用いる、という方針です。
表記については、零戦(漢字)・ゼロ戦(片仮名)・0戦(数字)の三様が史料上確認でき、どれも歴史的背景を帯びていますが、現代の日本語記事では可読性と統一の観点から零戦かゼロ戦の二択にまとめるのが無難です。
この語の読みは正誤で裁断するより、目的と読者に応じて選択するのが実践的でしょう。歴史用語としての厳密さを重んじるなら「れいせん」、当時の言語感覚や国際的通称に寄り添うなら「ぜろせん」と。両者の併記は、史実と用法の幅を併せて伝えるうえで有効な手法だと言えます。
零戦の名前の由来と歴史背景

零戦という呼び名の核にあるのは、制式採用年を示す零式です。日本海軍では、兵器が正式採用(制式化)された年を皇紀で表し、その下二桁を式名として付す運用がありました。
1940年は皇紀2600年に当たり、下二桁が00となるため零式とされ、ここに零式艦上戦闘機という正式名称が成立します。式は「その年に制式化された型」であることを明快に示すラベルで、名称だけで年代感が即座に分かるのが狙いでした。
この方式は零戦に限ったものではありません。たとえば九六式艦上戦闘機は1936年(皇紀2596年)採用、九九式艦上爆撃機は1939年(皇紀2599年)採用という具合に、式名を見るだけで年次が読み解けます。
補給・整備・改修の現場では、年度由来の名前が型の代替・互換・在庫の判断を素早くする役割を果たしました。言い換えれば、零式という語は「一つの機種名」であると同時に「運用管理のための年次コード」でもあります。
試作段階の名称と制式名称の関係も整理しておくと理解が深まります。零戦は開発初期に十二試艦上戦闘機と呼ばれました。ここでの十二試は昭和12年(1937年)に試作要求が発せられたことを意味し、「試」は試験用、すなわち制式採用前の段階を示します。
設計の確定と審査を経て、1940年に海軍が正式採用を決定した時点で、十二試艦戦は制式名称の零式艦上戦闘機へと改称され、量産と部隊配備が進みました。試(試作年)と式(採用年)という二つの年次ラベルが連続して使われる仕組みは、日本海軍の航空機命名に特有の特徴です。
社会的背景にも目を向けると、零の字がもつ象徴性が見えてきます。皇紀2600年は当時、国家的な記念年として広く意識され、式典や出版物でも強調されました。
この節目の年に制式化された艦上戦闘機が零式の名を冠したことは、単なる規則運用にとどまらず、時代の空気を反映した出来事でもあります。その後、零式艦上戦闘機は略して零戦と呼ばれるようになり、新聞・雑誌・広報物のなかで一般語として定着しました。
連合軍側がZero Fighterと呼称したことも相まって、国内でもゼロ戦という表記・呼び方が広範に流通し、通称としての存在感を強めていきます。
正式名称の各語が示す中身にも意味があります。艦上戦闘機は航空母艦を運用基盤とする戦闘機という分類を表し、零式は採用年次コード、戦闘機は用途を示します。
これと並行して、工業・軍内部で用いられたA6Mという形式符号(A=艦上戦闘機、6=同分類で六番目、M=三菱)は、製造・改修・調達のための技術的識別子として機能しました。つまり、零式艦上戦闘機(名称)とA6M(符号)は、対外的な呼称と業務上の型番という二つのレイヤーで同一機を指し示しているのです。
以上を踏まえると、零戦の名前は偶然の産物ではなく、規則化された年次命名と試作から制式への移行プロセス、さらには当時の社会的象徴性が重なって成立したことが分かります。
零という語感に引き寄せられがちなこの機体名は、実務と時代精神の両方を映し込んだ、機能的かつ歴史的な名称だったと言えるでしょう。
零戦の正式名称とその意味

零戦の正式名称は零式艦上戦闘機です。この名称には、機体の性格と採用年次、運用環境が順序よく埋め込まれています。すなわち、零式は制式採用の年次コード、艦上は航空母艦を運用基盤とすること、戦闘機は主たる任務が制空・迎撃・護衛であることを示します。
名前そのものが設計思想と配備先、任務の三点を簡潔に伝える仕組みになっているのが特徴です。
名称を構成する要素の意味
- 零式:1940年に制式採用(皇紀2600年)されたことを示す年次コードです。日本海軍は採用年の皇紀下二桁を式名に用いており、00=零となります
- 艦上:航空母艦への搭載を前提とした運用を意味します。着艦フックや低速安定性、収納効率など、艦運用の要件を満たす設計であることを指します
- 戦闘機:敵航空機の撃墜や艦隊・輸送隊の護衛など制空任務を担うカテゴリで、爆撃や偵察と区別されます
この正式名称とは別に、製造・整備・補給の現場で使われた技術的な型番がA6Mです。Aは艦上戦闘機の区分、6は海軍が採用した同区分の第6番機、Mは三菱を表すメーカー記号です。
A6Mという三文字だけで、機体の用途・世代・製造者が即時に共有できるため、図面や補給品の手配、改修指示のやり取りが効率化されました。
実戦配備段階では、これに二一型・五二型といった派生型名が付与され、最初の数字が機体形状の改修順、次の数字が発動機換装の順を示す方式が採られたのです(各桁は「に・いち」のように一桁ずつ読みます)。
連合軍側の呼称は、運用上の識別を簡略化するためのコードネームが使われました。零式艦上戦闘機にはZekeが付与され、無線や報告で短く明確に機種を伝える目的で運用されています。
なお、角ばった翼端をもつA6M3(二一型と外形が異なる初期の改修機)は一時的にHap(のちHamp)と別機種扱いで呼ばれた事例もあります。並行して、英語圏ではZeroあるいはZero Fighterという通称も広まり、国内の略称である零戦(読みはれいせん/ぜろせん)と相互に影響し合いました。
以上のように、零式艦上戦闘機という正式名称は、年次・運用環境・任務という三つの情報を一度に伝えるための実務的な設計であり、A6Mという型式符号やZekeといった対外的識別名と組み合わせて、多層的な識別体系を形成していました。
制度としての命名、現場での整備・補給、戦術通信の三領域が、それぞれの名付けの役割を分担していた点が要点です。
ゼロ戦とは?簡単に理解するために

零戦は、第二次世界大戦期に日本海軍が運用した艦上戦闘機であり、長大な航続距離と卓越した機動性を兼ね備えていました。最大航続距離は増槽を使用した場合で3,000kmを超え、当時の他国の艦上戦闘機を大きく上回る性能だったのです。
武装は20ミリ九九式二号機銃2門を主翼に搭載し、さらに機首には7.7ミリ機銃2門を備えるという構成で、当時の戦闘機としては高火力を誇っていました。これにより、太平洋戦争初期には格闘戦で連合軍機を圧倒し、真珠湾攻撃やフィリピン侵攻作戦などで数多くの戦果を挙げたのです。
しかし、優れた性能を実現するために徹底した軽量化が施され、防弾装甲や自動防漏燃料タンクといった安全装備はほとんど搭載されていませんでした。その結果、敵弾を受けると火災や爆発を起こしやすく、搭乗員の生存性が低いという大きな欠点を抱えていたのです。
戦争後期になると、米軍のF6FヘルキャットやF4Uコルセアといった新鋭機が登場し、速度や防御力、火力の面で優位に立つようになり、零戦は次第に劣勢に追い込まれていきました。
開発は三菱重工業が中心となり、主任設計者は堀越二郎でした。その後、大量生産の必要性から中島飛行機も製造に加わり、戦争末期までに約1万機以上が生産されたと記録されています(出典:国立公文書館アジア歴史資料センター「零式艦上戦闘機関連史料」https://www.jacar.archives.go.jp/)。
この生産数は、日本軍戦闘機の中で最も多いものであり、零戦が日本海軍航空戦力の象徴的存在であったことを示しています。
零戦の型式一覧と主な特徴

零戦は開発から終戦に至るまで改良が繰り返され、多数の型式が存在しました。型式番号のルールとしては、一桁目が機体の主要設計変更回数を示し、二桁目がエンジン換装の回数を示す方式が採用されていました。
この体系により、型式番号を見るだけで基本設計の更新度合いとエンジンの変更状況を把握できる仕組みになっていたのです。
以下の表に、代表的な型式とその特徴を整理します。
| 型式名 | 記号 | 初飛行・配備期 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 十二試艦戦 | A6M1 | 1939年試作 | 試作機段階、基礎設計を確立 |
| 一一型 | A6M2a | 1939年末 | 初期量産型、基本武装を装備 |
| 二一型 | A6M2b | 1940〜41年 | 折りたたみ翼端を採用、航続距離約2,600km |
| 三二型 | A6M3 | 1942年 | 短縮翼で上昇力向上も航続距離は短縮 |
| 二二型 | A6M3 | 1942年秋 | 運用性を改善、燃料搭載量を増加 |
| 五二型 | A6M5 | 1943年以降 | 非折りたたみ翼端、排気推力活用、主力化 |
| 五二型甲/乙/丙 | A6M5a/b/c | 1943〜44年 | 武装や防弾装備を強化、燃料タンクに防火措置 |
| 六三/六二型 | A6M7 | 1945年 | 終盤の改良型、爆装能力や生存性を向上 |
| 六四型 | A6M8 | 1945年試作 | 三菱金星エンジンを搭載した最終案 |
零戦の中でも、二一型は真珠湾攻撃など初期の長距離作戦で主力となり、五二型は中期以降の完成形として最も多く生産されたモデルです。
五二型では最高速度が565km/hに達し、急降下性能の改善や排気管推力の活用による加速力向上が実現しました。また、防御力強化の一環として、パイロット背後に防弾板が追加されるなど、戦況の変化に対応した進化も見られました。
これらの型式改良は、零戦が戦争全期間を通じて第一線で使用され続けた大きな理由でもあります。各型式の違いを理解することで、戦史の中で零戦が果たした役割や、その時代ごとの航空戦の特徴がより鮮明に見えてくるのです。
戦史と評価から見る零戦の読み方と名前の由来

- 零戦21型の性能と活躍
- 零戦52型の改良点と主力化
- 零戦はなぜ「ゼロ」とつくのか?
- アメリカでは零戦を何と呼んでいたか
- ゼロ戦に対する海外の反応と評価
- 特攻での零戦の役割と影響
- 零戦の読み方と名前の由来を総括
零戦21型の性能と活躍
零戦21型は、零式艦上戦闘機の中でも最初に大規模量産された型式であり、日本海軍航空隊の主力戦闘機として太平洋戦争初期の戦局を支えました。当時の艦上戦闘機としては世界的に見ても高水準の性能を備えていた機体です。
- 搭載エンジンと速度性能
中島製の栄12型(空冷星型14気筒)を搭載し、離昇出力は約940馬力です。実用高度約4,500mで最高速度は時速約530kmに達し、当時の艦上戦闘機として高水準でした。 - 航続距離と戦略的価値
落下式増加燃料タンク(増槽)装備時に2,600km超の長距離飛行が可能でした。 - 例:真珠湾攻撃への長距離進出
- 例:フィリピン侵攻作戦など外洋での作戦行動
- 空母運用への適合設計
片翼約50cmの翼端折りたたみ機構により格納庫の収納効率を向上。限られた艦内スペースを前提とした設計思想が反映されています。 - 武装と火力バランス
翼内20mm機銃2門+機首7.7mm機銃2門を装備。F4Fワイルドキャットなど同時期の艦上戦闘機と比べても、総合火力で優位に立てる場面が多くありました。 - 防御面の弱点
防弾ガラスや防漏燃料タンクの採用は限定的で、被弾時の火災・爆発リスクが高い点が弱点でした。軽量化と長航続を優先した設計の代償といえます。 - 操縦性と格闘戦能力
軽快な旋回性と素直な操縦特性を備え、初期の空戦で格闘戦に強みを発揮しました。熟練搭乗員の技量と相まって高い戦果につながりました。 - 外観と識別標識
明灰白色の基本塗装に、部隊ごとの尾翼記号や主翼前縁の黄色識別帯を施しました。戦史資料や各地の博物館展示で当時の塗装・標識が確認できます。
長大な航続力、空母運用への最適化、高い格闘戦能力という長所と、防御の脆弱さという短所を併せ持つ機体であり、太平洋戦争初期の日本海軍航空戦力を象徴する主力型でした。
零戦52型の改良点と主力化

零戦52型は、太平洋戦争中期以降に登場し、零戦シリーズの中で最も多く生産された改良型です。
搭載エンジンと速度性能
- 中島製の栄21型(空冷星型14気筒)を搭載し、離昇出力は約1,130馬力へ向上しました。
- 実用高度約6,000mで最高速度はおおむね565km/h前後を記録し、初期型に比べ高速域の余裕が増しています。
空力設計の改修
- 折りたたみ翼端を廃し、短縮された固定翼端を採用して翼剛性と空力特性を最適化しました。
- 排気管の噴流を推進力に変える排気推力(推力式単排気管)を積極活用し、加速と巡航速度の伸びに寄与しています。
- 補助翼の改修などでロール応答が改善し、格闘戦での姿勢変換が俊敏になりました。
防御と生存性の底上げ
- 操縦席前面に防弾ガラスを導入し、被弾時の致命傷リスクを軽減しました。
- 燃料タンクには火災対策(自動消火装置の採用や防火措置)が段階的に施され、燃焼拡大の抑制が図られました。
武装の構成と強化例
- 基本構成は翼内20mm機銃2門と機首7.7mm機銃2門です。
- 改良型では20mm機銃の給弾をベルト化(125発程度)して持続射撃性を改善した例があります。
- 一部の派生では機首に13.2mm機銃を採用するなど、対重装甲目標への打撃力向上が試みられました。
生産体制と規模
- 三菱と中島の両社で量産され、総数は数千機規模に達しました。
- 終戦期の資源逼迫や空襲下でも生産が継続され、海軍戦闘機戦力の中核を担い続けました。
運用環境の変化への適合
- 航続距離は二一型より短縮しましたが、戦場が島嶼防衛や迎撃中心へ移るにつれ、長距離よりも速度・防御・火力のバランスが重視されました。
- その要請に応える形で、52型は中期以降の主力として実戦運用に適した完成度を示しました。
栄21型による出力増、固定短翼端と排気推力による空力改善、防弾と給弾方式の見直しなどを組み合わせ、零戦52型は初期型の長所を活かしつつ弱点を緩和した実戦的改良型として機能しました。
このように、零戦52型は零戦シリーズの「完成形」とも言える機体であり、太平洋戦争中盤から終盤にかけての日本海軍の主力戦闘機として活躍したのです。
零戦はなぜ「ゼロ」とつくのか?

零戦にゼロという呼称が付いた背景には、日本海軍独自の兵器命名規則があります。海軍では、制式採用年を皇紀で表し、その下二桁を兵器名に冠する慣習がありました。
零式艦上戦闘機が採用された1940年は、皇紀2600年にあたり、その末尾の「00」が「零」と置き換えられたのです。このため、正式名称として「零式艦上戦闘機」と命名されました。
この命名規則は零戦に限らず、九六式艦上戦闘機や九九式艦上爆撃機などにも用いられており、採用年度を即座に判別できるという実務上の利点がありました。零戦という略称は、この正式名称から自然に派生した呼び方であり、軍内部や報道、一般社会で広まっていったのです。
さらに、太平洋戦争中に米軍がこの機体を「Zero Fighter」と呼んだことも、日本国内でゼロ戦という俗称が浸透する要因となりました。もともと零の漢字は「れい」と読むのが一般的ですが、英語の「Zero」の影響によって「ぜろ」と読まれることが普及し、現在でも両方の読み方が併存しています。
つまり、ゼロという言葉は技術的な愛称ではなく、日本海軍の制度的な命名規則に基づく公式名称に由来したものです。その後、戦中・戦後を通じて口語的に広まり、今では歴史的背景とともに理解されるべき呼称となっています。
アメリカでは零戦を何と呼んでいたか
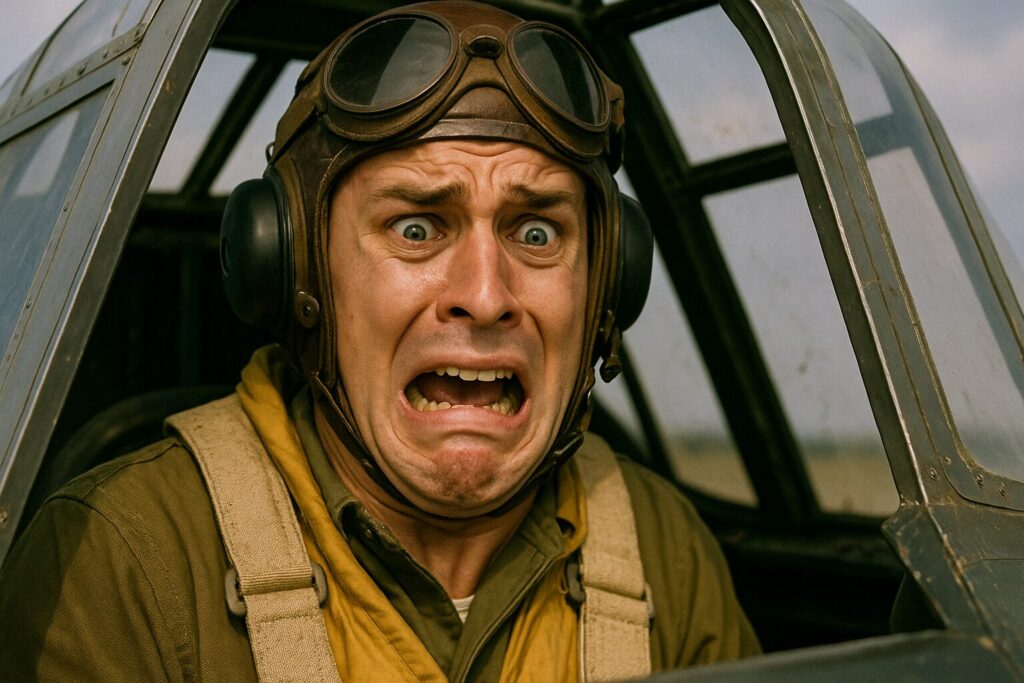
アメリカにおいて零戦は、一般的にZeroあるいはZero Fighterと呼ばれていました。これは、零式艦上戦闘機の「零」という呼称が英語のZeroに置き換えられ、そのまま通称として使われたものです。
公式の連合軍コードネームはZekeであり、これは米軍が日本軍機の識別を容易にするために定めた命名規則に基づくものです。この規則では、戦闘機には男性の名前、爆撃機には女性の名前が与えられることになっており、零戦にはZeke(ジーク)という短く発音しやすい名前が割り当てられました。
さらに、太平洋戦争中にアラスカのアリューシャン列島で不時着した零戦がほぼ無傷の状態で鹵獲され、これが「Akutan Zero」として米軍に解析されました。この機体はアメリカ本土に送られて徹底的に試験飛行と研究が行われ、その飛行特性や弱点が明らかになったのです。
特に旋回性能の高さと引き換えに防御力や急降下性能に難があることが判明し、これが後の対零戦戦術の確立に大きく寄与しました。アメリカでの呼称は、こうした研究や実戦における運用上の利便性を重視した便宜的な名称であり、設計思想や正式名称とは異なる体系に基づいています。
ゼロ戦に対する海外の反応と評価

零戦に対する海外での評価は、時期によって大きく変化しました。太平洋戦争開戦初期、零戦は3,000kmを超える航続距離と卓越した旋回性能を誇り、当時の米海軍F4Fワイルドキャットなどを圧倒。
特に真珠湾攻撃やフィリピン戦線においては、零戦の優位性が顕著に表れ、連合軍側のパイロットにとって未知の脅威として恐れられました。欧米の航空関係誌では「世界で最も優れた艦上戦闘機」と称賛された事例もあります。
しかし、戦局が進むにつれ、その評価は徐々に変化していきました。零戦は軽量化を優先した設計により、防弾装甲や自動防漏燃料タンクを欠いており、敵弾を受けた際の脆弱性が明らかになったのです。
1943年以降、アメリカ軍が投入したF6FヘルキャットやF4Uコルセアは速度・防御・火力の面で零戦を凌駕し、さらに「サッチウィーブ」と呼ばれる対零戦戦法が確立されると、零戦の優位性は急速に失われました。
現代においては、各国の航空博物館で零戦は技術史的に極めて重要な存在として展示されています。その解説は単なる戦闘機としての評価に留まらず、革新的な設計と同時に戦局の推移の中で直面した限界を併せて伝えるものが多く、零戦を航空技術と戦史の交差点に位置づける視点が一般的です。
これにより、零戦は単なる軍用機ではなく、20世紀前半の航空技術の進化を象徴する存在として再評価されています。
特攻での零戦の役割と影響

戦争後期になると、零戦は特攻攻撃の主力機としても投入されるようになりました。背景には、零戦の生産数の多さや整備性の高さに加え、既に最新鋭機に比べて性能面で劣勢となっていた点があったのです。
特攻機として用いられた零戦は、多くの場合、機体の下部に250kg爆弾を搭載し、敵艦船への体当たり攻撃に用いられました。こうした攻撃は通常の航空作戦とは異なり、一度出撃すれば帰還を前提としないものでした。
機体改修の多くは爆弾搭載に関する強化にとどまり、防弾装備や防火構造といった防御面の改善はほとんど行われませんでした。そのため、特攻での生還率は極めて低く、多大な人的損失を伴いました。
一方で、特攻攻撃は米艦隊に対して局地的な損害を与え、心理的な衝撃をもたらしたのも事実です。特に沖縄戦では、多数の特攻機が投入され、米軍の上陸作戦に一定の影響を与えました。
しかしながら、戦略的に見れば特攻は持続的な優位をもたらす戦術ではなく、日本の航空戦力や工業生産力が限界に達していたことを示す行動でした。
歴史研究では、零戦が特攻に使われた事実は、戦争末期の切迫した状況と人的資源を重視した戦術の転換を象徴するものとされています。そのため、零戦は航空史において華々しい初期の戦果とともに、戦争末期の悲惨な側面とも不可分の存在として語られ続けているのです。
参考資料:©鹿児島県 公益社団法人鹿児島県観光連盟
零戦の読み方と名前の由来を総括
この記事のポイントをまとめます。
- 「れいせん」と「ぜろせん」の二通りの読みが併存
- 公式文書は「れいせん」が基本で俗称に「ぜろせん」
- 零式は皇紀2600年採用の命名規則に基づく
- 正式名称は零式艦上戦闘機で略称が零戦
- A6Mの符号はメーカーと機種系列を示す
- ゼロ戦は長航続と機動性に優れた艦上戦闘機
- 型式は機体改修とエンジン換装の組合せ表記
- 二一型は折りたたみ翼端と遠距離作戦が強み
- 五二型は短縮翼と排気推力で高速域を改善
- 海外ではZeroやZekeと呼称され識別に使用
- 初期は性能が高評価も後期は弱点が顕在化
- 特攻では爆装改修で投入も損耗が非常に大きい
- 読み方は媒体や文脈に応じた使い分けが妥当
- 名前の由来は制度的背景で理解が深まる
- 型式一覧を把握すると戦史の流れが見通せる
最後までお読みいただきありがとうございました。
おすすめ記事:
飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策
【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説
三菱重工 戦闘機工場の全貌と歴史|名古屋拠点と各工場の役割を解説
プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例
【第五世代戦闘機】トップガンの敵機はSu-57?描写の裏側を徹底解説