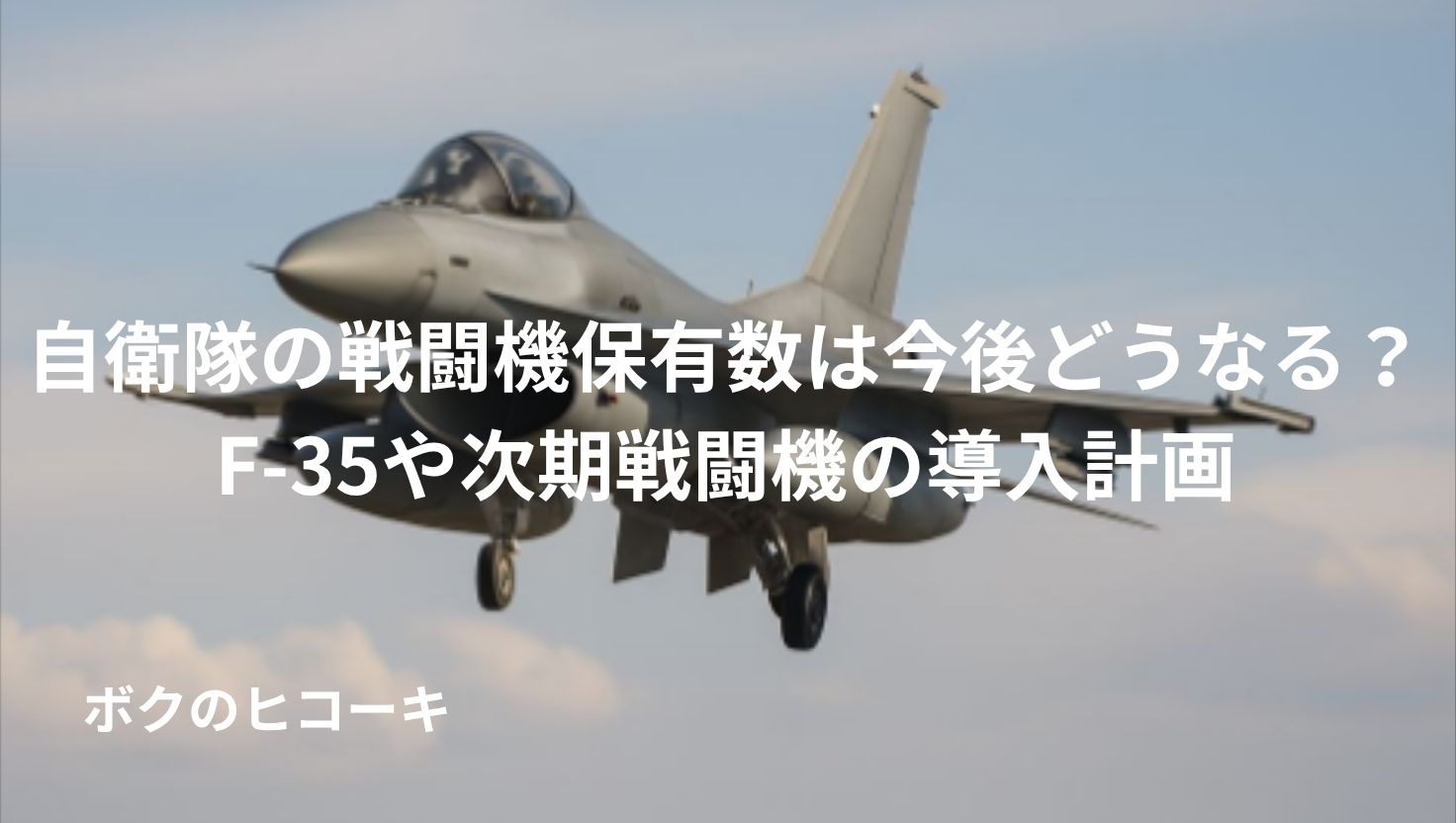日本の防空体制を理解するうえで、自衛隊の戦闘機保有数は重要な指標の一つです。特に、現在配備されているF-35の保有数や、今後の導入計画に注目が集まっています。この記事では、F-35保有数の現状だけでなく、F-16保有数がゼロである理由、各国のF-35保有数との比較などについても詳しく解説します。
また、航空自衛隊の戦闘機一覧や歴代機種の変遷、さらには航空自衛隊戦闘機の配備基地についても触れていきます。小松基地の戦闘機配備数や、今後の配備計画も含めて整理していますので、現在の戦力バランスを把握したい方には参考になるでしょう。
加えて、海上自衛隊の航空機保有数や、対潜哨戒の主力であるP-1の保有機数など、空自以外の航空戦力についても網羅しています。日本の防衛力を総合的に知るために、本記事をぜひ最後までご覧ください。
- 自衛隊が現在保有している戦闘機の種類とその機数
- F-35やF-2など各機種の配備状況と今後の導入計画
- 戦闘機の配備基地や基地ごとの配備バランス
- 他国とのF-35保有数の比較と日本の戦略的な位置づけ
【自衛隊の戦闘機保有数】現状と推移

- 日本は現在何機の戦闘機を保有していますか?
- 自衛隊のF35保有数は今後どうなる?
- 自衛隊のF16保有数はゼロ!その理由とは?
- 航空自衛隊の戦闘機 一覧と主力機種の特徴
- 航空自衛隊の戦闘機、歴代の機種と配備の歴史
日本は現在何機の戦闘機を保有していますか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総保有数(公式) | 約260機(防衛省公表値) |
| F-15の保有数 | 約200機(うち訓練・開発用も含む) |
| F-2の保有数 | 約91機 |
| F-35の保有数 | 39機(2025年3月末時点) |
| 単純合計 | 約330機(重複含む場合あり) |
| 数値のズレの要因 | 重複集計の有無、訓練・試験機の扱い |
| 運用可能数との違い | 整備中・退役予定機を含むため差が出る |
| 教導機や試験機 | 戦闘部隊とは別に存在する |
| 実働機数 | 即応可能な機体のみカウントすると減る |
| 配備のバランス | 地域や基地ごとの分散が必要 |
| 戦闘機の性能 | 機数よりも質が重要視される場面も多い |
| 整備体制の重要性 | 稼働率を左右する要因として重要 |
| 保有数の理解 | 数はあくまで目安で、背景理解が必要 |
日本が現在保有している戦闘機の数は、おおよそ260機とされています。これは防衛省が公式に発表している「戦闘機:約260機」という表記に基づいた数値です。ただし、配備機種や報道資料によっては、F-15が約200機、F-2が約91機、F-35が39機(2025年3月末時点)とされており、単純合計すると約330機になる場合もあります。
このような数値のズレが生じる背景には、重複集計の有無や、教導機・試験機などを含めるかどうかといった集計基準の違いがあります。
例えば、同じF-15でも、通常配備の戦闘部隊に加えて、訓練用や技術開発用途で使われている機体も存在します。そのため、「運用可能な戦闘機数」と「保有総数」ではやや数字に差が出てしまうのです。
また、退役を控えた機体や、整備中で飛行不能な機体なども一定数含まれることがあります。これらの機体は配備台帳上は存在していても、即応できる戦力としてカウントされない場合があるため、現場での実働機数とは異なる可能性があります。
このように、日本の戦闘機保有数は約260機とされていますが、実際には運用状況や任務内容によって変動があるため、あくまで「目安」としての理解が求められます。重要なのはその数だけでなく、配備のバランスや戦闘機の性能、維持整備体制の充実度も含めて全体を評価することです。
自衛隊のF35保有数は今後どうなる?

自衛隊が今後保有するF-35の機数は、最終的に147機になる予定です。これはF-35Aを105機、F-35Bを42機導入するという政府の調達計画に基づいたもので、日本はアメリカに次いで世界第2位のF-35保有国になる可能性があります。
まず、F-35Aについては既に39機が配備済みで、三沢基地や小松基地などに順次展開されています。F-35Bについては、2025年8月から宮崎県の新田原基地に初期配備が開始され、今後さらに増強される予定です。
ただし、ソフトウェア開発の遅延や国際的な生産調整の影響で、配備スケジュールが一部変更された事例も報告されています。
F-35をこれだけ大規模に導入する理由は、防空能力の強化だけでなく、老朽化したF-4やF-2などの機種を段階的に置き換える目的があります。特にF-35は第5世代戦闘機としてステルス性能や情報収集能力が高く、多様な任務に対応できることが大きな強みです。
今後の戦闘は単独行動よりもネットワーク連携やセンサー統合が重要になるため、F-35の導入は戦術の根幹にも関わる改革といえるでしょう。
ただし、運用には注意点もあります。F-35は非常に複雑なシステムで構成されており、維持管理には高い技術力とコストが求められることです。
特にエンジンや補用部品の供給遅れ、ソフトウェアの更新対応などが稼働率に影響する可能性が指摘されています。また、機密性が高いため、運用に関する情報が十分に日本側に提供されないという課題もあります。
このように、自衛隊のF-35保有数は今後も増加していきますが、単なる数の拡大だけでなく、運用体制や整備基盤の充実が成功の鍵となるのです。
自衛隊のF16保有数はゼロ!その理由とは?

現在、自衛隊がF-16戦闘機を1機も保有していないという点は、航空戦力に詳しくない方には少々意外に感じられるかもしれません。しかし、これは単にアメリカ製のF-16を導入しなかったという話ではなく、日本独自の戦略と開発方針に基づいた明確な選択によるものです。
F-16を直接導入せず、代わりに開発されたのが国産戦闘機「F-2」です。F-2はF-16をベースにして日米共同開発された戦闘機で、主に日本の防衛ニーズに合わせて設計されました。例えば、F-2は大型の主翼を持ち、複合素材を多用することで長距離航続や高い対艦攻撃能力を実現しています。
このように、F-16とは設計思想こそ共通していても、運用目的や性能面では大きく異なる機体なのです。
こうした選択の背景には、防衛装備の国産化や自立性の確保という日本の長期的な防衛政策があります。F-16をそのまま導入するよりも、日本の技術力を生かしながら国産機の開発力を維持・強化したいという意図がありました。
また、アメリカ製機体に完全依存すると、部品調達や運用情報の制限などで不利になる場面も少なくありません。
一方で、日本国内でF-16を目にする機会が全くないわけではありません。実際、在日米軍基地にはアメリカ空軍のF-16が多数配備されており、訓練や警戒任務で頻繁に飛行しています。ただし、これらの機体はあくまで米軍の装備であり、自衛隊が所有・運用しているわけではありません。
結果として、自衛隊のF-16保有数は「ゼロ」である一方、F-2がその役割を実質的に担っており、運用上のギャップは発生していません。むしろ、日本独自の運用環境や防衛方針に合った戦闘機選定がなされているといえるでしょう。
航空自衛隊の戦闘機 一覧と主力機種の特徴

| 戦闘機の種類 | 主な特徴・役割 | 配備・運用状況 |
|---|---|---|
| F-35A | 第5世代のステルス戦闘機。情報収集・対空・対地・電子戦に対応 | 三沢基地、小松基地などに配備中。今後の主力機 |
| F-35B | 短距離離陸・垂直着陸が可能なSTOVL型。島嶼部での運用に強み | 2025年より新田原基地で配備開始予定 |
| F-15J/DJ | 長年主力の制空戦闘機。マッハ2.5、近代化改修で電子戦能力も強化 | 全国各地に配備。領空侵犯対応などで即応出動 |
| F-2A/B | F-16ベースの国産戦闘機。対艦・対地攻撃に特化した設計 | 国内各基地に配備。海上防衛任務で活躍中 |
航空自衛隊が現在運用している主な戦闘機は、F-35A、F-35B、F-15J/DJ、F-2A/Bの4種類です。それぞれに異なる役割と性能があり、日本の防空体制において重要な役割を担っています。
まず注目すべきはF-35Aです。第5世代ステルス戦闘機であり、高度な情報収集能力とステルス性能を兼ね備えています。現在は三沢基地や小松基地などに配備が進められ、将来的には航空自衛隊の主力になると見られています。マルチロール機として、対空戦・対地攻撃・電子戦と幅広い任務に対応可能です。
続いてF-15J/DJは、長年にわたり空自の主力制空戦闘機として運用されてきた機体です。最高速度マッハ2.5という高性能に加え、近年では電子戦能力を強化する近代化改修も進んでいます。主に対空戦闘任務に特化し、領空侵犯への即応出動などで活躍しています。
F-2A/Bは、日本とアメリカが共同で開発した国産戦闘機で、F-16をベースに大幅な性能向上が図られています。特に対艦・対地攻撃能力に優れ、海上防衛を重視する日本の防衛方針にマッチした設計です。炭素複合素材を使用した大型主翼など、日本独自の要素も多く採用されています。
そして2025年からは、F-35Bの配備が始まっています。こちらは短距離離陸・垂直着陸(STOVL)能力を持つタイプで、新田原基地を中心に配備される予定です。空母のような艦艇や滑走路の短い離島での運用も想定されており、南西諸島などの防衛強化に貢献すると期待されています。
このように、航空自衛隊の戦闘機は用途別に最適化された構成となっており、制空・対艦・情報収集と多岐にわたる任務をカバーしています。配備数の多いF-15Jを軸に、新型のF-35シリーズへと主力がシフトしつつあるのが現状です。
参考資料:航空自衛隊公式サイト
航空自衛隊の戦闘機、歴代の機種と配備の歴史

| 導入年代 | 戦闘機名 | 特徴と役割 |
|---|---|---|
| 1950年代 | F-86セイバー | 日本初のジェット戦闘機。防空能力の基盤を構築 |
| 1960年代 | F-104Jスターファイター | マッハ2超の高速性能。迎撃専用だが運用難易度が高かった |
| 1970年代 | F-4EJファントムⅡ | 多用途で長寿命。偵察型や教導機としても活用 |
| 1980年代 | F-15J | 高信頼の制空戦闘機。現在も主力として運用中 |
| 2000年代 | F-2 | F-16ベースの国産戦闘機。対艦攻撃に特化 |
| 2010年代~ | F-35A / F-35B | 第5世代ステルス機。多任務対応・F-35Bは2025年配備予定 |
| 2035年以降(予定) | 次期戦闘機(F-X) | 第6世代機。日英伊共同開発、AIや無人機連携を想定 |
航空自衛隊の戦闘機の歴史は、1950年代に遡ります。戦後に新設された空自が最初に導入した本格的な戦闘機は、アメリカ製のF-86セイバーでした。これが日本にとって最初のジェット戦闘機となり、防空能力の基盤を築きました。
次に1960年代には、F-104Jスターファイターが配備されました。この機体はマッハ2を超える高速性能を持ち、迎撃任務に特化した機体として運用されました。ただし運用が難しく、事故も少なくなかったことから、後継機への更新が急がれました。
1970年代にはF-4EJファントムⅡが登場します。全天候型の双発機で、多用途な運用が可能でした。日本ではライセンス生産され、延命改修を受けつつ長期間にわたり第一線で活躍。偵察型や教導用にも活用され、2021年まで運用が続けられた息の長い機体でした。
1980年代からはF-15Jが導入され、日本の空を守る制空戦闘機として定着します。この機体は現在でも主力のひとつであり、近代化改修により今もなおアップグレードされ続けています。設計の堅牢さや高い信頼性から、40年以上にわたる長期運用が可能となりました。
2000年代には国産機F-2が配備され、F-16をベースとしつつも大型化・高性能化が図られました。特に対艦ミサイル搭載能力に優れ、日本独自の防衛戦略に沿った運用が可能です。
そして2010年代後半以降は、最新のF-35シリーズが導入され始めました。F-35Aは2016年から本格運用が開始され、F-35Bも2025年に配備が始まるなど、戦闘機体系は「第5世代」へと移行しています。
このように、航空自衛隊の戦闘機は時代ごとの技術と戦略の変化に応じて進化してきました。各世代で必要とされる性能や任務が異なり、それに応じた導入と更新が繰り返されています。次期戦闘機(第6世代)の配備が予定されている2035年以降も、こうした流れは続く見込みです。
【最新の自衛隊戦闘機】保有数まとめ
- 航空自衛隊の戦闘機、配備基地と配備状況
- 小松基地の戦闘機、配備数と今後の計画
- F35保有数、各国比較と日本の位置づけ
- 海上自衛隊の航空機、保有数とその役割
- P-1の保有機数は?海上監視の要となる存在
- 次期戦闘機の導入と今後の保有数の見通し
航空自衛隊の戦闘機、配備基地と配備状況

| 基地名 | 所在地 | 主な配備機種 | 特徴・役割 |
|---|---|---|---|
| 三沢基地 | 青森県 | F-35A | 初期配備基地。第302飛行隊が情報収集・制空任務を担当 |
| 小松基地 | 石川県 | F-35A、F-15J | 今後F-35Aの主力配備地に。2030年代には約20機体制 |
| 新田原基地 | 宮崎県 | F-35B(予定) | 2025年8月から配備開始。不整地運用にも対応 |
| 那覇基地 | 沖縄県 | F-15J | 南西空域の即応体制を担う戦略拠点 |
| 築城基地 | 福岡県 | F-2 | 西日本エリアの防衛に対応 |
| 百里基地 | 茨城県 | F-2、F-15DJ | 訓練・即応部隊を兼ねた関東の防衛拠点 |
| 名古屋飛行場 | 愛知県 | F-15(試験機など) | 整備・試験・技術開発の拠点として機能 |
航空自衛隊は日本全土に複数の戦闘機配備基地を持ち、地域の防衛バランスや地政学的リスクを考慮しながら戦力を分散させています。主な戦闘機基地は、三沢、小松、新田原、那覇、築城、百里などで、それぞれ異なる機種や部隊が運用されています。
まず、青森県の三沢基地はF-35Aの初期配備地として知られています。ここでは第302飛行隊がF-35Aを運用しており、ステルス性能を活かした高高度情報収集や制空任務を担います。F-35Aは今後も三沢を中心に展開予定で、全国的な主力機への移行が進められている機体です。
次に、石川県の小松基地もF-35Aの配備先として注目されています。当初、三沢基地で受け入れる予定だったF-35Aの一部は、ソフトウェア開発の遅延によって配備先が小松に変更されました。これにより、小松では今後さらにF-35Aの配備数が増え、2030年代には20機規模になると見込まれています。
一方、九州の新田原基地には2025年8月からF-35B(短距離離陸・垂直着陸型)が配備される予定です。この基地は南西諸島の防衛ラインに近く、F-35Bの特徴を活かして不整地や滑走路の短い地域での展開力強化が期待されています。
沖縄の那覇基地にはF-15J戦闘機が配備されており、南西空域における即応体制を支える重要な拠点です。この基地は近年、対中国を意識した空自の防衛強化策の一環として、装備や人員の増強が続いています。
その他にも、築城基地(福岡県)、百里基地(茨城県)、名古屋飛行場(愛知県)などにも戦闘機が配備されており、全国に12の飛行隊が配置されています。これにより、日本全土の防空体制を柔軟かつ迅速に支える運用が可能となっているのです。
小松基地の戦闘機、配備数と今後の計画

小松基地は北陸地方に位置する航空自衛隊の中核基地の一つであり、日本海側の防空任務を担う重要な拠点です。かつては主にF-15Jが中心となって防空任務を担当していましたが、現在はF-35Aの配備が本格的に進められています。
2024年度中に三沢基地へ配備予定だったF-35Aの一部が、搭載ソフトウェアの開発遅延によって小松基地へ配備先を変更された経緯があります。結果的に、今後数年で小松基地には最大20機のF-35Aが配備される予定であり、これは日本国内でも大規模なF-35A部隊となる見込みです。
こうしたF-35Aの展開は、旧来のF-15Jからの機種更新を意味します。現在、小松基地には依然としてF-15Jが多数配備されていますが、これらは段階的に退役または他基地への移動が進められると考えられています。F-15Jの一部は近代化改修が施されていますが、F-35の導入に伴い、旧型機の縮小は避けられません。
小松基地は航空自衛隊と民間航空(小松空港)が共用する基地であり、運用には騒音対策や空域管理などの課題もあります。F-35は最新鋭の戦闘機である一方で、エンジン出力が大きく、騒音も懸念されているため、周辺住民への説明や運用調整が引き続き重要です。
将来的には、小松基地が日本海側のF-35運用拠点として確立されることで、対北朝鮮・対ロシアといった複数の脅威に対応できる体制が整うと見られています。小松基地の機能強化は、北陸地方だけでなく全国的な航空防衛バランスの中でも重要な意味を持っているのです。
F35保有数、各国比較と日本の位置づけ

| 国名 | F-35導入予定数 | 主な配備機種 | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 約2,443機 | F-35A/B/C | 最大保有国。空軍・海軍・海兵隊で展開、共同開発国 |
| 日本 | 147機(A:105機、B:42機) | F-35A/B | 世界第2位の保有予定。新田原や三沢、小松などに配備 |
| イギリス | 138機 | F-35B | 艦載機として導入。空母「クイーン・エリザベス」に搭載 |
| イタリア | 約90機 | F-35A/B | 国内で最終組立ラインを保有 |
| オーストラリア | 約72機 | F-35A | アジア太平洋地域で早期導入を進行 |
| 韓国 | 60機以上 | F-35A | 北朝鮮への抑止力強化が目的。追加導入を検討中 |
F-35戦闘機は、世界中の先進国で導入が進められている第5世代ステルス機です。その中で、日本は今後の導入計画を含めると世界第2位の保有数になると見られています。これは非常に大きな戦略的転換であり、日本の航空戦力の中核がF-35シリーズになることを意味します。
まず、最大の保有国はアメリカで、最終的には約2,443機を配備予定とされています。すでに1,000機以上が実戦部隊で運用されており、空軍・海軍・海兵隊で異なるF-35型(A/B/C)が展開。アメリカはF-35の共同開発国でもあり、その運用規模は他国を大きく引き離しています。
これに次ぐのが日本です。日本はF-35Aを105機、F-35Bを42機、合計147機を導入する計画です。2025年3月末時点でF-35Aは39機が配備済みで、今後も各地で配備が拡大されていきます。F-35Bも2025年に新田原基地での運用が始まるなど、既に導入が進んでいます。
他の国を見ると、イギリスはF-35Bを主に艦載機として導入し、最終的に138機を計画。イタリア、オーストラリア、韓国なども数十機単位で導入を進めていますが、日本のように100機を超える国は非常に限られています。
このような状況から、日本のF-35保有は量的にも質的にも非常に高い位置にあると言えるでしょう。
ただし、F-35の運用には多くの課題も伴います。維持費はF-35Aで年間約8億円前後、F-35Bに至っては13億円以上とされ、コスト面の負担は大きいからです。また、米国の技術依存が強く、整備や情報アクセスに制限があるという問題もあります。
それでも、F-35を大量導入することで日本は空中戦力の質を大きく引き上げています。将来的にF-15やF-2の老朽化が進む中で、F-35が主力となることで新たな時代の防空体制の形成は不可欠です。各国との比較においても、日本のF-35戦略は「防衛力強化の象徴」として注目されています。
海上自衛隊の航空機、保有数とその役割

| 機種名 | 主な用途 | 配備数の目安 | 特徴・役割 |
|---|---|---|---|
| P-1哨戒機 | 対潜哨戒 | 約30機 | 国産最新鋭。潜水艦探知・追尾・攻撃に対応 |
| P-3Cオライオン | 対潜哨戒 | 約70機 | 長年運用される主力機。P-1への置き換え進行中 |
| SH-60Kヘリコプター | 艦載・対潜・救難 | 多数 | 護衛艦搭載型。多目的運用で即応力を発揮 |
| 輸送・連絡機 | 人員・物資輸送、支援活動 | 複数 | 災害派遣にも対応。海自の支援任務を担う |
| ※合計保有数は約210機(2024年時点)。戦闘機は含まれず、海洋防衛・監視・救難に特化した構成。 | |||
海上自衛隊の航空機保有数は、2024年時点で約210機とされています。これらは戦闘機ではなく、主に対潜哨戒、警戒監視、輸送、救難といった海洋防衛や支援任務に特化した機体で構成されています。
中でも中心的な存在が対潜哨戒機です。海自は国産のP-1哨戒機と、長年運用されてきたP-3Cオライオンの2機種を保有しており、両機を合わせて100機前後が配備されています。これらの航空機は、海中に潜む潜水艦をソナーやセンサーで探知し、必要に応じて攻撃も可能なため、日本の海上防衛において欠かせない存在です。
加えて、SH-60Kと呼ばれる艦載型ヘリコプターも多数配備。この機体は護衛艦に搭載され、対潜水艦戦、捜索救難、情報収集などの多目的任務に活用されます。空からの即応力を持つことで、海上自衛隊の艦隊運用に柔軟性をもたらしているのです。
また、輸送・連絡用の航空機も複数機保有。これらは隊員や装備の輸送、災害派遣時の支援などにも使用され、軍事的用途にとどまらない広い役割を果たしています。
これにより、海上自衛隊の航空部隊は単なる補助戦力ではなく、日本周辺の広大な海域に対して高度な監視能力と即応性を提供する「目」と「耳」として機能しています。艦艇単独では対応しきれない距離や範囲を、航空機の機動力で補う体制が確立されているのです。
参考資料:海上自衛隊公式サイト
P-1の保有機数は?海上監視の要となる存在

P-1は日本が独自に開発した最新の対潜哨戒機であり、2025年時点での保有数は33機とされています。これは防衛省の公表資料や予算資料に基づいた数字であり、今後もさらに配備が進む見通しです。
このP-1は、旧式のP-3C哨戒機の後継として設計された機体です。航続距離、搭載センサー、静粛性、耐久性のすべてにおいて進化しており、日本周辺の広大な海域を長時間監視する能力に優れています。
特に、国産のHPS-106アクティブフェーズドアレイ(AESA)レーダーや、高度な磁気探知装置(MAD)を装備している点は大きな特長です。
このように言うと、「最新鋭の装備で探知すれば終わりでは?」と思われるかもしれません。しかし、実際の海中監視任務では、複数のセンサーを組み合わせ、広範囲の海域に対して長時間滞空しながら細かく探索する作業が求められます。
P-1はそれを可能にする性能を備えており、既存のP-3Cよりも効率的かつ精度の高い運用が実現できるのです。
もちろん、導入当初は整備コストや運用経験の蓄積など課題もありました。ただ、今では訓練体制も整い、配備部隊は徐々にP-3CからP-1への置き換えを完了させつつあります。
P-1の役割は単なる対潜哨戒にとどまりません。対艦攻撃、電子戦、災害時の情報収集などにも対応できる拡張性を持っており、今後はより多様な任務で活用されていく可能性があります。すでにP-1は自衛隊の演習や国際共同訓練でも実績を積んでおり、その存在感は年々高まっています。
次期戦闘機の導入と今後の保有数の見通し

航空自衛隊では、F-15やF-2といった現行機の老朽化を受けて、次期戦闘機(仮称:F-X)の導入が進められています。この新型戦闘機は、日本とイギリス、イタリアの3カ国が共同で開発中の「GCAP(Global Combat Air Programme)」の一環として2035年頃の配備開始を目指しています。
F-Xは第6世代戦闘機と位置付けられており、従来の戦闘機に比べて人工知能による自律飛行、無人機との編隊飛行、極超音速兵器への対応といった高度な機能を備える予定です。また、電子戦能力やセンサー融合技術なども強化され、空中戦だけでなく広範な任務への適応が期待されています。
こうして導入されるF-Xは、最終的に約100機規模が見込まれています。これは現行のF-2(約91機)を置き換える目的もあり、単なる「新しい機体の追加」ではなく、全体の保有機構成を再構築するプロジェクトでもあるのです。
今後、F-15の老朽化に伴う削減や、F-35との連携運用を考慮した機数調整も進められると考えられています。
ただし、F-Xの配備には長期的な開発計画と大規模な予算が必要です。エンジン、電子機器、機体設計といったすべての要素で高い技術力が求められるため、納期の遅延やコスト超過といった課題も避けられません。さらに、共同開発国との調整や、国内産業との連携体制の構築も重要なステップとなります。
このような状況から、次期戦闘機の保有数は「今ある戦闘機をどう置き換えるか」「F-35との役割分担をどうするか」によって柔軟に調整されていくと見られます。航空自衛隊の戦力は単なる「数」ではなく、「質」や「即応性」にも焦点を当てた変革期に差しかかっているのです。
【自衛隊の戦闘機保有数】概要と今後の展望
この記事のポイントをまとめます。
- 日本の戦闘機保有数は約260機とされるが集計方法で差異がある
- 実動可能な機数と保有機数は必ずしも一致しない
- F-35Aはすでに39機が配備済みで、今後も増加予定
- F-35Bは新田原基地に2025年から配備が開始される
- F-35シリーズは最終的に147機の導入が計画されている
- 自衛隊はF-16を保有せず、代替としてF-2を開発・配備している
- F-2はF-16をベースに日本仕様で改良された国産機である
- 主力戦闘機はF-15J/DJ、F-2、F-35A/Bの4機種が中心
- 各戦闘機には制空、対艦、ステルスなど異なる特性がある
- 戦闘機は三沢、小松、新田原、那覇など全国の基地に分散配備されている
- 小松基地ではF-15JからF-35Aへの更新が進行中
- F-35保有数では日本はアメリカに次いで世界第2位となる見込み
- 海上自衛隊は約210機の航空機を保有し、対潜哨戒が主な任務
- 国産のP-1哨戒機は33機が導入され、P-3Cからの置き換えが進行中
- 次期戦闘機F-Xは2035年頃の配備を予定し、100機規模が見込まれている
最後までお読みいただきありがとうございました。
おすすめ記事:
飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策
【ケムトレイルと飛行機雲】見分け方と科学的根拠をわかりやすく解説
ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説
プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例