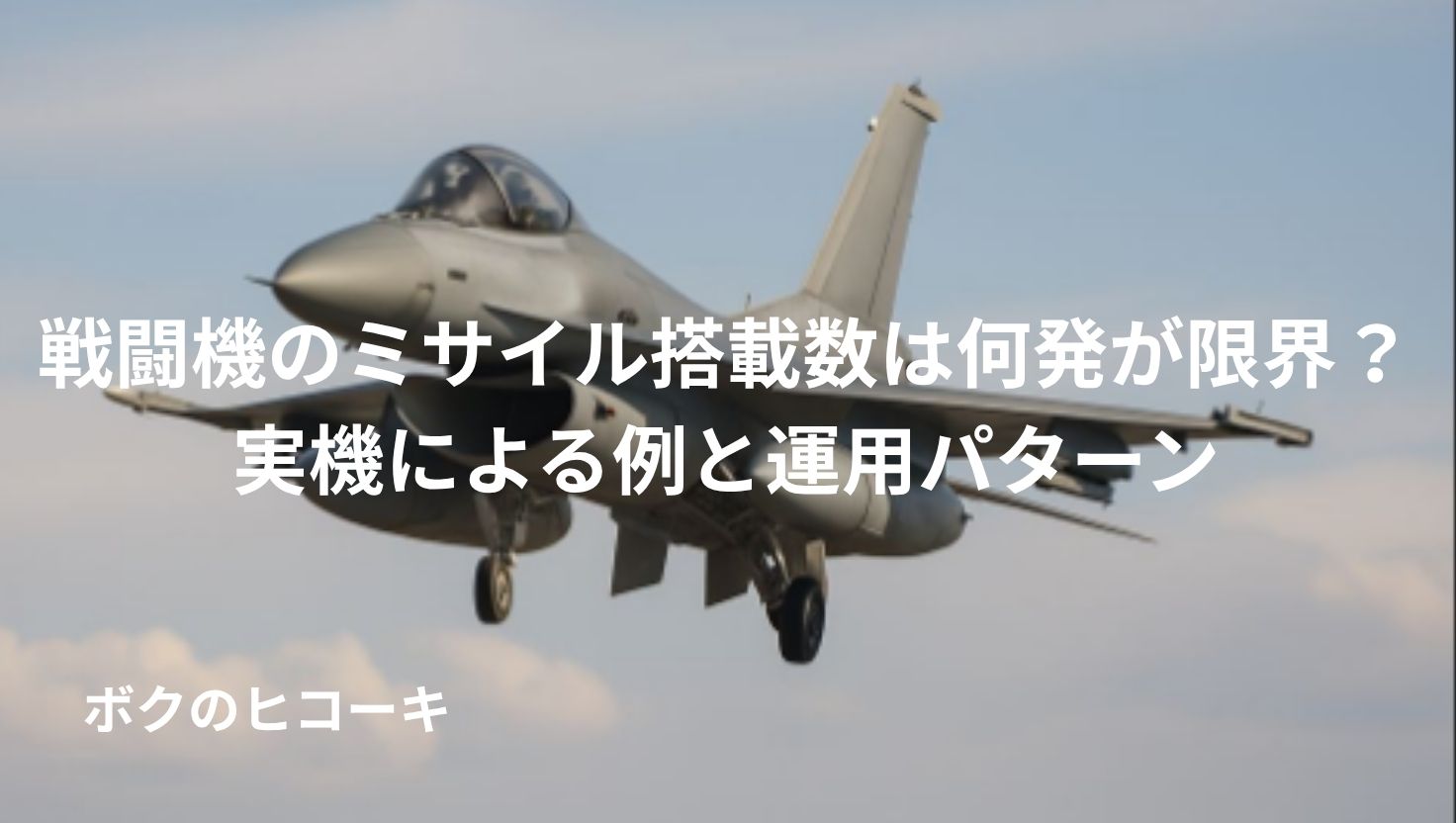現代の空中戦において、戦闘機の性能を語る上で「ミサイル搭載数」は欠かせない要素の一つです。特に、F18戦闘機やF-35、F-22、F-2、F-15といった各国の主力機は、それぞれ異なる設計思想と運用戦術によって、搭載可能なミサイルの数や種類に大きな違いがあります。
この記事では、戦闘機のミサイル搭載数というテーマを軸に、各機種が実際にどの程度の兵装を搭載できるのか、どのような運用がされているのかを詳しく解説していきます。
また、最強の空対空ミサイルは?という疑問や、AIM-9サイドワインダーは1機いくらか、空対空ミサイルの速さはどれほどなのかといった、気になる情報にも触れていきましょう。
さらに、ゲーム「エースコンバット」のように大量のミサイルを装備する演出は現実とどう違うのか、その背景もご紹介します。初めて戦闘機に興味を持った方にもわかりやすく、専門的になりすぎない形で構成していますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 各戦闘機ごとのミサイル搭載数とその違い
- 実戦でのミサイル運用例と制約
- 搭載数とステルス性や機動性の関係
- 空対空ミサイルの価格や性能に関する基礎知識
現代戦闘機におけるミサイル搭載数の実情とは

- F18戦闘機のミサイル 搭載数と実戦搭載例
- F-35戦闘機のミサイル搭載数と運用モード
- F-22戦闘機に搭載できるミサイルの数
- F-2戦闘機はミサイルを何発搭載できる?
- F-15戦闘機はミサイルを何発搭載できるのか
F18戦闘機のミサイル 搭載数と実戦搭載例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用国 | 主にアメリカ海軍 |
| 最大搭載数(理論値) | AIM-120 ×10発、AIM-9 ×2発の合計12発 |
| ハードポイント数 | 合計11基(2連装ランチャー併用) |
| 実戦搭載例 | AIM-120 ×5発、AIM-9 ×4発の合計9発(2024〜2025年紅海) |
| 運用上の制限 | 機動性・燃費・航続距離への悪影響 |
| 実戦での現実的な搭載数 | 8〜9発程度 |
| 大型ミサイルの運用 | AIM-174Bなどを搭載可能(同時搭載数は減少) |
| 特徴 | 多用途型で高い兵装積載能力を持つ |
F/A-18E「スーパーホーネット」は、アメリカ海軍を中心に運用されている多用途戦闘機であり、高いミサイル搭載能力を持った機体です。最大で空対空ミサイルを12発まで装備可能とされていますが、実戦でその全てを使うケースは非常に限られます。
F/A-18Eが搭載できる空対空ミサイルの構成としては、中距離用のAIM-120 AMRAAMを最大10発、短距離用のAIM-9サイドワインダーを2発の合計12発が理論上の限界です。この際、主翼に設けられた11基のハードポイントと、2連装ランチャーの併用によって高い兵装積載量が実現されます。
ただし、これはあくまで「カタログスペック」であり、実際の作戦ではこの最大数すべてを装備することはほとんどありません。理由は複数ありますが、特に重要なのは機体の運動性能や燃費への悪影響です。
ミサイルを満載すると機体重量が増加し、加速や旋回といった高機動戦闘の能力が低下します。また、空気抵抗も大きくなるため航続距離にも悪影響が出ます。
実際の運用例としては、2024年から2025年にかけて米海軍が紅海で展開したF/A-18Eが「AIM-120を5発、AIM-9を4発」の合計9発を搭載して任務にあたったケースが注目されました。このように、最大値に近い構成も採用されるようになってきていますが、これは特定任務向けの特別な装備構成です。
また、近年ではAIM-174Bといった大型の空対空ミサイルを搭載する例も増えつつありますが、この場合は重量制限などを考慮して、同時搭載数が減少する傾向にあります。
つまり、F/A-18Eは理論上12発の空対空ミサイルを搭載できる設計ですが、実戦では8〜9発前後が現実的な上限とされ、ミッション内容によって柔軟に調整されているのが現状です。
F-35戦闘機のミサイル搭載数と運用モード

| モデル | 特徴 | ステルスモード(機内搭載) | ビーストモード(外部搭載) |
|---|---|---|---|
| F-35A(空軍仕様) | 標準的なモデルで最も多く運用されている | AIM-120を最大4発(将来6発に拡張予定) | 10発以上の空対空ミサイル搭載が可能 |
| F-35B(STOVL型) | 垂直離着陸可能でスペースに制約がある | 2~4発と少なめ | 搭載量に制限あり |
| F-35C(艦載型) | 空母での運用に特化し、強化設計が施されている | Aと同等の搭載能力(最大4発) | 10発以上の搭載が可能 |
F-35戦闘機にはA・B・Cの3つのモデルがあり、それぞれにミサイル搭載能力の違いがありますが、いずれも「ステルス性」と「柔軟な兵装運用」を両立する設計が特徴です。特に注目すべきは、運用モードによって搭載数や構成が大きく変化する点です。
まず、F-35A(空軍仕様)をはじめとする各モデルでは、ステルス性を重視する「ステルスモード」と、兵装量を最大化する「ビーストモード」という2つの主要な運用形態があります。
ステルスモードでは、機体内部のウェポンベイにミサイルを収納することでレーダー反射断面積を最小限に抑えます。この際、搭載できる空対空ミサイルの数は、AIM-120 AMRAAMを最大4発までです。
将来的には「サイドキック」と呼ばれる専用のランチャーを導入することで、ウェポンベイに6発搭載できる構成も開発中ですが、2025年時点では標準構成は4発です。
一方で、ステルス性を犠牲にして外部パイロンを使用するビーストモードでは、10発以上の空対空ミサイルや他の爆装を同時に搭載することも可能になります。
この構成ではF-35の機体サイズとパイロン配置の工夫により、大量の兵装を積載することができますが、レーダーへの露出が増えるため敵に発見されやすくなるというデメリットも伴います。
また、モデルによる違いも見逃せません。F-35B(STOVL型)は垂直離着陸機能の影響で内部スペースに制限があり、機内搭載数が2~4発と少なめです。一方、F-35C(艦載型)は空母運用に適した強化設計により、F-35Aと同等の搭載能力を持っています。
このように、F-35のミサイル搭載数は固定的なものではなく、任務内容や運用モード、モデルによって柔軟に変化するのが最大の特徴です。高いステルス性と多様な兵装構成を両立する点で、現代戦闘機の中でも非常に特異な存在といえるでしょう。
F-22戦闘機に搭載できるミサイルの数

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機体名 | F-22 ラプター |
| 世代・特徴 | 第5世代ステルス戦闘機、制空戦闘特化 |
| 通常モードの最大搭載数 | AIM-120 ×6発、AIM-9 ×2発(合計8発) |
| 搭載方式(通常) | すべて機内ウェポンベイに収納、ステルス性重視 |
| 試験時の最大搭載記録 | 最大28発(WSEP 22-12 演習で確認) |
| 試験モードの内容 | 外部パイロン+多連装ランチャー使用(非ステルス構成) |
| 実戦での運用構成 | 通常は8発構成が基本 |
| フル搭載構成の課題 | ステルス性の喪失、重量増、機動力と航続距離の低下 |
| 設計思想 | ミサイル数よりもステルス性と精密攻撃力を重視 |
F-22ラプターは、アメリカが誇る第5世代ステルス戦闘機であり、その兵装搭載能力はステルス性と戦闘力のバランスに重きを置いた設計となっています。搭載できるミサイルの数は、搭載モードによって大きく異なるのです。
通常運用、つまりステルス性能を最大限に活かす構成では、全ての兵装を機体内部のウェポンベイに収納します。この構成では、AIM-120 AMRAAM(中距離ミサイル)を6発、AIM-9 サイドワインダー(短距離ミサイル)を2発の、合計8発が最大搭載数です。
これは、F-22の標準的な空対空戦闘任務における構成とされており、空中戦での高い生存性と攻撃力を両立させています。
一方、ステルス性をある程度犠牲にして外部パイロンを活用することで、さらに多くのミサイルを搭載することも理論上は可能です。特に注目すべきは、2022年に実施された米空軍の評価演習(WSEP 22-12)において、F-22が最大28発の空対空ミサイルを搭載・発射したという記録です。
このときは、外部パイロンや多連装ランチャーなどをフル活用し、あくまで試験的なモードとして実施されました。
ただし、このような運用は実戦向けではありません。外部兵装の搭載は空気抵抗を増やし、F-22最大の強みであるステルス性を著しく損ないます。また、重量増加による運動性能の低下や航続距離への影響も大きいため、日常的な任務では採用されない構成です。
つまり、F-22に搭載できるミサイルの数は、通常運用では8発が現実的な上限であり、28発といったフル装備構成は特殊な試験や想定訓練時に限られた運用です。この機体は数の多さよりも、優れたステルス性と精密な攻撃力によって制空戦闘を支配する設計になっています。
F-2戦闘機はミサイルを何発搭載できる?

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機体名 | F-2 戦闘機 |
| 開発国 | 日本(多用途戦闘機) |
| 対応ミッション | 空対空、空対艦など多目的任務 |
| 空対空ミサイル最大搭載数 | 約8発(短距離・中距離ミサイル混合) |
| 主な空対空ミサイル | AAM-3、AAM-4 |
| 空対艦ミサイル最大搭載数 | 最大4発(例:ハープーン、ASM-2) |
| 複合構成例 | 空対艦ミサイル4発 + 短距離空対空ミサイル2発 |
| 運用上の制約 | 全搭載は非現実的、重量・空力・燃費のバランスが重要 |
| 特徴 | 任務に応じた柔軟な搭載構成が可能 |
F-2戦闘機は、日本が開発した多用途戦闘機であり、空対空から空対艦まで幅広いミッションに対応できる設計になっています。そのため、搭載できるミサイルの種類や本数は、任務内容によって柔軟に構成が変わります。
最大搭載数としては、空対空ミサイルを中心に構成した場合、短距離・中距離のミサイルを組み合わせて合計8発程度の空対空ミサイルを搭載することが可能です。これは、左右の主翼端や胴体下、その他の兵装ステーションを活用して、AAM-3やAAM-4といった日本独自の空対空誘導弾を積むことで実現されます。
一方で、空対艦任務においては、ハープーンやASM-2などの大型空対艦ミサイルを左右に2発ずつ、最大で4発搭載することが標準的です。その場合、空対空ミサイルの搭載数は減少し、例えば「空対艦ミサイル4発+短距離空対空ミサイル2発」といった構成が採用されることが多く見られます。
このような柔軟性を持つ一方で、すべてのハードポイントにミサイルを満載する運用はあまり現実的ではありません。重量・空力バランス・燃費などを総合的に考慮する必要があり、作戦の目的に応じて兵装は最適化されます。特に、F-2はその設計上、航続距離や加速性能を維持するためにミサイル搭載数を絞る場合も少なくありません。
つまり、F-2戦闘機のミサイル搭載数は、任務に応じて調整されるものの、空対空で最大8発、空対艦では4発+αが標準的な構成となります。搭載能力の多さよりも、戦術的な組み合わせの柔軟性がF-2の強みと言えるでしょう。
参考資料:航空自衛隊公式サイト
F-15戦闘機はミサイルを何発搭載できるのか

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機体名 | F-15 戦闘機(F-15C/F-15J/F-15EX) |
| 運用開始年 | 1970年代〜(最新型はF-15EX) |
| 主な運用国 | アメリカ、日本など |
| 従来型の最大搭載数 | 8発(中距離×4 + 短距離×4) |
| F-15EXの最大搭載数 | 12発(拡張型ハードポイント使用) |
| 特殊構成の例 | 4連装ランチャーで16発以上の搭載を計画中 |
| 実戦での搭載目安 | 通常6〜10発が現実的な構成 |
| 搭載制限の要因 | 機動性や燃費の低下を防ぐため |
| 特徴 | 優れた速度・航続距離・搭載力を持つ大型戦闘機 |
F-15戦闘機は、1970年代から運用されてきたアメリカ製の大型制空戦闘機であり、日本ではF-15J型として航空自衛隊でも長年使用されています。この機体の特徴は、優れた速度・航続距離・兵装搭載能力にあります。
従来型のF-15CやF-15Jでは、空対空ミサイルを最大で8発搭載可能です。具体的には、胴体下面に中距離ミサイル(AIM-7スパローまたはAIM-120 AMRAAM)を4発、左右の主翼に短距離ミサイル(AIM-9サイドワインダー)を4発搭載する構成が一般的です。この兵装配置は、空対空戦闘において高い継戦能力を実現します。
さらに、近年配備が始まっている最新型のF-15EX(イーグルII)では、設計が改良されており、最大12発の空対空ミサイル搭載が可能です。
追加されたハードポイントと新型ランチャーの採用により、従来よりも大幅に兵装の搭載量が拡張されています。また、一部計画段階では、特殊な4連装ランチャーを用いて16発以上の搭載も検討されており、「ミサイルトラック」としての運用も視野に入れられています。
ただし、前述の通り、すべてのパイロンにミサイルを満載する構成は実戦ではあまり現実的ではありません。ミサイルを大量に積むことで、機体の機動性や燃費が低下するため、実際の搭載数は6〜10発程度に抑えられるケースが多く、任務内容や空中給油の有無などによって最適なバランスが取られます。
つまり、F-15戦闘機は機種によって差はあるものの、従来型で8発、最新型で最大12発のミサイルを搭載できる性能を持っており、さらなる改良によってその数は今後も拡張される可能性があります。空対空戦における優位性を支える大きな要因の一つが、この高い兵装搭載力です。
戦闘機のミサイル 搭載数の上限と限界
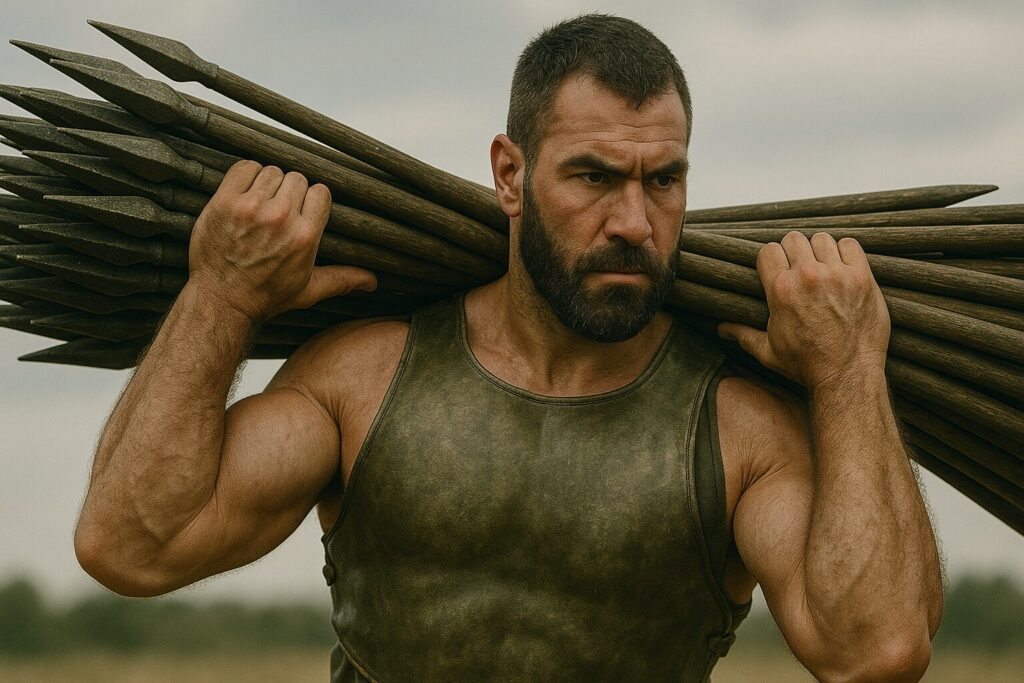
- 戦闘機のミサイルの最大搭載数は?
- 空対空ミサイルで最強のものは?
- サイドワインダーは1機いくら?
- 空対空ミサイルの速さは?
- エースコンバット ミサイルが多すぎの理由
- 搭載数が多ければ強いのか?
戦闘機のミサイルの最大搭載数は?
現代の実用戦闘機における空対空ミサイルの最大搭載数は、「設計上の限界」と「実際の運用で採用される数」の2つに分けて考える必要があります。理論上の最大数は各機体のハードポイント数や装備方式によって異なりますが、一般的に10発以上搭載できる機体は限られているからです。
例えば、アメリカのF-15EXは最新のハードポイント増設によって最大12発の空対空ミサイルを搭載可能です。同様に、F/A-18EスーパーホーネットもAIM-120を10発+AIM-9を2発の計12発まで装備できます。さらにロシアのSu-35は設計思想が異なり、最大14発のミサイルを積載できることで知られています。
一方、特殊な評価試験ではこれを大きく上回る例もあります。F-22は2022年の演習において、最大28発のミサイルを外部パイロンに搭載して発射したという記録がありました。ただし、このような搭載はあくまで訓練用の非ステルスモードで行われたものであり、実戦で採用されることはまずありません。
このように見ると、実戦運用で現実的に採用される最大数は、おおむね10〜14発程度が上限です。パイロン数だけでなく、機体の重さ・空気抵抗・航続距離・機動性といった要素が制約となるため、最大数を積むことは例外的です。任務の目的や作戦内容に応じて、搭載数は柔軟に調整されています。
したがって、「戦闘機のミサイル最大搭載数」とは単に数の問題ではなく、運用の現実性や戦術的な最適化とのバランスを前提とした設計上の限界値であることを理解しておく必要があるのです。
空対空ミサイルで最強のものは?

空対空ミサイルの「最強」とは、単に射程距離が長いことだけを意味しません。以下のような複数の要素を総合的に評価して判断されます。
- 誘導技術の精度
- 命中率の高さ
- 電子戦に対する耐性
- 搭載される戦闘機との統合性
- 実戦での運用実績や信頼性
現在、世界で最強クラスとされる空対空ミサイルは、以下の3種です。
● 中国「PL-15」
- 搭載機:J-20などの第5世代戦闘機
- 射程:約200km以上と推定
- 特徴:アクティブレーダーホーミング搭載、高い電子妨害耐性
- 備考:米空軍が従来型ミサイルでは対抗困難と懸念するほどの性能
● アメリカ「AIM-260 JATM」
- 開発目的:PL-15に対抗するための最新ミサイル
- 性能:AIM-120Dを大きく上回る誘導精度と射程
- 搭載予定:F-22、F-35などの次世代戦闘機
- 配備計画:2020年代後半から本格運用開始見込み
● ロシア「R-37M」
- 最大射程:約400km
- 最高速度:マッハ6に達する高速性能
- 運用特性:早期警戒機・爆撃機などの大型目標を一撃離脱で攻撃
- 弱点:近距離戦での機動性と命中率に課題あり
このように、どのミサイルが「最強」かは、想定される戦闘シナリオや戦略によって異なります。
- 遠距離からの撃墜能力を重視するなら「R-37M」
- 戦術バランスと実戦運用を考慮するなら「PL-15」や「AIM-260」
近年は、性能競争が加速しており、「最も遠くに飛ぶ」ことだけでなく、「どれだけ使えるか」という実用性の評価が重視される時代になっています。
サイドワインダーは1機いくら?

AIM-9「サイドワインダー」シリーズは、アメリカで開発された短距離空対空ミサイルであり、世界中の多くの空軍で採用されてきました。最新型であるAIM-9Xの価格は、モデルや調達契約によって変動しますが、現在の目安としては以下のような金額になります。
米空軍や米海軍が調達する場合、1発あたりの価格はおおよそ43万〜47万ドル(日本円で約4,700万〜5,300万円)とされています。この金額にはミサイル本体の製造コストだけでなく、センサーや電子制御装置といった高度な誘導機構が含まれているため、年々価格は上昇傾向にあります。
一方、FMS(有償対外軍事援助)制度を通じて他国へ輸出される場合は、ミサイル本体に加えて保守契約、訓練支援、物流費用などが含まれるため、1機あたり80万〜90万ドル(約8,900万〜1億円前後)にまで上昇することも珍しくありません。
価格差の背景には、ミサイルの型式や技術レベルの違いがあります。例えば、旧型のAIM-9LやM型は比較的安価でしたが、最新のAIM-9Xでは全方位ロックオン、画像誘導、ジャミング対策などの高機能が追加されており、これが大きなコスト要因となっているからです。
また、生産規模や調達数も価格に影響を与える要素です。大量調達により単価を抑えることが可能ですが、特注仕様や小ロット生産ではコストが上昇する傾向があります。
このように、「サイドワインダー1機の価格」は、使用国、型式、契約内容によって大きく変動します。最新型のAIM-9Xを米軍が調達する場合でも1発約5,000万円前後という高額な兵器であることを理解しておくと良いでしょう。
空対空ミサイルの速さは?

| ミサイル種別 | 代表例 | 飛行速度 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 短距離空対空ミサイル | AIM-9 サイドワインダー、IRIS-T | マッハ2.5〜3(約3,000〜3,700km/h) | 近距離戦闘、ドッグファイト | 高い機動性と誘導精度に特化 |
| 中距離空対空ミサイル | AIM-120 AMRAAM、R-77 | マッハ3.5〜4(約4,300〜5,000km/h) | 中距離からの迎撃 | 広範囲を迅速にカバー可能 |
| 超長射程空対空ミサイル | R-37M(ロシア) | マッハ6(約7,000km/h) | 大型機(早期警戒機・爆撃機)迎撃 | 高高度・長距離迎撃に特化 |
空対空ミサイルの飛行速度は、種類によって大きく異なります。一般的には「中距離ミサイル」と「短距離ミサイル」の2つに分類され、それぞれに適した速度性能が設計されています。
中距離空対空ミサイル、たとえばAIM-120 AMRAAMやロシアのR-77などは、敵機を目視できない距離からの交戦を目的としており、最大でマッハ3.5~4.0(時速約4,300~5,000km)の速度で飛行。これにより、広い空域をカバーしつつ、目標に対して迅速に到達することができます。
一方で、短距離空対空ミサイル(例:AIM-9 サイドワインダーやIRIS-Tなど)は、主に近距離戦闘やドッグファイトで使用され、マッハ2.5~3程度が標準的です。こちらは、機動性と誘導精度を重視した設計となっており、目標の激しい回避運動に対応できるように設計されています。
さらに、ロシアが開発したR-37Mのような超長射程ミサイルは、マッハ6(時速約7,000km)に達する速度性能を持ち、高高度からの発射により長距離での高速迎撃が可能です。これは主に早期警戒機や大型爆撃機を対象とした用途で設計されており、速度と射程の両立を目指しています。
空対空ミサイルの速度は、推進システム、ミサイルの大きさ、空気抵抗、飛行高度など複数の要素によって決まります。高速であるほど命中率や回避困難性は増しますが、誘導精度や操縦性とのバランスも重要であり、単に「速いほど優れている」とは限りません。
このように、空対空ミサイルの速さはマッハ2.5〜6程度まで幅があり、用途や技術レベルによって最適化されているのが現状です。
エースコンバット ミサイルが多すぎの理由

ゲーム「エースコンバット」シリーズでは、戦闘機が現実では考えられないほど大量のミサイルを搭載して戦う姿が描かれます。中にはF-16で50発以上、架空機では100発を超えるミサイルを撃てる場面もあり、これに疑問を抱いたプレイヤーも多いのではないでしょうか。
このような設定が採用されているのは、あくまでもゲーム性を優先した演出によるものです。プレイヤーが多数の敵機や地上目標とテンポよく戦い、爽快感を得られるように設計された結果、弾数の制限が緩くなっています。
仮に現実の戦闘機と同じく「6〜12発程度しか撃てない」設定にした場合、敵の数に対応しきれず、ゲームが成り立たなくなってしまうためです。
また、ゲームではストレスなく攻撃を繰り出せるよう、リロードや弾薬管理の制約が緩くなっています。その結果、ミサイルはまるで弾丸のように連射できる設計になっており、プレイヤーが戦術を自由に組み立てられるようになっています。
一部のプレイヤーは、見た目の懸架数(ミサイルの見た目の数)に合わせて使用制限を設ける「縛りプレイ」を行うこともありますが、これはごく一部の楽しみ方に過ぎません。
つまり、「ミサイルが多すぎる」のは現実の軍事仕様とは無関係な、ゲームならではのバランス調整と演出効果によるものです。リアルさよりも、プレイヤー体験を重視した設計思想が背景にあります。
搭載数が多ければ強いのか?

戦闘機のミサイル搭載数は確かに戦力を測る一つの要素ですが、「多ければ強い」という単純な考え方が常に正しいわけではありません。実際の戦闘では、以下のような複数の要素が総合的に勝敗を左右します。
- 機体そのものの加速力や旋回性能
- レーダーやセンサーの探知・追跡能力
- パイロットによる戦術判断と操作技量
たしかに、ミサイル搭載数が多いことにはメリットがあります。
- 複数の目標に対して同時に対応しやすくなる
- 弾薬切れのリスクが低減する
- 長時間の任務でも余裕を持った交戦が可能
こうした利点は、特に多数の敵機との遭遇や、広域な空域の警戒任務などで顕著に発揮されます。
しかし、その反面でデメリットも明確です。
- 搭載数が増えると機体重量が増加し、機動性が低下する
- 外部パイロンに多数の兵装を装着すると空気抵抗が増え、航続距離や速度性能が損なわれる
- ステルス機の場合は、外装兵装がレーダー反射面積を拡大させ、被探知性が上昇する
実際、F-22やF-35などのステルス戦闘機では、ミサイルを機体内部のウェポンベイに収めることでレーダーへの露出を抑えています。これは、あえて搭載数を減らすことで「発見されにくさ」を優先する戦術思想を反映したものです。
また、多くの任務において全パイロンにフル装備を行うことはまれで、任務内容に応じて以下のように装備構成が調整されます。
- 空対空任務では高機動性を優先し、軽装備にするケース
- 空対地攻撃では大型ミサイルや誘導爆弾を中心に構成
- 偵察・警戒任務では電子戦装備を優先してミサイル数を抑制
このように、ミサイルの搭載数だけでは戦闘機の「強さ」を測ることはできません。真に重要なのは、以下の3点がバランス良く整っていることです。
- 任務に最適化された兵装構成
- 機体の基本性能と兵装の整合性
- ステルス性や作戦範囲など戦術的条件の総合調整
数だけを追い求めるのではなく、全体として機能するシステムとしての完成度が、現代の戦闘機における強さを決定づけているのです。
現代戦闘機におけるミサイル搭載数の実態を総括
この記事のポイントをまとめます。
- F/A-18Eは最大12発だが実戦では9発前後が現実的
- F-35は運用モードにより4~10発以上と変化する
- F-22は標準で8発、試験では28発の搭載例もある
- F-2は空対空で最大8発、空対艦では4発が目安
- F-15は従来型で8発、最新型EXでは12発以上も可能
- Su-35は設計上最大14発を搭載できる
- 搭載数が増えると空気抵抗や運動性能に悪影響がある
- ステルス戦闘機は内部搭載により搭載数が制限される
- 任務内容に応じて兵装構成は柔軟に調整される
- ビーストモードではステルス性を犠牲にして火力を増す
- 外部パイロンの使用はステルス性低下の大きな要因となる
- ミサイル搭載数はカタログ値と実戦値で乖離がある
- 最新型では多連装ランチャーによる搭載拡張も進む
- 機体設計によって同じ兵装でも搭載数に差が出る
- 単なる数の多さより戦術的な運用バランスが重要
最後までお読みいただきありがとうございました。
おすすめ記事:
飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策
飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド
ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説
プライベートジェットの購入価格を徹底解説!所有する有名人の事例