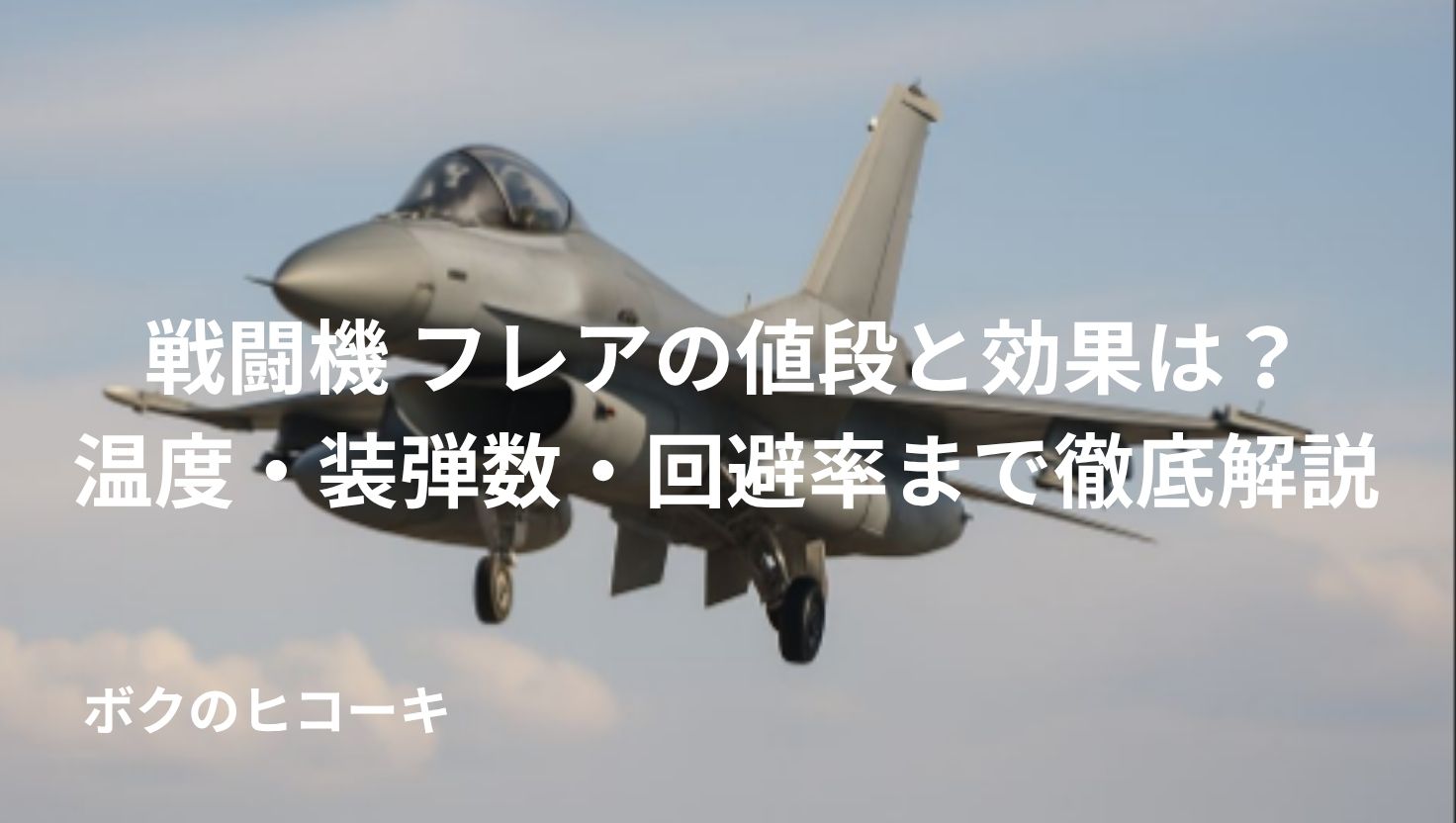現代の戦闘機には、目に見えないミサイルの脅威から機体やパイロットを守るための高度な防御装備が搭載されています。その中でも「フレア」は、赤外線誘導ミサイルを回避するために欠かせない防御手段の一つです。
本記事では、「戦闘機 フレアの値段と効果」に関心を持つ方に向けて、フレアの基本的な仕組みや価格の相場、実際の効果や回避率などをわかりやすく解説していきます。
フレアは「火炎弾」や「発炎弾」といった日本語表現でも呼ばれることがあり、その役割は単なる発射物ではなく、命を守るための重要な装備です。
戦闘機がフレアを使う理由には、ミサイル回避だけでなく、自衛的な警告行動も含まれています。また、フレアは「チャフ」と並ぶ代表的な防御装備であり、「デコイ」との違いを理解することも重要です。
本記事では、戦闘機のフレアの温度や装弾数、自動展開の仕組みなど、実際の運用に関する知識も盛り込んでいます。さらに、日本の自衛隊がフレアを使用した具体的な状況にも触れ、現実の運用事例からその重要性を深掘りしました。フレアの値段と性能の関係に疑問を持った方は、ぜひ最後までご覧ください。
- フレアの価格帯と性能の違い
- フレアの仕組みと回避効果の仕組み
- 戦闘機がフレアを使う理由と運用方法
- 自衛隊が実際にフレアを使用した事例
【戦闘機のフレア】値段の相場と価格差

- 値段の相場と価格差
- フレアの装弾数は?
- フレアの効果と回避率
- 戦闘機のフレアの温度は?
- フレアの日本語「火炎弾」
- 「デコイ」と「チャフ」と「フレア」の違い
値段の相場と価格差
| フレア名 | 価格(1発あたり) | 搭載機種例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| M206 | 約35ドル | A-10、F-16など | 構造がシンプルで大量生産向き |
| MJU-61/B | 約75ドル | 複数の機体に対応 | 基本構造を維持しつつ広範な対策が可能 |
| MJU-53/B | 約75ドル | 複数の機体に対応 | 中価格帯でバランスの取れた性能 |
| MJU-68/B | 約3,000ドル | F-35など | 赤外線スペクトル全域対応・高性能センサー妨害 |
戦闘機で使用されるフレアの価格は、想像以上に幅があります。安価なタイプでは数十ドル程度ですが、高性能なものになると1発あたり数千ドルに上ることもあります。この大きな価格差は、使用される製造技術の複雑さや、対応が求められるミサイルの種類、さらに搭載機の任務内容や運用環境といった要素に左右される構造です。
基本的なフレアの一例として、アメリカのA-10やF-16などが使用する「M206」は、1発あたりおよそ35ドルと比較的安価です。これは大量生産されており、構造もシンプルなため低価格で提供されています。
一方で、F-35のような最新鋭戦闘機に搭載される「MJU-68/B」のようなフレアは、1発あたり約3,000ドルという非常に高額な価格が設定されています。このフレアは、赤外線スペクトル全域への対応や高度なミサイルのセンサー対策など、複雑な防御性能を備えていることが特徴です。
他にも、MJU-61/BやMJU-53/Bなど、比較的新しいモデルでは1発あたり75ドル前後となっており、中間的な価格帯に位置しています。これらは、M206と同様の基本構造を持ちながらも、より広範なミサイル対策が可能な設計となっているのです。
これを見ればわかるように、フレアの価格は単なる「弾薬の単価」ではなく、航空機の任務の危険度、ミサイルの進化への対応能力、そして装備の先進性に応じて変動します。つまり、フレアは消耗品であると同時に、航空機の生存性を左右する重要な投資対象でもあるのです。
フレアの装弾数は?

戦闘機が搭載するフレアの装弾数は、機体の種類や任務の内容によって異なりますが、おおよそ30~60発程度が一般的な装填数です。これは「1つのフレアディスペンサー(投射装置)につき約20~30発程度」が標準で、複数のディスペンサーを搭載することで合計発数が増加します。
例えば、F-15戦闘機では左右に1基ずつフレアディスペンサーが装備され、各ディスペンサーに30発前後のフレアを装填することが可能です。これにより、1回の出撃で最大60発程度のフレアを発射できる設計となっています。
F-16やF-35といった他の主要な戦闘機も、同様の構造を採用。ディスペンサーの位置は主に主翼の付け根や機体下部にあり、ミサイルの進入角度に応じて効率的にフレアを展開できるようになっています。
ここで注意すべき点として、フレアは「ミサイルの接近時に一度に複数発同時に発射される」ことが多く、実際の作戦ではあっという間に消費されるという特徴があります。ミサイルが複数回発射されたり、連続して回避行動を取る必要がある場合には、数十発でも十分とは言えないのが実情です。
さらに、チャフ(レーダー妨害用の金属片)との混合装填も一般的であるため、ディスペンサーの一部にはチャフが割り当てられ、結果としてフレアの搭載数が制限されることも。こうした制約を踏まえ、航空機は出撃前にミッション内容や敵の脅威に応じて、フレアとチャフの比率や搭載数を慎重に設定しています。
フレアの効果と回避率

フレアの主な目的は、赤外線誘導ミサイルから戦闘機を守ることにあります。ミサイルは通常、ジェットエンジンの排気が発する赤外線(熱)を追尾する仕組みを持っており、フレアはこれを逆手に取った防御手段として機能します。具体的には、フレアが機体よりも強力な熱源となることで、ミサイルのセンサーを欺き、進路をそらせるのです。
ただし、その効果や回避率は一律ではなく、次のような条件によって大きく左右されます。
- 使用するフレアの種類と性能
- 対応するミサイルの技術レベル(旧型か最新型か)
- フレアを発射するタイミングや飛行条件
例えば、旧式の赤外線ミサイルに対しては、以下のような高い効果が確認されています。
- フレア使用時の回避成功率は70~90%に達する場合がある
- 単純な熱量を追尾するセンサーが多いため、誤誘導が容易
一方で、近年増えているIIR(赤外線画像誘導)ミサイルには、以下のような難点があります。
- 熱源の形状や動きも検知できるため、フレア単体では欺けない
- ある調査では、フレア単独での回避成功率が8%にとどまった事例も存在
このような状況では、以下のような複合的対策が求められます。
- 機体の急旋回や加速を用いた回避行動
- 電子妨害装置(ECM)との併用
- 適切な戦術の選択と即応性の確保
それでもなお、フレアは有効な防御装備として広く使用されています。特に次のような戦術により、フレアの効果は大きく高まります。
- 「ディストラクション戦術」:ミサイルが標的を認識する前に展開
- 「セダクション戦術」:ロックオン後に即座にフレアを発射し誘導をそらす
ただし、以下のような使い方には注意が必要です。
- タイミングを誤ると効果が得られず、逆に脆弱になる可能性がある
- 必要以上にフレアを発射すれば、装備の浪費や弾切れを招く恐れがある
そのため、実際の運用では自動制御システムやパイロットの訓練によって、状況に応じた正確な発射が行われるよう設計されています。フレアは単なる発熱装置ではなく、状況判断と連携した防御戦術の一環として機能しているのです。
戦闘機のフレアの温度は?

戦闘機から発射されるフレアの温度は、非常に高温であることが特徴です。一般的にはおよそ2,000℃前後、ケルビン温度で言えば2,200K程度に達します。この高温こそが、赤外線誘導ミサイルに対抗するうえで決定的に重要な要素なのです。
赤外線誘導ミサイルは、航空機のエンジン排気などから放出される赤外線(熱)を探知して目標に向かいます。つまり、エンジンが発する赤外線よりも強く、ミサイルのセンサーにとって魅力的な熱源を作り出すことができれば、ミサイルはそちらに誘導される可能性が高まるというわけです。
ここでフレアの構造に注目すると、燃焼の中心となるのはマグネシウムやテフロンなどを主成分とした火工品です。これらは空中に放出された直後に激しく酸化し、高温の火炎を発生させます。燃焼時間はおおよそ2〜3秒程度と短時間ですが、その間に航空機のエンジン排気以上の赤外線エネルギーを発することができます。
ただし、高温であることが必ずしも万能ではありません。近年のミサイルは赤外線の波長特性を識別したり、対象の形状を解析する機能も持っているため、「単純に熱い」だけのフレアでは通用しないケースも出てきています。
そうした場合には、複数の波長に対応した「スペクトル型フレア」や、燃焼せずに赤外線だけを発する「自然発火型デコイ」などが使われます。
このように、戦闘機のフレアが生み出す約2,000℃の熱は、従来型の赤外線ミサイルにとって非常に強力な妨害手段である一方で、最新型ミサイルには別の工夫が求められています。高温は基本性能として重要であるものの、それだけに依存しない進化が続いているのが現状です。
フレアの日本語「火炎弾」

「フレア」という言葉は一般的に英語のままカタカナで使われていますが、日本語では「火炎弾」あるいは「発炎弾」と呼ばれることがあります。いずれも正式な訳語として使用されており、防衛関連の資料や報道でも見かける表現です。
火炎弾という表現は、フレアの見た目や動作から来ています。フレアは空中で激しく燃焼し、炎と煙を伴って強烈な熱を放出。この様子がまさに「火を噴く弾丸」のように見えることから、火炎弾と呼ばれるようになったと考えられます。
ただし、ここで注意しておきたいのは、フレアは攻撃目的の兵器ではないという点です。焼夷弾や爆弾といった攻撃用の火炎兵器とは異なり、フレアはミサイルの赤外線センサーを欺いて回避するための「防御用装備」に分類されます。つまり、相手を破壊したり殺傷するためではなく、自機を守るための手段なのです。
一方で、発炎弾という呼び方は、より機能に忠実な表現とも言えます。発炎、つまり「炎を発する装置」という意味であり、フレアの本質である赤外線を放射する熱源という側面を端的に表しているからです。防衛白書などの公的文書では「発炎弾」という語が好まれる傾向にあります。
このように、「火炎弾」と「発炎弾」はいずれもフレアの日本語訳として使われますが、それぞれ微妙にニュアンスが異なります。
前者は外見的な印象、後者は機能的な側面に着目した表現です。文脈によって使い分けることが望ましいですが、一般的な会話やメディア報道では「フレア」というカタカナ表記も広く定着しているのが現状です。
「デコイ」と「チャフ」と「フレア」の違い

| 装備名称 | 主な用途 | 仕組み・特徴 | 対応する脅威 |
|---|---|---|---|
| デコイ | 敵の攻撃や追尾を誤誘導する | チャフやフレアを含む広義の欺瞞装置。模擬標的や自立型囮も含む | 全般(レーダー・赤外線など) |
| チャフ | レーダー誘導ミサイルへの妨害 | 金属片を空中に撒きレーダー波を乱反射。偽の反射源を作る | レーダー誘導ミサイル |
| フレア | 赤外線誘導ミサイルからの防御 | 高温で燃焼し赤外線を放射。ミサイルを熱源として誘導 | 赤外線誘導ミサイル |
軍用機が装備する防御装置には、「デコイ」「チャフ」「フレア」と呼ばれる3つの主要な手段があります。これらはすべて敵のミサイルやセンサーを欺くことを目的とした装備ですが、対象とする脅威や仕組みは大きく異なるのです。
まず「デコイ」は最も広い意味を持つ言葉で、敵をだます目的の装置全般を指します。つまり、チャフやフレアも広義にはデコイに含まれます。さらに、艦艇が発射する模擬標的や、自立して飛行する囮ミサイルなどもデコイの一種です。
次に「チャフ」ですが、これは主にレーダー誘導ミサイルに対抗するための装備です。中身は細かく裁断されたアルミニウムなどの金属片で、空中にばらまかれることでレーダー波を乱反射させ、複数の偽の反射源を作り出します。その結果、敵のレーダーは本物の航空機を見失い、ミサイルの誘導も困難になります。
一方で「フレア」は、赤外線誘導ミサイルに対抗するために使われる装備です。マグネシウムなどの火工品を高温で燃焼させることで、航空機よりも強い赤外線信号を発し、ミサイルのセンサーを欺いて進路をそらします。燃焼時間は数秒と短いものの、その瞬間的な熱エネルギーは極めて強力です。
ここで重要なのは、チャフはレーダー波を妨害し、フレアは赤外線センサーを欺くという点です。つまり、両者は異なる種類のミサイルに対して使い分けられる必要があります。現代の戦闘機や輸送機は、これらを同時に搭載し、状況に応じて自動または手動で展開できるよう設計されています。
言い換えれば、フレアとチャフは「異なる敵に対抗するための専用ツール」であり、機体の生存性を高めるうえでどちらも欠かせない装備と言えるでしょう。デコイという用語は、その包括的な枠組みとして理解しておくと混乱がありません。
【戦闘機フレア】値段の背景となる仕組み

- フレアの仕組みと燃焼メカニズム
- 戦闘機がフレアを使う理由とその意義
- なぜ戦闘機はフレアを自動展開できるのか
- 日本の自衛隊がフレアを使用した具体的な状況
フレアの仕組みと燃焼メカニズム
戦闘機に搭載されるフレアは、赤外線誘導ミサイルの追尾機能を欺くために使われる「熱源型のデコイ装置」です。構造自体はシンプルですが、その役割は現代の航空戦で非常に重要です。
フレアの基本構成には以下のような特徴があります。
- 主成分にマグネシウム、テフロン、金属酸化物などの火工品を使用
- 空中でこれらの物質が激しく燃焼し、強力な赤外線を放射
- 燃焼温度は約2,000℃に達し、航空機エンジンの排気熱よりも高温
- ミサイルの赤外線センサーにとって、フレアの方が魅力的な熱源になるため、ミサイルを引き寄せることが可能
点火方式には2種類あり、それぞれ異なる利点があります。
- 火工品型:内部の点火薬を使用して強制的に着火させる方式
- 自然発火型:空気と接触することで酸化反応を起こし、火種なしで燃焼を開始する方式(高速展開や厳しい気候下に有利)
燃焼時間は短く、2~3秒ほどですが、その間に強烈な赤外線信号を発して、ミサイルの誘導機能を混乱させます。ただし、次のようなデメリットもあります。
- 燃焼時に発生する炎や煙により、夜間では敵から視認されやすくなる
- 可視光を抑えたタイプや、赤外線スペクトルに合わせて設計されたフレアでその弱点をカバーする動きもある
このように、フレアは単なる発熱体ではなく、細かく設計された防御装備です。使用される素材、点火の仕組み、燃焼時間といった複数の要素がその防御性能に直結しています。
戦闘機がフレアを使う理由とその意義

戦闘機がフレアを使用する目的は、主に敵の赤外線誘導ミサイルから機体を守ることです。フレアは、防御装備のひとつとして航空機に搭載され、パイロットや乗員の命を守るための重要な役割を担っています。
赤外線誘導ミサイルの特徴として、以下の点が挙げられます。
- エンジン排気の熱(赤外線)を感知して目標を追尾する
- 一度ロックオンされると命中精度が高く、回避が困難
このような脅威に対して、フレアは以下のように機能します。
- マグネシウムなどの高温燃焼素材で構成されている
- 燃焼時に強力な赤外線信号を放出する
- ミサイルのセンサーにとって、より魅力的な熱源として認識されやすい
- 結果として、ミサイルの進路を航空機からフレア側に逸らすことが期待できる
この防御手段は、F-15やF-2、F-35といった航空自衛隊の戦闘機にも共通して搭載されており、実戦・訓練の両方で広く運用されているものです。特に以下のような場面では、自動的にフレアが放出される場合があります。
- 危険地域への侵入時
- 低空飛行中の接近戦想定
- 高リスクな作戦飛行時の予防措置
さらに、フレアは非攻撃的な「警告行動」としても活用されることがあります。具体的な用途は以下の通りです。
- 領空に接近または侵犯した外国軍機への非武力的対応
- 無線警告を無視する相手に対して、強い意思表示として発射
- 空中で強い光を放つことで、視覚的な警告手段となる
実例として、2024年9月にはロシア軍哨戒機による度重なる領空侵犯に対し、航空自衛隊がフレアを発射したという事案が発生しました。この行動は、武器を用いずに明確な抗議を示す方法として慎重に選ばれたもので、国際的なルールに違反しない非武力的措置とされています。
ただし、フレア運用にはいくつかの注意点もあります。
- 地上付近での発射は、気象や地表環境への影響が懸念される
- 消耗品であり、有効期限が存在するため定期的な使用・管理が必要
- 不適切な発射は、逆に防御力を損なう可能性がある
このように、フレアは単なる熱源弾薬ではなく、防御技術としてだけでなく外交的メッセージの伝達手段としても価値を持ちます。状況に応じて柔軟に活用されるフレアは、現代の航空戦や安全保障において欠かすことのできない重要な装備といえるでしょう。
なぜ戦闘機はフレアを自動展開できるのか

現代の戦闘機がフレアを自動で展開できる理由は、機体に搭載された「ミサイル警戒システム(MAWS)」などの電子センサーが進化しているからです。これらのシステムは、敵ミサイルの発射や接近を瞬時に検知し、パイロットの操作を待たずにフレアを自動的に発射する機能を持っています。
このような自動展開の仕組みは、パイロットの生存性を高めるうえで非常に有効です。高速で飛行中にミサイルの脅威を認識し、手動で反応するには時間が足りません。自動制御による即時展開によって、数秒の遅れが生死を分ける戦闘状況でも対応できるようになります。
センサーが検知するのは、ミサイルの赤外線放射や発射時の熱、もしくは機体に近づく異常な動きなどです。検知後は、事前に設定されたアルゴリズムに基づいて、最適な数・タイミング・方向でフレアが放出されます。さらに、機体の動きに連動して回避運動も同時に取るような統合的なシステムも導入されています。
また、特定の状況では「予防的な展開」も可能です。たとえば、敵対勢力の赤外線ミサイルが潜んでいる可能性がある地域を飛行する際、ミサイルが実際に発射されていなくても、一定間隔で自動的にフレアをばらまくよう設定されているケースもあります。
これにより、センサーでは探知できない潜在的な脅威に対してもリスクを軽減することができます。
一方で、自動展開機能には誤作動やフレアの無駄遣いといったリスクも。そのため、多くの機体では「自動・半自動・手動」の切り替えが可能であり、パイロットや状況に応じて運用モードを選択できるようになっています。
このように、フレアの自動展開は最新の電子防御技術によって実現されており、現代の航空戦においては不可欠な防御システムの一部となっています。
日本の自衛隊がフレアを使用した具体的な状況

2024年9月23日、日本の航空自衛隊は極めて異例の対応として、実際にフレアを発射するという行動に出ました。これは、北海道・礼文島北方の空域においてロシア軍の哨戒機IL-38が日本の領空を3度にわたり侵犯した事案に対する対応でした。
この日、自衛隊は対象機に対してまず無線での呼びかけや、接近飛行による警告を実施しました。しかし、相手機は警告に応じることなく再度領空に侵入したため、航空自衛隊の戦闘機はついに「フレア発射」という手段を選択します。これが日本における、領空侵犯に対する「実戦でのフレア使用」の初めての例とされています。
この判断は、防衛省によって「最も強い非武力的警告手段の一つ」として位置づけられています。つまり、武器を使用することなく、しかし相手に対して明確かつ視覚的に強いメッセージを伝える目的で実施された措置ということです。
発射されたフレアは空中で強く光り、遠方からもその存在が明確に確認できます。そのため、フレアは単なる熱源ではなく「視覚的警告装置」としても高い効果を持っています。この対応は、これ以上の領空侵入を認めないという日本側の姿勢を明確に伝える強力な手段となりました。
もちろん、フレア発射は通常の運用では防御手段に限定されるため、こうした対応は極めて限定的です。今回のケースでは、複数回の領空侵犯と無反応という背景があり、最終手段として発動された形でした。
このような具体的な事例を通じて、フレアは「戦術兵器」だけでなく、「外交的メッセージ」としての機能も担っていることがよく分かります。
参考資料:NHK
戦闘機 フレア 値段の背景と性能の総まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- フレアの価格は1発あたり35ドル〜3,000ドルと幅がある
- 安価なM206型は構造がシンプルで大量生産向き
- 最新鋭のMJU-68/Bは高性能だが高額
- 中間価格帯のフレアも存在し用途に応じて選ばれる
- 搭載数は1機あたり約30〜60発が一般的
- フレアは同時に複数発発射されるため消費が早い
- チャフとの混合搭載によりフレア数が制限されることもある
- 赤外線ミサイルに対する回避率は状況により変動する
- 旧型ミサイルには高い効果を発揮する
- IIR型ミサイルには単独では効果が限定的
- フレアの温度は約2,000℃でエンジン排気を上回る
- 使用される火工品にはマグネシウムやテフロンを含む
- 自動展開はセンサーと連動した電子防御システムによる
- 威嚇や警告として使用される場合もある
- フレアは攻撃用ではなくあくまで防御目的の装備
最後までお読みいただきありがとうございました。
おすすめ記事:
飛行機に爪切りの持ち込みはOK?国内線と国際線ルールを完全ガイド
【宙わたる教室】原作は全何話?文庫本の発売日や購入情報も徹底解説
飛行機のシャンプー持ち込み 国内線 国際線別ルールとおすすめ対策
ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説