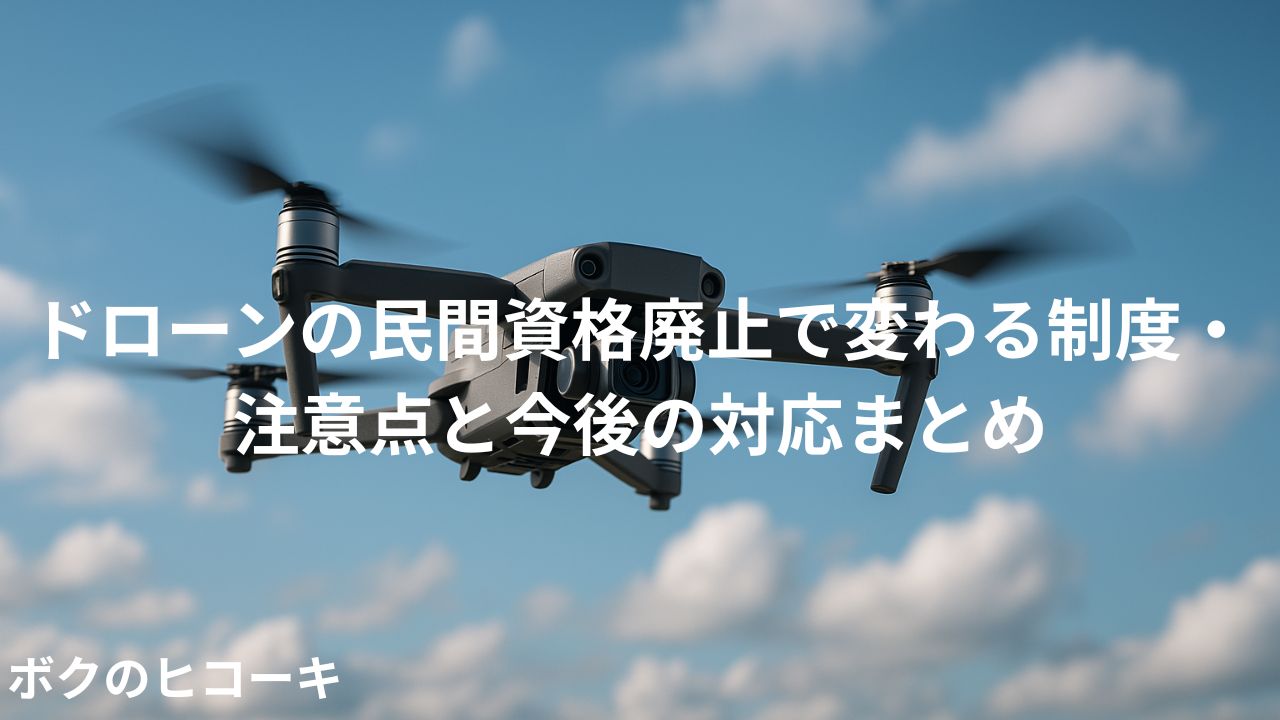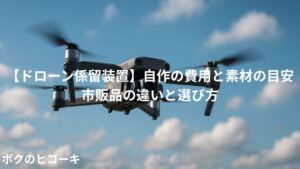ドローンの活用が広がる中で、操縦に関する制度も大きな転換点を迎えようとしています。特に「ドローンの民間資格 廃止」に関心を持つ方が増えており、2025年12月に向けて大きな変更が予定されているのが現状です。
これまで、民間ライセンスを取得していれば飛行許可申請の際に一部手続きが簡略化されるなど、民間資格の優遇や免除のメリットが存在しました。しかし、制度の見直しにより、「民間ライセンスが2025年12月に無効になる?」という不安の声も上がっています。
本記事では、国土交通省が導入した国家資格制度の概要や、民間資格が今後どうなるのかについて詳しく解説いたします。これからドローンを業務やビジネスに活用したいと考えている方にとって、どの資格を取得すべきか、どのように対応すればよいのかを判断するための手助けとなる内容を以下にまとめました。
- 民間資格が飛行申請に使えなくなる時期と理由
- 国家資格制度の内容と取得の流れ
- 民間資格の今後の扱いや活用方法
- 民間資格と国家資格の違いやメリット
ドローン民間資格廃止の理由と背景

- 民間ライセンスが2025年12月に無効になるって本当?
- 国土交通省が導入した国家資格制度とは
- 国家資格への一本化で何が変わるのか
- ドローンの飛行ルール強化と資格の統一
- 民間資格は完全に廃止されるの?
民間ライセンスが2025年12月に無効になるって本当?
2025年12月以降、民間ライセンスは飛行許可申請の簡略化には使えなくなります。ですが、「民間ライセンスそのものが完全に無効になる」というわけではありません。
この変更の背景には、ドローンの安全な運用を強化したいという国の方針があります。従来は、一定の民間資格を持っていれば飛行許可申請時の手続きが一部省略される制度がありました。しかし、資格を発行する団体によって基準にばらつきがあるため、国土交通省は技量や知識を証明する手段としての信頼性に課題を感じていました。
例えば、ある団体では実技重視の資格であっても、別の団体では座学中心の資格となっているケースもあります。このような状況では、申請手続きを簡略化する前提となる「一定レベル以上の操縦技術」を公平に判断することが難しくなるでしょう。
このため、2025年12月5日以降は、民間ライセンスを持っていても、それを根拠に飛行申請の書類を省略することはできなくなります。ただし、民間ライセンス自体が無効化されるわけではありません。今後も、知識や技能の習得を示す証明として活用することは可能です。
つまり、業務や特定の飛行でドローンを活用する場合は、国家資格の取得が事実上の必須条件になります。一方で、趣味や自己研鑽の目的であれば、民間ライセンスの取得にも引き続き価値があると言えるでしょう。
参考資料:「無人航空機操縦者技能証明等」国土交通省
国土交通省が導入した国家資格制度とは

ドローンの国家資格制度は、2022年12月から国土交通省によって正式に導入されました。この制度の目的は、操縦者のスキルと知識を国の基準で統一し、安全な飛行を保証することです。
この資格制度では、「無人航空機操縦者技能証明」という名称のライセンスが発行され、一等と二等の2種類に分かれています。二等資格は比較的一般的な業務飛行に対応。一等資格を取得すれば、より高度な飛行、たとえば有人地帯での目視外飛行(いわゆるレベル4飛行)が可能になります。
これまでの民間資格と異なり、国家資格は航空法に基づいて発行されるため、国が操縦技術を直接審査・証明する点が大きな違いです。試験は「学科」「実地」「身体検査」の3つで構成されており、合格すれば「無人航空機操縦者技能証明書」が交付されます。
また、登録された講習機関で所定のカリキュラムを修了すれば、実地試験が免除される制度もあり、スムーズに取得できる仕組みも整えられています。
この国家資格制度の導入によって、申請手続きの簡略化や、飛行範囲の拡大といった実用面でのメリットも生まれました。例えば、DID地区(人口集中地区)や夜間の飛行が条件付きで許可不要になることもあります。
今後、ドローンを業務で活用する予定がある場合、国家資格の取得は避けて通れない流れになるでしょう。正確な知識と技術を持つ操縦者として認められるためにも、この制度を正しく理解しておくことが大切です。
国家資格への一本化で何が変わるのか

民間資格から国家資格への一本化により、飛行許可の申請や操縦者の評価制度が大きく変わります。最も影響を受けるのは、ドローンを業務で使う人や、特定の飛行条件に該当するケースです。
まず、これまで民間資格を保有していれば、飛行許可申請時の一部書類を省略できる優遇措置がありました。しかし、今後はこの優遇がなくなり、申請手続きを簡略化するには国家資格が必須になります。つまり、国家資格を持っていないと、飛行のたびに細かい情報をすべて提出しなければならなくなるということです。
さらに、操縦者のスキル評価が国の基準に一本化されたことで、「資格の信頼性」や「技術の均一性」が確保されやすくなりました。
民間資格は発行元の団体によって難易度や内容にばらつきがありましたが、国家資格では学科・実地試験・身体検査という共通の試験を経てライセンスが交付されるため、一定レベル以上の操縦者であることが客観的に示せるようになります。
例えば、ある事業者が人が多く集まるイベントで空撮を行いたい場合、これまでは民間資格でも一部申請の省略が認められていました。しかし今後は、国家資格がなければその飛行には追加の許可が必要になる可能性があります。
このように制度が変わったことで、飛行の自由度を保ちたい、あるいは業務効率を高めたいと考えるなら、国家資格の取得が現実的な選択肢になります。一方、趣味や練習目的での飛行であれば、許可申請をすれば従来通り飛ばすことは可能です。
ドローンの飛行ルール強化と資格の統一

近年、ドローンの飛行ルールは確実に厳しくなってきています。そして、こうしたルールの強化とあわせて進められているのが、操縦資格の統一です。目的は、ドローンによる事故やトラブルを防ぎ、安全な運用を徹底することにあります。
かつては、重量200g未満のドローンはほとんどの規制の対象外でした。しかし現在では、100g以上の機体は機体登録が義務づけられ、飛行場所や時間帯にも厳しいルールが設けられています。加えて、飛行するために許可や承認が必要となる「特定飛行」の対象も増加しており、個人・法人問わず注意が必要です。
このような状況で、民間資格のままでは十分な知識や技術の担保が難しいと判断されました。複数の団体がそれぞれ独自の基準で資格を発行していたため、安全性の一貫性が保ちにくかったからです。そこで導入されたのが国家資格制度であり、すべての操縦者を共通のルールで評価する仕組みに変わりました。
例えば、夜間飛行や目視外飛行を行う場合、以前であれば民間資格があれば一部省略できた申請も、今後は国家資格がなければ同様の飛行が難しくなります。また、無資格のまま飛行させる場合も、許可・承認が必要なエリアでは従来以上に細かい条件に対応しなければなりません。
安全管理がより厳格になっている今、ドローンを安全に運用するには、制度を正しく理解し、ルールに従った操縦を行うことが求められます。資格の統一はそのための第一歩と言えるでしょう。
民間資格は完全に廃止されるの?
民間資格そのものが完全に廃止されるわけではありません。2025年12月をもって、民間資格を「飛行許可申請時の証明書類」として使うことができなくなるだけで、資格自体の存在がなくなるわけではないのです。
ここで押さえておきたいのは、「何が変わって、何が残るのか」という点です。これまで民間資格は、ドローンの操縦者が一定の技術と知識を持っていることを示す証明として利用されてきました。特に、飛行申請の手続きを一部省略する際に、その資格がエビデンス(証拠)として認められていた経緯があるのです。
しかし、今後はその役割が終了し、国家資格を持っていなければ、すべての申請でフルの手続きを求められるように変更されました。例えば、夜間飛行や目視外飛行を行う際、民間資格があっても申請書類を簡略化することは不可能となります。
それでも、民間資格には一定の価値が残ります。操縦技術や知識の習得を示す証明として、就職活動や案件の獲得など、ビジネス面での信頼を得る手段としては引き続き利用できるケースも少なくありません。
また、国家資格を取得する際には、民間資格の保有者が「経験者扱い」となり、講習時間の短縮やコスト削減につながる可能性も十分にあるでしょう。
つまり、民間資格は制度変更によって「申請上の特典」はなくなるものの、「技能証明としての効力」は残るということです。これからドローンの操縦を学ぶ人にとっても、民間資格は国家資格へのステップとして活用できる選択肢といえるでしょう。
ドローン民間資格廃止後にどうすべきか

- 民間資格は今後どうなるのか
- 民間資格の優遇や免除のメリットは残る?
- 国家資格を取るべき人の特徴とは
- 国家資格取得時に講習が短くなる場合も
- スクール選びで失敗しないためのポイント
民間資格は今後どうなるのか
今後も民間資格は、ドローンの知識や操縦技術を身につけた証明として活用できます。ただし、公的な飛行許可申請における効力は段階的に縮小されていきます。
2025年12月以降、民間資格は国土交通省への飛行申請において、技量を証明する資料として認められなくなります。これまでは民間資格を提示することで、手続きの一部が省略できるケースがありましたが、その運用は終了します。
一方で、資格そのものが無意味になるわけではありません。スクールでの講習内容は操縦技術、法律、点検、緊急時対応など実務に役立つ内容が中心で、これらを学んだ証明として今後も活用されていく可能性があります。特に企業や団体の採用基準では、知識と実績の裏付けとして評価される場面もあるでしょう。
また、民間資格を取得しておくことで、その後に国家資格を取得する際に「経験者コース」を受けられる場合があります。このように、資格自体は活かし方によって今後も有効に機能する場面があるということです。
現在保有している方も、これから取得を検討している方も、どう活用するかを明確にしておくことで、民間資格の価値を維持できるでしょう。
民間資格の優遇や免除のメリットは残る?

飛行申請の簡略化といった優遇措置はなくなりますが、民間資格保有者には引き続き講習面での免除や優遇を受けられる可能性があります。
例えば、国家資格を取得する際に、民間資格を持っていれば「経験者」として扱われる場合があります。これにより、受講する講習の時間が短縮されたり、受講費用が抑えられたりすることがあります。全ての講習機関で適用されるわけではありませんが、国土交通省の認定を受けた登録講習機関の多くでは、このような制度が設けられているのです。
また、実際に現場でのドローン操縦経験があれば、実技講習の一部が省略されたり、確認テストのみで済むケースも見られます。こうした仕組みを利用することで、国家資格の取得にかかる時間やコストを抑えることが可能です。
ただし、注意点もあります。民間資格の内容や講習機関によっては、優遇対象とならない場合があります。そのため、今後民間資格の取得を検討する際は、そのスクールが「国家資格への移行支援」や「経験者向けコース対応」をしているかを事前に確認しておくことが重要です。
このように、申請手続きの特典こそなくなりますが、国家資格取得のプロセスにおいては、今後も民間資格による優遇や免除が役立つ可能性があります。
国家資格を取るべき人の特徴とは
国家資格を取得すべきかどうかは、ドローンをどのように使うかによって判断が分かれます。特に業務や商用利用を前提としている人には、国家資格の取得が強く求められます。
例えば、建設業や測量、農薬散布、物流、空撮など、法律で「特定飛行」に該当する業務を定期的に行う予定がある方は、国家資格があることで許可申請の手続きが簡素化されます。また、空撮イベントや都市部での飛行など、人や建物が多い場所での操縦が必要な場面でも、国家資格を保有していれば、飛行そのものがスムーズに進められます。
さらに、レベル4飛行(有人地帯での補助者なし目視外飛行)を視野に入れている方は、一等無人航空機操縦士の取得が前提条件となるため、国家資格が必須となります。これは、将来的にドローンによる配送やインフラ点検などの高度なビジネスモデルを計画している人にとって大きな要素です。
一方、趣味や練習としてドローンを飛ばす人や、飛行申請が不要なエリア・条件での利用にとどまる場合は、必ずしも国家資格を取得しなければならないわけではありません。ただし、今後のルール変更に備えておくという意味では、早めの取得を検討するのも一つの選択肢です。
このように考えると、「今後、業務や商用利用のために飛行回数が多くなる予定がある人」や「飛行許可の手続きを減らして効率化したい人」は、国家資格を取得するべき対象と言えるでしょう。
国家資格取得時に講習が短くなる場合も

すでに民間資格を取得している場合や、一定の操縦経験がある方は、国家資格の講習が短くなるケースがあります。これは「経験者コース」や「講習の一部免除制度」として多くの登録講習機関で導入されています。
例えば、一般的な国家資格講習は初学者向けのフルカリキュラムで数日間かかることがありますが、民間資格を保有していれば、実技講習が一部省略されたり、学科講習の時間が短くなったりする可能性があります。これにより、受講期間を1〜2日程度に短縮できることもあり、時間的にも経済的にもメリットが大きくなります。
実際、ドローンスクールによっては「民間資格証の提示」と「操縦経験を証明する書類(飛行履歴など)」を提出することで、経験者扱いとしての受講が認められる場合があります。この仕組みを活用すれば、国家資格取得のハードルを下げることが可能です。
ただし、すべての民間資格が対象となるわけではありません。国土交通省に認定された講習機関で発行された民間資格であることや、講習内容が一定の基準を満たしていることが条件となるケースが多いため、事前に講習機関に確認しておくことが重要です。
このように、民間資格を持っていれば国家資格取得の講習時間が短くなる可能性があります。すでに資格をお持ちの方は、取得したスクールや資格の種類を確認し、活用できる制度をチェックしてみると良いでしょう。
スクール選びで失敗しないためのポイント

ドローンスクールを選ぶ際は、単に「近くにあるから」や「料金が安いから」といった理由だけで決めてしまうと、後から後悔することがあります。しっかりと目的に合ったスクールを選ぶことが大切です。以下の点をしっかり確認しましょう。
1. 国土交通省の登録講習機関であるか
- 登録講習機関であれば国家資格に対応した講習を提供している
- 修了することで、実地試験の一部または全てが免除される場合もある
- 国家資格の取得を目指す人は、必ずこの登録の有無を確認すべき
2. カリキュラムの内容
- 操縦技術だけでなく、以下のような実務知識が学べる内容が望ましい:
- 航空法の基礎
- 安全管理・リスク対策
- 飛行計画の立て方
- 講師の実務経験や指導の丁寧さもスクール選びの大きな判断材料
3. アフターフォローの充実度
- 修了後のサポート体制が整っているかを確認
- 就業支援や機体購入サポート
- LINEやメールでの相談対応などがあると安心
- サポートの有無によって、卒業後の活用の幅が大きく変わる
4. 講習スタイルの柔軟性
- スケジュールに合わせた受講ができるかも重要
- 土日開催コース
- 短期集中型コース
- 自分のライフスタイルに合った講習形式を選ぶことで、無理なく学習を継続できる
これらのポイントを押さえることで、自分に最適なドローンスクールを選び、効果的にスキルを習得することができます。
このように、スクール選びでは「資格が取れるかどうか」だけでなく、「自分に合っているか」「学んだあとに活用できるか」といった視点からも判断することが、失敗を避けるポイントとなります。
ドローン 民間 資格 廃止に関する重要ポイントまとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 2025年12月以降、民間資格は飛行申請の簡略化に使えなくなる
- 民間資格そのものは廃止されず、技能証明としては活用可能
- 国家資格を取得しなければ業務での効率的な飛行申請が困難になる
- 民間資格の信頼性にばらつきがあることが制度変更の背景
- 国家資格制度は2022年12月に正式導入された
- 国家資格は「一等」「二等」に分類され、用途に応じて選べる
- 登録講習機関での受講により、実地試験が免除される場合がある
- 国家資格を持つと夜間や目視外飛行などで申請不要になるケースがある
- 国家資格は航空法に基づき、国が直接操縦技能を審査する
- 民間資格保持者は国家資格取得時に講習の一部が短縮されることがある
- 業務利用や特定飛行を予定している人は国家資格の取得が必須
- 民間資格は就職や信頼の証明として引き続き評価される可能性がある
- ドローンの飛行ルールは強化され、資格の統一が進められている
- スクール選びでは国家資格対応やアフターフォロー体制も重視すべき
- 民間資格は趣味や自己研鑽としての学びには今後も有効である
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事:
セスナの速度はどのくらい?最高速度・巡航速度・失速速度を詳しく解説
ヘリコプターがずっと飛んでる理由を地域別に分析!飛行の目的と影響とは
【ヘリコプターの値段】自家用機の購入ガイド!新車・中古の価格と維持費
ヘリコプターで夜景!安いプランを東京で楽しむ/おすすめと料金解説
セスナ機の免許取得費用はどこが安い?取得方法と節約ポイントを解説